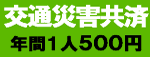議案第1号
青森県市長会提出
地方財政基盤の充実強化について
地方自治体は,行政需要が増大,多様化する現状にあってなお,事務事業の見直しや職員数の抑制等による歳出削減に取り組み,行財政基盤の強化に努めてきたところであるが,景気回復局面における地域格差の拡大や人口減少,急激に進む高齢化等による社会保障費の増大など,地方財政を取り巻く環境はより一層厳しさを増している。
地方公共団体が地方創生の実現に向けて施策を進めていくためには,持続可能な財政基盤の確立が不可欠であるが,脆弱な財政基盤が合併の一因となった地方公共団体においては,合併関連事業の進捗が遅れていることに加え,行政区域の広域化に対応するための財政需要は依然として高く,大きな負担となっている。
また,東日本大震災復興需要や東京オリンピック・パラリンピック需要などにより建築資材単価が高騰していることから,老朽化した学校施設の改築や,大規模な改修の補助単価と実施単価との乖離はより深刻化し,地方自治体の負担が増加している状況である。
他方では,東日本大震災からの復興に向けた各種事業に対する,国の財政支援が復興期間内である平成32年度をもって途切れることは,被災自治体の負担を増加させることになり,事業の進捗を停滞させることになり兼ねない。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 地方創生の実現に向けて,地方自治体が自主性を発揮して施策を進められるよう,合併団体等の財政需要を遺漏無く地方財政計画に反映させ,臨時財政対策債を廃止するとともに,地方交付税の増額による十分な財政措置を講じること。
2 次代を担う子ども達の安全・安心な教育環境を確保するため,公立学校施設の改築や大規模な改修に対し,実情に見合うよう補助単価を引き上げるとともに,十分な財政措置を講じること。
3 震災からの真の復興を実現するため,社会資本整備総合交付金(復興枠)などの特別な財政支援について,事業の特殊性を柔軟に考慮し,実施中の事業が完了するまで継続するとともに,当該事業期間内は,現行の交付率及び震災復興特別交付税による財政措置を継続し,現在の地方負担の水準を維持すること。
議案第2号
秋田県市長会提出
地方財政基盤の充実強化について
地方自治体には,少子高齢化に対応した保健・医療・福祉施策の推進,生活関連施設の整備,農林水産業の振興などの課題に的確に対応する役割が求められており,懸命に行財政改革に取り組んではいるものの,より自主的・主体的な地域づくりを進めるためには,なお一層の財源の充実・強化が必要不可欠となっている。
こうした中,多くの自治体では,人口減少により,地域経済の規模縮小が引き起こされ,税収減少による行政基盤の低下により行政サービスの維持が困難となることが予想されるところであり,今後とも持続的に行政サービスを提供していくためには,安定的な財源の確保が不可欠である。
よって,国は,地方自治体の安定的な財政運営が図られるよう,次の事項について,特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 地方税及び地方交付税については,地方自治体の安定的財政運営に必要な総額を確実に確保するとともに,地方交付税制度については,地域間の格差が拡大することのないよう財源調整機能と財源保障機能を堅持すること。また,地方交付税原資の安定性の向上・充実を図るため,法定率の見直しを行うなど,引き続き持続可能な制度の確立を目指すこと。
2 国庫補助負担事業の廃止等にあたっては,地方への負担転嫁とならないよう十分な財源確保措置を講じること。
3 地方債の総額を確保するとともに,起債充当率の引き上げ,貸付利率の引き下げ等地方債発行条件の改善を図ること。
4 地方分権改革の推進にあたっては権限移譲とあわせて税源移譲も確実に実施すること。
議案第3号
福島県市長会提出
地方財政基盤の充実強化について
「経済財政運営と改革の基本方針2018」が閣議決定され,地方財源については,基盤強化期間と位置付けた2021年度まで,「地方の歳出水準については,国の一般歳出の取組みと基調を合わせつつ,交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について,2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされたところであるが,地方自治体は,行政需要が増大,多様化する現状にあってなお,事業抑制や職員数削減等による歳出低減に取り組み,行財政基盤の強化に努めてきたものの,景気回復局面における地域格差の拡大や人口減少,急激に進む高齢化等による社会保障費の増大など,地方財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある。
よって,国は,地方財政基盤の充実強化のため,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 社会保障など自治体の行政運営に必要な財政需要を2019年度地方財政計画に的確に反映し,に地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額・地方交付税総額を確保すること。
また,普通交付税の算定について,「人口と面積」といった規模だけではなく,地方の実情に沿った算定方法に改め,地域間格差を是正するような予算の確保・充実を図ること。
2 税制改革で地方税が減額された際には,補てんする財源を確保すること。
3 法人税率の引き下げに伴う減収分の財源確保について,課税ベースのさらなる拡大等により安定的な代替財源を確保し,地方の歳入に影響を与えないよう措置を講じること。
また,地方公共団体間の財政力格差の是正は,法人住民税などの地方税収を減ずることなく,国税からの税源移譲や地方交付税の法定率の引上げ等,地方税財源拡充の中で行うこと。
4 住民生活に直結する行政サービスに係る財政需要の急増に対応するため,偏在性の少ない安定的な財源である地方消費税の拡充を図ること。
5 地方消費税交付金の増収分が,一般財源の増加につながるよう,消費税率の10%引上げ時までに,財政力に応じて算入率を見直すこと。
6 地方創生推進交付金については,人口減少克服・地域経済活性化に向けた事業などの推進のため,地方自治体の判断で自由に活用できる財源となるような制度に改めるとともに,十分かつ継続的な財源の確保に努めること。
7 降雪期の過酷な雪国の現状を踏まえ,自治体が地域住民の安全・安心な生活を守らなければならないが,近年の集中豪雪の増加や過疎化・高齢化の進行などの影響で自治体としての役割が増加しているため,明確な基準による財政支援制度を確立するとともに,除雪費の財源充実・確保を図ること。
8 緊急防災・減災事業及び公共施設等の老朽化対策について,継続して取り組めるよう財源の確保を図ること。
9 公共施設の統廃合に際し,公共施設と民間病院等公益性の高い施設との複合化が推進されるよう,民間施設との複合化についても,市民の利便性を向上し街づくりに資するため,公共施設等適正管理推進事業債の対象とするなど,財政措置を拡充すること。
10 定住自立圏を取りまとめる中心市に対し,連携事業におけるPDCAサイクル構築に活用できるデータの提供や連携事業を後押しする人的支援など各種支援を拡充するとともに,連携する自治体に対する財政措置を拡充すること。
議案第4号
宮城県市長会提出
学校施設の整備に係る財源の確保について
小・中学校の施設・設備の老朽化が進み,計画的な改修等が全国的な課題となっている。
そのような中,国では,平成25年度に国庫補助事業の改善として「長寿命化改良事業」を創設したところである。
しかしながら,近年,国の公立学校施設の改修・整備に係る交付金が大幅に減少しており,多くの自治体で事業採択が見送られている状況にある。
多額の経費を要する学校施設の整備を自治体単独で継続的に実施していくことは困難であり,国の財政支援は必要不可欠である。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 学校施設の整備に係る必要な財源を確保し,確実な財政措置を講じること。
2 学校施設の整備に係る国庫負担金・交付金の算定基準単価が実勢の建築単価と大きく乖離していることから,実勢価格に見合った算定基準単価へ見直しを図ること。
議案第5号
秋田県市長会提出
施設の統廃合等に係る「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の柔軟な対応について
高度経済成長期に建設された公共施設が,これから大量に更新時期を迎える一方で,地方公共団体の財政は依然として厳しい状態にある。
人口減少等により公共施設等の利用需要が変化し,未利用施設の増加等,市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。
公共施設等の最適な配置を実現するため,公共施設等総合管理計画を策定し,公共施設等の全体を把握するとともに,長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行っている。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条(財産の処分の制限)については,平成20年5月の財務省通知(補助対象財産の転用等の弾力化について)により,各省庁から「補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分等の承認基準」の通知がなされ,補助対象財産の処分手続きに関しては一定の弾力化が図られたところであるが,各省庁間で,その手続きや取扱い等に差異があり,今後,公共施設等総合管理計画によって施設の縮小を進めるにあたりその実行が困難となることもあり得る。
よって,国は,地方公共団体が公共施設等総合管理計画に基づき実施する国庫補助対象施設の統廃合・複合化等については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条(財産の処分の制限)に係る各省庁の取り扱いが,より柔軟かつ弾力的な運用が可能となる措置を講じるよう要望する。
議案第6号
青森県市長会提出
除排雪対策への財政支援等について
豪雪地帯における除排雪対策については,依然として冬期間における都市機能の維持や市民生活の安定を図る上で持続可能な除排雪を実施する必要がある。
しかしながら,自治体の除排雪経費に係る特別交付税については,国が調査した額をもとに算定されるが,所要見込額は,調査時点までの執行済額と年度末までの執行見込額の合算となっており,年度末までの執行見込額については,その期間における過去5年間の実績額の年間執行額に占める割合により算定されるため,調査日以前に発生した大雪災害対応が調査日時点で十分でない場合や調査日以降に発生した大雪災害時には,その所要見込額を大幅に上回ることとなり,自治体が実際に負担した額と乖離が生じ,財政運営の大きな支障となっている。
一方,災害復旧事業においては,地方財政法第5条の規定により,地方債をその財源とすることができるが,大雪災害対応に関する除排雪は,道路機能を復旧するための事業であるにもかかわらず,災害復旧事業の対象とはならないため,地方債を活用することができない。
よって,国は,大雪災害対応に関する除排雪経費について,災害復旧事業と同等の地方債制度を創設するよう要望する。
議案第7号
宮城県市長会提出
過疎地域に対する支援の継続について
過疎地域は,我が国の国土の過半を占め,豊かな自然や歴史・文化を有する地域であり,都市に対する食糧・水・エネルギーの供給,国土・自然環境の保全,いやしの場の提供,災害の防止,森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
しかしながら,過疎地域においては,多くの集落が消滅の危機に瀕するなど,極めて深刻な状況に直面している。人口減少に歯止めをかけるには,大都市から地方へ,人・企業などを分散することが重要であり,そのためにも過疎地域が安心・安全に暮らせる,活力と魅力ある地域として健全に維持されていくことが必要である。
よって,国は,平成33年3月末をもって失効する現行の「過疎地域自立促進特別措置法」の期限終了後も,過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持できるよう,引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を継続し,住民の暮らしを支えていく政策を推進するため,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 継続的に過疎地域の振興が図られるよう,平成33年度以降における新たな過疎対策法を制定すること。
2 現行過疎法の期限終了後も,過疎市町村が取り組む事業が円滑に実施できるよう過疎対策事業債及び各種支援制度の維持を図ること。
3 過疎地域市町村を含む合併があった市町村において,過疎地域の振興が図られるよう現行法第33条の規定による「市町村の廃置分合等があった場合の特例」を引き続き設けること。
議案第8号
山形県市長会提出
公園施設における専門技術者による遊具点検経費に対する財政支援について
人口減少,少子高齢化が進み財政制約から社会資本の整備に充てられる財源が厳しくなる中,公園施設の老朽化や都市公園ストックの一定の蓄積など,都市公園を取り巻く社会状況が大きく変化していることを背景として,平成29年に都市公園法が改正され,老朽化が進行する公園施設を適切に維持管理していくための維持修繕の技術的基準が定められ,当該基準に基づく管理が平成30年4月から義務付けられた。
この改正は「適切な時期に点検を行い,必要な措置を講じることを義務付けることにより,予防保全による長寿命化・安全対策を徹底する。」ものであり,言わば量の整備からストック活用のステージへ公園緑地行政の舵を切るものである。
これまでも,公園施設の安全確保については,各自治体が「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」や「公園施設の安全点検に係る指針」等に基づき,施設の老朽化等への対応も含め,可能な限りの点検等を行ってきたところである。
しかしながら,今回の改正により,専門技術者による遊具点検について,年1回の点検が義務化されたことに伴い,これまで複数年サイクルで実施してきた自治体にとって,点検に要する費用が膨らみ,一般財源の負担が増加することとなる。
よって,国は,公園施設の安全点検を適切かつ確実に行うため,公園遊具点検に要する経費について,財政支援措置を講じるよう要望する。
議案第9号
青森県市長会提出
医療・福祉施策の充実強化について
少子高齢化・人口減少社会が到来する中,住む場所によって左右されずに,次世代を担う子どもたちを安心して生み育てることができる環境づくりが求められている。併せて,医師不足が問題となっている地方において,特に産科医及び麻酔科医の不足は,周産期医療や急性期医療の充実を困難にしており,医師確保は少子化に歯止めをかけるためにも欠かせないものとなっている。
また,国では地域福祉社会推進の理念が示され,地域住民の身近な相談相手として民生委員・児童委員への期待がこれまでにも増して高まっているが,一方で,住民の生活課題,福祉課題が多様化・複雑化しており,各委員の高齢化に加えて,活動範囲の広がり等による負担の増加,担い手不足等が深刻化し,民生委員・児童委員制度の根幹を揺るがしかねない状況にある。
よって,国は,どこにいても誰もが健康で安心して生活できる医療・福祉制度の確立を推進するため,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 医師法及び医療法改正により,地域における医師の確保及び地域偏在の是正に向けた対策が講じられるが,国は都道府県の取り組みについて結果を測定・評価し,必要に応じ指導するための体制を整備すること。また,新専門医制度の実施によって,これらの取り組みの効果が損なわれることのないよう,国及び専門医機構においても十分な対策を講じ,実効性ある医師確保・偏在対策及び専門科目の偏りの解消に取り組むこと。
2 多くの自治体は独自施策として中学生までの医療費を無料としているが,各自治体の財政状況によって,実施内容に地域間格差が生じている。また,特定教育・保育施設の利用者負担額についても同様の格差が生じている。子育て世帯の負担軽減のため,全国一律で,中学生までの医療費を無料とするとともに,幼稚園・保育所・認定こども園の利用に係る利用者負担額について,所得制限を撤廃し,全て国費により無料とすること。
3 民生委員・児童委員については,地域の意見を聞きながら,拡大する役割に応じた報酬制度の創設や活動に応じた費用弁償の充実を図るとともに,ボランティアを原則とする身分制度の根本的な見直しを図り,将来に向けて持続可能な制度を確立すること。
また,町内会等と連携した地域の個別支援活動が円滑に行われるよう,地域支援者間における個人情報の共有に係る取扱いの指針を示すこと。
議案第10号
秋田県市長会提出
地域における社会保障基盤の充実・強化について
人口減少,高齢化が進む中にあって地域に住み続けるためには,医療及び介護の安定的供給が必要不可欠となっている。
しかしながら,現状では医師の地域的及び診療科間の偏在が大きな課題となっており,人口減少地域における病院経営を支援する措置等による医療機関の堅持が求められている。
また,介護保険制度については,高齢化の進展に伴い,実情に即した運営を安定的に提供することが困難になっている。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 いのちを守る緊急の課題として医師養成を図るとともに,医師の偏在をなくし,全国均等な専門医の配置など医療提供体制の整備について,国の制度や方針を確立すること。
2 国が実施する医師確保対策の強化により,地域住民に良質な医療を効果的かつ持続的に提供できる医療環境を早急に構築すること。
3 現在の地域医療の窮状を解決するため,医師の地域偏在が是正されるまでの間,緊急臨時的な措置として短期間交替制の常勤医師の派遣制度を創設すること。
4 産科,麻酔科および小児科の救急医療について,国の責任において地域への均衡ある医師配置に取り組むなど,医療体制の整備と財政措置の継続を図ること。
5 地域性や患者の必要度に応じた安全で質の高い看護を持続的に提供できるよう,看護師確保に対する施策を積極的に行うとともに,薬剤師確保に係る施策を実施すること。
6 消費税率引き上げ対策として診療報酬の適正なプラス改定により医療材料や医療品などの仕入れにかかる消費税負担の軽減措置を講じること。
7 介護及び介護予防に係る給付費の国庫負担割合を,現行の20%から引き上げるとともに,調整交付金は従来どおり別途配分するなど,更なる財政基盤の強化と介護保険料上昇の抑制に努めること。
議案第11号
岩手県市長会提出
地域医療の充実強化について
市民一人ひとりの生命を守り,医療格差のない安心・安全な医療サービス等が提供される地域医療保健の充実が求められている。
特に,医師,看護師等の確保は深刻な問題となっており,地域の必要な医療が身近で受けられない等,地域医療は危機的状況となっており,新たな医療の仕組みの構築など,医師等の地域偏在の一刻も早い解消が喫緊の課題となっている。
一方,疾病の早期発見や感染症等の予防を目的とする健康診査や予防接種は,国が定める「21世紀における国民健康づくり運動」の基本方針である国民の健康寿命の延伸や健康格差の縮小に大きく寄与するものであるが,その実施に当たっては,自治体が費用の大半を負担するなど,その財政負担が非常に大きく,自治体の財政状況によって,受診できる健診等に地域間格差が生じることが懸念される。
よって,国は,次の事項について,特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 医師,看護師確保対策について,都道府県による取組が円滑に行われるよう,引き続き医療環境の改善策,財政支援を講じること。
2 医師の偏在や不在の状況が是正されるまでの間,様々な患者ニーズに対応するため,国による医師派遣等の支援を講じること。
3 妊婦健康診査に係る費用について,安定した公費負担制度を継続的に実施できるよう,地方交付税措置ではなく,全額国庫負担とすること。
4 定期予防接種に係る費用について,国の責任において,必要とする国民すべてが等しく接種できるよう,全額国庫負担とすること。
議案第12号
福島県市長会提出
地域医療及び国民健康保険制度の充実強化について
東北地方においては,地域的偏在による医師不足が恒常化し,地域に必要な医療体制の確保が難しい状況となっており,安心して子どもを生み育てることができないといった不安を住民に与え,少子化に拍車をかける要因にもなっている。
また,国民皆保険制度の基礎となる国民健康保険制度は,他の医療保険制度と比較して高齢者や低所得者の割合が高いなどの構造的な問題を抱えており,財政基盤は極めて脆弱である。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 産科及び小児科,並びに二次救急医療機関について,国は緊急医師確保対策を早期に実現し,医師の養成や地域偏在及び専門科目の偏りの解消に取り組むなど医療体制の整備を図ること。
また,医師の確保・調整については,都道府県の取組が円滑に進むよう引き続き財政支援を行うことはもとより,都道府県域を超えた医師偏在の調整や,国による医師派遣システムの構築等,医師派遣制度の更なる拡大に実効性のある措置を講じるなど医師が不足している地方病院が医師を確保できるシステムを構築すること。
2 医師,病院等の偏在による医療サービスの格差を埋めるべく,自治体が取り組む地域医療の確保・充実のための施策に対し,十分な財政支援措置を講じること。
3 医師,看護師,薬剤師,理学療法士等の医療従事者の人員の確保及び地域偏在の是正等が図られるよう,医師派遣体制を充実させるとともに,自治医科大学等の入学定員の増員や医師に一定期間地域医療従事を義務付ける等のシステムを早急に構築する等,各種支援措置を講じること。
また,特定の診療科に偏らないような医師育成制度を構築するとともに,新専門医制度の導入により都市部や大病院等への更なる医師の偏在を加速させないよう対策を講じること。
4 医療機関の偏在を是正するため,休床している病床を偏在是正に活用できる制度を創設すること。
5 自治体からの公的病院等への各種助成に対する特別交付税措置は,地域医療の確保の上で貴重な財源であり,救急医療提供体制を維持する上で必要であるため,引き続き継続するとともに措置額の縮小等を行わないこと。特に,救急告示病院に関しては,公的病院と私的病院の格差を是正すること。
6 新たなワクチンの定期予防接種化に当たっては,自治体の財政基盤や被接種者の経済状況によらず,財源を全額保障すること。
また,任意の予防接種であるおたふくかぜ及びロタウイルスワクチン接種費用についても,財政措置を講じること。
7 新たな運営体制となった国民健康保険制度について,安定的かつ持続的な運営ができるよう,国庫補助を増額するなど,更なる財政基盤の拡充強化を図るとともに,広域化による急激な保険料水準の上昇を抑制するための激変緩和措置を講じること。
また,国民皆保険制度を堅持するため,将来的には,全ての国民を対象とする医療保険制度の一本化に向けた抜本的改革を実施すること。
8 民の健康増進及び傷病の重症化防止並びに自治体の事務の軽減が図られるよう,また,自治体独自の子育て世代の移住・定住促進策を支援するためにも,医療費助成の現物給付方式実施に伴う国保の普通調整交付金及び療養給付費負担金の減額措置を完全に廃止すること。
9 国保税(保険料)における子どもの均等割額については,被用者保険にはない負担であり,医療保険制度間の公平性を確保し,子育て世帯の負担軽減を図るため,国による財源措置を含めた軽減制度を創設すること。
10 低所得者や高齢者などの国保税(保険料)軽減を拡充するとともに,国の責任において十分な財政補てんを行うこと。
とりわけ,生活保護水準の世帯については,国保税(保険料)の応益負担を現行の最大7割から,更に軽減を拡充するなどの措置を行うこと。
議案第13号
山形県市長会提出
民生委員・児童委員の活動費の増額について
高齢者世帯や要援護者世帯の増加に伴い,民生委員・児童委員の果たす役割は年々重要かつ多岐にわたるものになっている。しかし,民生委員法第10条の規定により,民生委員には給与が支給されず,交通費等の費用弁償として活動費が支給されているものの,活動費に係る国の地方交付税算定基礎額は一人当たり年間59,000円と,一月あたり5,000円にも満たず,活動範囲が広域な場合は,交通費にもならないような状況である。
民生委員・児童委員への期待が高まり,活動も多様化する中で,経済的負担の拡大は委員退任の一因となっている。このような状況下では,担い手の確保についても大きく影響を及ぼすことから,待遇面の充実を図っていく必要がある。
よって,国は,民生委員・児童委員の活動費に対する地方交付税算定基礎額を増額するよう要望する。
議案第14号
岩手県市長会提出
社会保障制度の充実強化について
医療費助成事業の現物給付方式は,医療費の支払いにおける一時的な窓口負担を伴わず,経済的理由による受診抑制を要しないことから,医療サービスの受診機会の適正な確保の推進につながるものである。
しかしながら,国は国民健康保険への財政支援の拡充に取り組む一方で,現物給付を実施する自治体に対し,ペナルティともいえる国庫負担金の減額措置を設けている。
一方,地方自治体においては少子化対策の一環として,子育て家庭の経済的負担を軽減するため,地方単独事業により医療費の軽減措置を講じているのが現状である。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 医療費助成の現物給付方式の実施に伴う普通調整交付金及び療養給付費負担金の減額措置を,年齢制限なくすべて撤廃すること。
2 自治体によって異なる子どもの医療費給付制度を,少子化対策の一環として統一すること。
議案第15号
宮城県市長会提出
医療費助成制度の充実強化について
乳幼児医療費助成制度は,乳幼児の健全な発育を促進し,子育て家庭の経済的負担を軽減する重要施策として,都道府県の補助を受け,市町村事業として実施しているが,その内容は都道府県により異なっている。市町村においては,少子化が進む中で,独自に対象年齢を引き上げるなどの上乗せ助成が行われていることから,少子化対策に関する地域間格差が懸念される。国民健康保険における国の療養給付費負担金についても,基本交付額から地方単独事業波及増額分が減額して交付されており,市町村財政を圧迫している状況である。
また,心身障害者医療費助成制度は,助成対象者等に対して,適切な医療提供の機会を確保するとともに経済的負担の軽減を図るものとして重要であり,欠かすことのできない制度であるため,制度の充実強化が求められている。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 全国一律の「子どもの医療費助成制度」の創設,健康保険の患者負担軽減措置対象年齢の拡大など,地域間格差のないよう少子化対策としての子どもの医療費への支援措置を国の責任において講じること。
2 国民健康保険に係る国庫負担金について,基本交付額から地方単独事業波及増額分を減額して交付する療養給付費負担金減額措置を廃止するなど,財政支援の充実を図ること。
3 心身障害者医療費助成制度について,新たな自己負担の導入をすることなく,助成内容の充実強化を図ること。
議案第16号
山形県市長会提出
子育て支援医療給付制度の充実について
地方自治体は,子どもの健全な発育と子育て世帯の経済的負担の軽減を図り,安心して子育てができるよう,各県の補助事業を活用しながら,子育て支援医療費の給付を実施しているが,独自に段階的に支援内容の拡充を図り,中学生までの医療費を無料とする給付を行っているところや,給付対象者を高校生まで拡大している市町村があるなど,財政負担や支援内容に自治体間格差が生じている状況にある。
このような中,国は,自治体の少子化対策の取組を支援する観点から,未就学児までを対象とする医療費助成の国民健康保険の減額調整措置について,平成30年度から行わないこととしたが,本来,医療費助成は,自治体により格差が生じるのは望ましくなく,国の施策として統一的に実施されるべきである。
よって,国は,子育て支援策として,子どもの医療費給付を,国の責任において実施するよう要望する。
議案第17号
福島県市長会提出
子育て環境の充実について
国は,「新しい経済政策パッケージ」において幼児教育・保育の無償化を提唱し,また,「経済財政運営と改革の基本方針2018」において,「3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供について,2019年10月からの全面的な無償化措置の実施を目指す。」とするなど,具体化に向けた検討を行っている。
自治体は,子どもたちに一番近い立場で,子どもたちの視点に立ち,すべての子どもの健やかな育ちを目指して,子どもたちを中心とした支援策を創意工夫し,その実施にまい進している。
よって,国は,この新しい施策の具体化に当たっては,現場の意見を踏まえた望ましい形で,子どもたちのための無償化の施策が実現されることが肝要であることを踏まえ,また,子育て世代の誰もが一律の支援が受けられ,安心して子どもを生み育てる環境を整えるため,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 1 出生率の低下に歯止めをかけるため,妊娠・出産を望む男女がどこの自治体においても公平に十分な治療が受けられるよう,不妊治療の実情を踏まえ,経済的負担軽減のため特定不妊治療助成事業の助成額を拡充すること。
2 幼児教育・保育の無償化の実施に当たっては,対象を限定することなく,完全無償化するとともに,事務負担の増加に伴う人件費やシステム改修経費をはじめ,円滑な事務処理に必要となる全ての財源について,自治体に新たな負担が生じないよう国の責任において確保すること。
また,これまでの待機児童解消の取組に加え,無償化による保育需要の拡大に対応するため,幅広い保育人材の育成・確保や施設整備費等に対する財政措置など,あらゆる支援措置を講じること。
加えて,無償化の制度設計について,多様な保育形態の公平性を確保し,早急に内容や考え方を明示し地方と十分に協議するとともに,実施時期については,保護者への周知やシステム改修等,実務上の準備に相当な期間を要することから,円滑に遂行するために制度の詳細を早急に示し,自治体の準備が整ったことを確認してから実施すること。
3 待機児童の解消に加え,更なる保育需要の増加への対応のため,定員の弾力化等により既存施設を最大限に活用できるようにするとともに,公定価格における定員超過による減算措置を撤廃または期限を延長すること。
また,待機児童解消後の地域型保育事業の在り方を示すとともに,国の処遇改善制度の更なる充実や幅広い保育人材の育成等により保育士の安定的確保を図ること。
加えて,研修等を充実し保育士のスキル向上を図り,保育士の負担軽減を図るとともに,認可外保育施設を含め,保育の質の面からより適切な運営を確保する仕組みを構築し,地方に新たな負担が生じることのないよう十分な財政措置を講じること。
4 子ども・子育て支援法に基づき市町村が支弁する施設型給付費等の支給に要する費用について,平成29年度より新たな保育士処遇改善策が追加され支弁する施設型給付費等の総額が増額となり市町村の負担も増大していることから,子どものための教育・保育給付費国庫負担金について現行制度の負担割合を見直し,国の負担割合1/2を引き上げ,市町村の負担割合を1/4未満に軽減すること。
5 保育所等の施設整備に対する補助制度である保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金については,定員数に対する基準額が低く,事業者の負担が大きいことから,保育所運営に参入しやすくするため,当該交付基準額を見直すこと。
また,公立施設の整備に対しては事業費の1/2に対し施設整備事業債(充当率100%,交付税措置70%)を充当できる財政措置があるが,待機児童を解消する為には早急な対応が求められることから,交付税措置率の水準を保ったまま,事業費全体が施設整備事業債の対象となるよう拡充すること。
6 学校施設のブロック塀の撤去・改修事業について,学校施設環境改善交付金の該当事業において極めて重要な事業であることから,優先度の見直し及び予算総額の充実を図るとともに,児童生徒の通学路及び保育施設等における安全確保の観点から,保育施設や一般住宅を含めた都市全体のコンクリートブロック塀等の安全対策事業が円滑に実施できるよう,社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の予算総額の拡充,交付決定までの手続きの迅速化や緊急防災・減災事業の対象事業の範囲拡大など,関係省庁が連携した制度を拡充すること。
7 学校施設整備について,各自治体において計画的な施設整備ができるよう,必要な財源を確保するとともに,補助単価の見直しを図ること。大規模改修においては,補助対象上限額の廃止及び交付要件の緩和を図ること。また,屋上防水等の単体工事を補助対象とすること。
また,公立学校施設等の耐震化事業に対する交付金の算定割合を嵩上げし,実工事費と補助単価のかい離を解消するとともに,国庫負担嵩上げ率について,Is値要件を撤廃すること。さらに今後は,屋内運動場等の非構造部材の耐震対策を進めなければならないことから,耐震補助制度を拡充すること。
さらに,小中学校のICT環境整備について,自治体の財政負担を軽減し,整備を加速化するため,補助制度を創設すること。
8 小中学校及び幼稚園の特別支援教育支援員について,必要に応じ確実に配置するために,配置の義務化や,新たな補助制度を創設するなど財政措置の更なる拡充を図ること。
9 学校の統廃合に伴う遠距離通学の支援を継続していくため,へき地児童生徒援助等補助金に基づくスクールバス等の委託料に係る現在の年限(5年間)を廃止すること。また,10人乗り以上のスクールバス等に交付される普通交付税について,基準財政需要額算定を見直し,現状に合わせた引上げをするとともに,10人乗り未満のスクールバス等に交付される特別交付税についても,普通交付税と同様に引き上げること。
10 要保護児童生徒援助費補助金における「クラブ活動費・生徒会費・PTA会費」の予算単価の積算根拠や具体的な補助範囲,準要保護児童生徒就学援助に係る財政措置の考え方をより明確に示すとともに,準要保護児童生徒就学援助に係る財政措置を拡充すること。
議案第18号
山形県市長会提出
幼児教育・保育の無償化措置対象範囲への児童センターの追加について
国は,「経済財政運営と改革の基本方針2018」において,2019年10月からの,幼児教育・保育の無償化措置の具体化に向けた検討を開始しており,幼稚園,保育所,認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等については「一般的にいう認可外保育施設,自治体独自の認証保育施設,ベビーホテル」等が検討されている。
しかしながら,児童厚生施設である自治体の児童センターでは,保育所や認定こども園と同様に2歳児以上を対象に集団保育を行っているところもあるが,このような児童センターは無償化の対象とされていない状況である。
よって,国は,幼児教育・保育の無償化措置について,多様な保育形態の違いによる不公平が生じないよう対象範囲を見直すとともに,集団保育を行っている児童厚生施設についても無償化の対象とするよう要望する。
議案第19号
山形県市長会提出
保育所等整備交付金の基準額引き上げについて
就学前児童の総数は年々減少しているものの,保育所入所児童数では,0歳から2歳児までの,いわゆる未満児の保育需要が伸びている状況にある。
国では,いわゆる1億総活躍社会,女性の社会進出,更には保育料の無償化を目指しており,今後も未満児保育を中心とした保育ニーズが一段と高まると予想される。
しかしながら,保育所整備に関しては,昨今の人件費や資材の高騰による建設物価の上昇により,保育所の整備・改修を行う民間保育事業者の費用負担が重くなり,国の保育所等整備交付金の基準額は,毎年見直しされているとはいえ,実情を反映しているとは言い難い。
また,保育施設の整備は,子育て環境の充実,待機児童対策,働き手の確保による地域経済の活性化にも寄与している。
よって,国は,民間保育事業者が施設の整備と拡充に積極的に取り組むことができるよう,保育所等整備交付金の基準額の更なる引き上げを要望する。
議案第20号
福島県市長会提出
福祉施策及び介護保険制度の充実強化について
誰もが安心して暮らせる地域社会を築いていくため,障がい者への支援や高齢化社会に対応した福祉施策の強化が求められている。
また,急速に進む高齢社会を支える介護保険事業は,給付費増による事業運営の圧迫等の課題が顕著となっている。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 障害者福祉に係る地域生活支援事業の費用負担割合は国が事業費1/2以内,県が1/4以内であり,残りを市町村が負担することとなっているが,国・県から市町村への補助金(補助率)が年々減少傾向にあり市町村の財政負担が増加していることから,安定的な事業継続を図るため,十分に市町村と協議の上,補助率の下限を設けること等により早急に十分な財源を確保すること。
2 障害福祉サービス等利用に係る計画相談支援事業について,計画相談支援を行う特定相談支援事業所やサービス等利用計画を作成する相談員の不足が課題となっていることから,これらの増加を図るため,計画相談支援給付費の増額,相談支援従事者養成研修の受講機会の拡大,報酬体系の見直しなどの対策を早急に講じること。
3 平成23年の障害者基本法の改正により,手話が言語に含まれることが明記されたが,手話の理解,普及については,自治体ごとに条例を制定するなど,予算や対応に地域格差があることから,全国一律の基準での環境整備と財源措置を図ること。
4 高齢者が運動機能の低下により移動等が困難になり日常生活に支障をきたすことがないよう,また,運動機能が低下した高齢者が自宅等に閉じこもることのないよう,自らの意思で円滑に移動できる環境を整備する自治体独自の施策に呼応し,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」をより一層推進し,施設のバリアフリー化等高齢者を取り巻く環境改善を図るための財政措置を講じること。
また,自治体においては高齢者が住みなれた地域で日常生活を送ることを目標に,地域支援事業等の国の制度を活用しながら様々な高齢者施策を推進しているが,さらなる施策推進のための財政支援を講じること。
5 介護保険財政の健全な運営のため,将来にわたって地方自治体の財政負担が過重とならないよう,各自治体の実態を踏まえながら,介護及び介護予防に係る給付費並びに一般介護予防事業に係る地域支援事業費の国庫負担割合を現行の20%から引き上げ,調整交付金を別途配分するなど,更なる財政基盤の強化により,介護保険料上昇の抑制に努めること。
また,40歳から64歳までの医療保険加入者が65歳到達により,年金からの特別徴収に切り替わるが,切り替えまでの一定期間は普通徴収となるため,特別徴収に切り替わるまでの期間の介護保険料について未納が発生しやすいことから,徴収方法の改善措置を講じること。
6 平成27年4月に導入された公費による低所得者の介護保険料軽減制度について,低所得者の高齢者が支払う保険料の軽減に対する補填は,国の責任において負担割合を見直し,国の負担比重を大きくすること。
7 福祉・介護分野において,事業が継続され,事業者が質の高い人材を安定的に確保できるよう,適切な水準の介護報酬の設定を含めた,福祉・介護職員の処遇改善,福祉・介護人材の確保につながる更なる措置を講じるとともに,人材不足を補うためのICT化への更なる推進を図ること。
なお,福祉・介護職員の処遇改善に当たっては,介護保険料や介護サービス費,福祉サービス費の自己負担増とならないよう財政支援を図ること。
8 総合事業の多様なサービスの展開を促進するため,NPO法人やボランティア団体などが補助制度を活用し新たな介護サービス提供者となり得るよう参入しやすい環境を整えるとともに,人材育成策を支援すること。
議案第21号
青森県市長会提出
農業政策の充実強化について
国は,平成30年以降,行政による生産数量目標の配分を廃止したが,米価安定のために農業再生協議会による生産調整を行うにあたっては,水田活用の直接支払交付金により戦略作物への作付転換を継続的に進めていくことが不可欠である。特に,「水田フル活用ビジョン」に基づき,地域の裁量で活用可能な産地交付金は,麦・大豆等の生産性を向上するうえで重要な交付金である。
しかしながら,平成30年度より大豆・小麦・飼料作物などに係る産地交付金の交付要件が変更されたため,交付金を受け取ることが出来ない農家が増加することにより主食用米の生産への転換が進む可能性が高まり,過剰作付けによる米価下落が懸念されるものである。
よって,国は,農業経営体が自らの経営判断に基づき作物を選択できる環境を整備するため,水田活用の直接支払交付金を恒久的に継続するとともに,産地交付金については,大豆・小麦・飼料作物などの戦略作物の本作化を進めるため,平成29年度並みに交付要件を緩和するよう要望する。
議案第22号
岩手県市長会提出
農業政策の充実強化について
農業は地域経済を支える基幹産業であり,特に水稲は主要な作物として食料安定供給に重要な役割を果たしているが,米政策に不安を感じている農業者は多いことから,農業者が将来にわたって意欲を持って経営を継続できるよう,農林水産関連施策の一層の充実及び強化を図ることが望まれている。
また,国では,農業の生産性を高め,持続的な発展を図るため農地の大区画化・汎用化等へ農業農村整備事業等を推進するとともに,農用地の利用集積や水稲生産コストの低減に積極的に取り組んでいるが,今後,高齢化等により労働力不足が懸念され,農地中間管理機構への貸付の増加が見込まれている。加えて,担い手への農地の集積・集約化に向け,中山間地域や基盤整備未実施地域において,農地整備の希望が今後さらに増加することも予想される。
また,①TAG交渉(日米物品貿易協定),②TPP交渉(環太平洋戦略的経済連携協定),③EU・EPA交渉(日本・欧州連合経済連携協定),④RCEP(東アジア地域包括的経済連携)などの経済連携協定の議論は,農林水産業における生産への影響面だけでなく,雇用の喪失,水田による洪水防止,地下水かん養機能などの農業が担ってきた多面的機能の喪失など,幅広い見方が必要であり,中山間地域の農業の持続可能な支援策についても同時に策定する必要がある。
よって,国は,地方における重要産業である農業の,将来にわたる持続的発展を図るため,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 農林水産関係者の意見を踏まえ,生産者が将来にわたって意欲を持って経営を継続できるよう,農林水産関連施策の一層の充実及び強化を図ること。
2 米政策については,農業者が営農意欲を失うことなく持続的に農業経営に取り組めるよう米価下落等に対するセーフティーネットの整備をはじめ,需要に応じた生産を可能とする情報提供など万全の支援措置を講じること。
3 水田活用の直接支払交付金については,地域の特色ある魅力的な産地づくりが図られるよう産地交付金を拡充するなど,十分な予算措置を講じるとともに,飼料用米やその他の転作作物の生産が主食用米の生産と比べ経済的に不利とならないよう戦略作物助成による支援を現在と同じ水準で継続すること。
4 経営所得安定対策については,高齢化や農業就業者が減少している地域の実情を反映し,農業の大半を支えている中小規模農家も対象とするよう要件を拡充すること。
5 農地中間管理機構関連農地整備事業を含めた農業農村整備事業の更なる予算を確保すること。
6 生産の効率化や省力化,低コスト化を進めるため,自動操舵システムや農業用ドローン,自動給排水栓などICT化やAIを活用したスマート農業に対する予算や補助事業を拡充するとともに,公道での自動走行の移動や操縦オペレーターのみで農業用ドローンを使用できるようにする等の規制緩和を講じること。
7 各経済連携協定の進捗状況を踏まえ,主要な農産物の影響額と対応策を明示すること。
8 中山間地域の条件不利地域等については,一層の体質強化が図られるよう,品質向上や高付加価値化等による収益力向上のための支援など,必要な措置を講じること。
議案第23号
宮城県市長会提出
水産都市における諸課題への対応について
四方を海に囲まれた我が国において,水産物の安定供給を図ることは,健康で充実した国民生活を維持するとともに,食料自給率の向上を図る上からも極めて重要な課題であり,主要水産都市は,水産業の振興に積極的に取り組んできたところである。
このような中,全国の水産都市においては,少子高齢化,人口減少社会の進行により,生産年齢人口が減少し,慢性的な労働力不足となっている。水産加工業の分野においては,外国人技能実習生制度に加え,政府が働き方改革の中で検討中の外国人単純労働者の安定的な活用が期待されているとともに,
漁船漁業の分野においては,漁船乗組員の新規就業者の確保と離職率の抑制が課題となっている。
また,水産加工品の原材料についても,その多くを海外からの輸入に頼っているが,世界的な需要増により価格相場が高騰している。一方で,水産加工品の販路に目を向けると,国内においては,震災による販路喪失からの回復や風評被害の払拭など課題が多く,海外への販路拡大については,事業者のノウハウの不足や諸外国による輸入規制などで厳しい状況が続いている。特に,震災から7年余が経過し,この間,海外における日本産水産物の輸入規制措置は徐々に緩和されて来たものの,一部の国及び地域においては科学的根拠が乏しいまま,未だに日本産水産物の輸入規制措置が実施されている。
また,震災により災害から命を守るための多くの教訓を得たが,魚市場に上場,存置された魚介類への補償制度がないことから,津波による避難勧告・指示発令時において,魚市場関係者が迅速な避難行動をとる妨げになっている。
さらに,我が国における漁業生産が長期連続的に減少する中,産地魚市場の経営は厳しさを増している。加えて近年は食の安全・安心が求められ,産地魚市場においては,一層の高度衛生管理への対応が求められている。これらの条件が卸売機関の経営圧迫の要因となってきており,その経営安定のための支援が必要となっている。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 水産加工業の労働力不足を補うため,外国人技能実習制度のさらなる弾力化に加え,働き方改革の中で検討中の外国人単純労働者受入れなど雇用課題解決に向けた支援策を講じるとともに, 遠洋・沖合漁業に従事する漁船乗組員の福利厚生及び新規就業者の確保に資するよう,低廉な定額料金による海上高速通信サービスの更なる高度化・普及に努めること。
2 世界的な水産物需要の増大により,加工用原料の確保が困難になっていることから,原料価格の高騰等により利益率が低下する場合に融資を受けやすくなるよう認定条件を見直すなど融資制度の充実を図ること。
3 水産加工品の輸出拡大のため,商談会の開催やトライアル輸出などに引き続き取り組むとともに,ターゲットとすべき各国市場のニーズ調査や効果的なプロモーション方法の確立などにより,事業者がより効率的・効果的に海外販路を拡大できる支援策を講じること。
4 津波による避難勧告・指示発令時並びに津波襲来時において,関係者が安心して避難行動をとることができるよう,魚市場に上場,存置された魚介類の滅失,損傷,価値低下等に対する救済措置の創設を図ること。
5 産地魚市場が連続的な取扱数量・金額の減少の中で,マーケットが求める高度衛生管理を目指す卸売機関の経営安定のため,市場の維持管理を担う自治体に対して財政支援を行い使用料の削減を図るとともに,卸売機関に対しても新たな補助制度による支援を行うなど必要な措置を講じること。
6 日本産水産物の安全性にかかる信頼の回復と国内漁業者の復興を成し遂げるため,一部の国及び地域で行われている日本産水産物の輸入規制措置の早期解除に努めること。
議案第24号
秋田県市長会提出
治水事業の促進及び総合的な河川整備の推進について
近年,地球規模の気候変動によって,異常豪雨の発生が増加傾向にあり,水害や土砂災害の発生が,今後さらに多発することが懸念されている。
東北各地でも,これまで経験したことのない記録的な大雨による河川の溢水等により,度重なる洪水被害が発生している。
河川管理は,水害や地震等大規模な自然災害が頻発している中,住民生活の安全・安心を確保するため,ますます重要となっており,財政状況の如何にかかわらず,各河川の現場で着実に実施されなければならない根幹的な事項となっている。
また,河川が中心となって形成された歴史・文化や自然環境を保全するとともに,住民生活はもとより,多様な動植物の生息・生育・繁殖環境や水質を保全するため,良好な河川環境の整備が必要である。
よって,国は,治水事業の促進および総合的な河川整備の推進のため,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 住民の生命と財産を守り,地域社会の発展を支えるため,未だ整備水準の低い堤防やダムの整備等を促進するとともに,ハザードマップの整備や避難体制の構築等ソフト対策とハード対策が一体となった治水対策を推進するなど治水事業費の確保及び適切な河川の管理に努めること。
2 地球規模の気候変動が顕在化し,全国各地で局地的豪雨が相次いで発生しており,築堤事業等の外水氾濫対策に併せた内水氾濫対策が重要性を増していることから,両対策を一体的に推進すること。
3 環境問題に積極的に対応するため,治水対策を基本とし利水・環境に配慮した総合的な河川整備を推進すること。
4 河川激甚災害対策特別緊急事業を確実に実施すること。
議案第25号
青森県市長会提出
国土交通政策の充実強化について
地域公共交通は,人口減少やモータリゼーションの進行等により利用者が年々減少し,その維持確保が大変困難な状況になっている。
国は,交通政策基本法の理念に基づき交通政策基本計画を策定し,地域の公共交通ネットワークの再構築を推進するとともに,地域公共交通確保維持改善事業として,地域の特性に応じた生活交通の維持確保や快適で安全な公共交通の構築等に対する支援を行うこととしている。
しかしながら,当該予算の確保等が不十分なため,必要な支援が行き届いておらず,特に人口の集中する都市部と違って,急速な人口減少により運送収入等が伸びない地方部にあっては,地域公共交通の維持確保が危ぶまれている。
よって,国は,地域公共交通を維持確保するため,地域公共交通確保維持改善事業に係る必要予算額を確保し,都市部と地方部を取り巻く環境の違いを勘案して補助率や補助要件等を設定するよう要望する。
議案第26号
岩手県市長会提出
地域公共交通の充実について
地方都市の鉄道やバスなどの公共交通は,地域住民の生活維持や地域間交流の促進を図るため,維持・確保していくことが求められているが,人口減少,少子高齢化,マイカーの普及などにより利用者数が低迷を続け,路線の減便や廃止が相次いでいる。その中で高齢者や学生等のマイカーを持たない住民の足をいかに確保し,維持していくかが喫緊の課題となっている。
東北では,BRTをはじめ,路線バス,乗合タクシー及びデマンド交通の運行とともに,復旧・復興の状況や日々変化する市民ニーズに対応しながら,運行経路の見直しやバス停の新設等に取り組んでいる市,高齢者や学生等の移動手段確保のためのコミュニティバスやデマンド交通の運行等に取り組んでいる市などがあるが,いずれも財政負担の増加など,公共交通の維持確保が非常に厳しいのが現状である。
よって,国は,交通政策基本法の基本理念にのっとり,交通需要者のニーズに対応できる公共交通体制を確立するため,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 利用しやすい公共交通ネットワークの構築を図るための新たなサービスを導入するにあたり,全国の地方都市が抱えている課題を把握し,必要に応じた法律の改正や規制緩和等を早急に検討すること。
2 路線バスの利便性の向上,効率的な運行のためのバス路線再編など,持続可能な地域公共交通施策の推進のための必要な財源を確保するとともに,専門知識や人材が不足する自治体に対し,情報提供や技術的支援の強化・充実を図ること。
3 地域公共交通確保維持改善事業において,広域・幹線バス路線の補助金減額措置の緩和など制度の拡充を図るとともに,必要な財源を確保すること。
4 地方公共団体等が運行するコミュニティバス,デマンド交通等に対する財政支援措置の拡充を図ること。
議案第27号
岩手県市長会提出
道路・橋梁等の整備・維持管理に係る財政支援等の充実について
市民生活の安全・安心の確保には,社会的基本インフラである道路・橋梁等の整備及び適正な維持管理が重要であるが,これらの社会資本ストックは,高度経済成長期に集中的に整備されており,今後,急速に老朽化が進み,維持管理費・更新費が増大することが見込まれる。
また,高齢化が進展する中,子どもから高齢者までが安全で快適に暮らせるまちづくりを進めるためには,道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保や未整備区間の解消を図るなど,今後においても長期間にわたり,計画的に道路・橋梁等の社会基盤の整備に取り組む必要がある。
地方自治体においては,厳しい財政状況の中,社会資本整備総合交付金,防災・安全交付金等を活用し,計画的な施設更新や長寿命化対策等に取り組んでいるところであるが,近年,予算要望額に対する国費配分額が低い状況にあり,計画的な事業の推進に支障が生じている。
よって,国は,道路・橋梁等公共施設の社会基盤の整備・維持管理を長期的・安定的に行い,国土強靭化を推進するため,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 道路・橋梁等の老朽化に伴う維持修繕,更新等に係る調査及び修繕に対する国の補助制度及び地方債措置等の財政措置等を拡充すること。
2 地方自治体が真に必要な社会資本の整備・維持管理を計画的に推進するための財源を安定的かつ継続的に講じること。
3 国道4号金ケ崎区間の拡幅整備の促進とともに,花巻山の神・北上村崎野間の4車線拡幅整備の早期事業化を図ること。
4 平成30年度に全線開通予定の東北横断自動車道釜石秋田線の花巻~釜石間へのアクセス向上による利便性を高めるため,花巻パーキングエリアへのスマートインターチェンジ整備の早期事業化を図ること。
議案第28号
福島県市長会提出
国土交通政策の充実強化について
道路,港湾,河川,砂防,下水道,街路,鉄道,空港等の社会資本の整備及び維持管理は,安全・安心な社会生活を確保するために必要不可欠である。
特に,近年,頻発する集中豪雨や記録的な大雪等により多くの被害が発生していることなどにより,自治体への財政的な負担が増加することが危惧される中,安全で災害に強いまちづくりのため,インフラの整備はもとより,ソフト面の対策も重要となっている。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 社会資本総合整備計画に基づき,継続した事業の実施が確実にできるよう,社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金について,十分な予算を確保すること。
2 道路,橋梁等の老朽化に伴う維持修繕,更新等に係る調査及び修繕に対する補助制度を拡充すること。特に,橋梁長寿命化計画における橋梁の法定点検の結果必要となる更新等に係る費用について,財政支援を拡充すること。
また,「景観・観光」,「安全・快適」,「防災」の観点から推進されている無電柱化について,自治体における事業に対する十分な財政措置を講じること。
3 国際バルク戦略港湾政策の実現に向け,滞船の解消や沖防波堤等の早期整備を図るとともに,既存施設の再整備・再編による機能高度化を図ること。
4 自治体が実施する雨水幹線整備,河川整備や河川浚渫等の浸水被害対策及び局地的な豪雪に対する雪害対策に対し,十分な財政措置を講じること。
5 下水道の公共的役割に対する国の責務の観点から,下水道施設の改築に対する国費支援を確実に継続すること。
また,自治体が実施する下水道の基幹事業と一体となって行う末端管渠整備について,平成27年度から社会資本整備総合交付金の対象外となったが,汚水処理施設未普及地域の早期解消(10年概成)の実現に向け,社会資本整備総合交付金の効果促進事業の対象とすること。
6 大震災や頻発する豪雨災害等へ備えるとともに,山村部における土地の境界確認に必要な人証や物証等が失われつつあり,地籍調査を促進する必要があることから,調査体制を整える自治体において必要とする予算を満額措置すること。
また,地方財政が非常に厳しい状況であることから,地籍調査の促進を図るために,調査費の国庫負担率の引き上げと補助対象経費の拡充及び特別交付税措置を堅持すること。
7 新幹線鉄道の沿線地域における騒音・振動対策については,かねてより国土交通省の指導のもとJR東日本が対策を講じ,一定の改善効果が認められるものの,平成28年度以降対策が行われておらず,依然として環境基準値を超える地点が点在していることから,沿線住民の良好な生活環境の保全を図るため,新幹線鉄道の騒音・振動の低減について事業者に対し適切な指導を講じること。
8 福島空港を含めた周辺地域を,首都圏などの補完機能を備え東北圏域の防災施設の中核的施設となる基幹的広域防災拠点として新たに位置付けること。また,福島空港の防災拠点としての機能を,国の防災基本計画の中に新たに位置付けること。
9 災害時の避難所として利用される公民館などの社会教育施設の耐震化について,社会資本整備総合交付金,防災・安全交付金等を活用し,耐震診断,耐震改修等を進めているところであるが,交付率の嵩上げや補助対象限度額の引上げ,広く市民が集まる施設であるものの防災拠点に位置付けられていない施設も対象とするなど,更なる財政措置の拡充を行うこと。
10 被災地域における幹線路線バスの運行維持に対する支援について,地域公共交通確保維持改善事業(地域間幹線系統確保維持費国庫補助金)における補助要件緩和及び補助率の拡充を図ること。
また,バス路線の維持のほか,バス待合所整備など付帯的な部分も含め,公共交通の利便性を高める自治体,交通事業者及び地域の取組に対して財政支援を図ること。
議案第29号
宮城県市長会提出
交通体系の整備促進について
産業・経済・文化の活性化を図り,地域の発展と市民生活の向上を目指すため,高速交通体系の整備促進は重要な課題である。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
記
1 国道47号の道路改良を通常予算の別枠で実施すること。
2 国道108号の整備を推進すること。
3 地域高規格道路候補石巻新庄道路を早期に計画路線に指定すること。
4 国道284号の高規格化の早期実現を図ること。
5 みやぎ県北高速幹線道路の整備促進を図ること。
6 国道4号における4車線拡幅の未事業区間について,早期に事業化を図ること。
7 国道349号の道路改良及び自歩道の整備促進を図ること。
8 仙台空港と東北縦貫自動車道を結ぶ緊急輸送路の整備を直轄事業として取り組むこと。
9 三陸沿岸道路の早期全線供用に向け整備促進をすること。
10 仙台北部道路の4車線化及び富谷ジャンクションのフルジャンクション化の整備促進を図ること。
議案第30号
秋田県市長会提出
交通体系の整備促進について
産業・経済・文化の活性化を図り,地域の発展と市民生活の向上を目指すため,運輸・交通体系の整備促進は重要な課題である。
特に高速自動車道は,広域大規模災害に際して救援・援護活動の迅速な展開や支援物資の搬送等にその役割を遺憾なく発揮し,地域間や広域的な連携の重要な基盤として,ミッシングリンクを解消し,ネットワークの早期完成が強く求められているところである。
よって,国は,次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。