 |
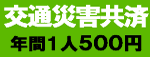 |
||
 |
|||
        �������s������� ��960-8043 �����������s����8-2 TEL024-522-6682 FAX024-524-0322 |
 �@���̓x�̓����{��k�Ђ��A�S���e�n��肨�������⌃��A�{�����e�B�A�x����~�������ȂǐS���܂鐔�X�̂��x��������A���ɂ��肪�����A���������e�s���\�������܂��āA��������\���グ�܂��B �@���̓x�̓����{��k�Ђ��A�S���e�n��肨�������⌃��A�{�����e�B�A�x����~�������ȂǐS���܂鐔�X�̂��x��������A���ɂ��肪�����A���������e�s���\�������܂��āA��������\���グ�܂��B�@�{����ۂƂȂ��Ă��̓�ǂ����z���ĎQ�肽���Ƒ����܂��̂ŁA����Ƃ��F�l�̉��������x��������܂��悤�A������낵�����肢�\���グ�܂��B �� �� �� �s �� ��@�@�@�@�@�@�@�@�@.
��@���@�ˁ@�F�@���i�����s���j |
|
|
  �{���͐��˕����s���A�����Îᏼ�s���A�n�ӂ��킫�s�����o�Ȃ��A��ɕ��������Đ���{���j�i�āj�ɂ��Ĉӌ��������Ȃ���A�e�s������́u�ӂ����Y�ƕ�����Ɨ��n�⏕���v�̘g�̊g��⏜���̒����ڕW�A���]��Q��A������t���̑Ώۊg��A�������҂̑Ή��Ȃǂɂ��Ĉӌ����o����܂����B |
|
|
|
| �����q�͑c��ɂ�錴�q�͑��Q�����̊��S���{�Ɋւ��铌���d�͂ւً̋}�v�����s���܂����B���c��̕���ł��鐣�ˉ���o�Ȃ��A�����d�͍L���햱�ɑ��A������ɑ��鍡�N1���ȍ~�̔�����⎩���̂ɑ��锅���Ȃǂɂ��ėv�����܂����B | |
  |
|
|
|
| �������o�ς̕����Đ���}�邽�߂ɐ݂���ꂽ�u�ӂ����Y�ƕ�����Ɨ��n�⏕���v�̗\�Z�g�[��}�邽�߁A���A������A���H��c���A����A���H��A����A������ƒc�̒�����Ƃ̍����ɂ��A���ɑ��v�]�����o�������܂����B | |
  |
|
�ӂ����Y�ƕ�����Ɨ��n�⏕���Ɋւ���ً}�v�] |
|
| �@�{�⏕���́A�����d�͕�����ꌴ�q�͔��d���̎��̂ɂ��A�������S�y���r��Ȕ�Q���������ƂɊӂݑn�݂��ꂽ���̂ŁA�{���Y�ƕ����{��̑傫�Ȓ��Ƃ��Ċ�Ƃ���������]�������������Ă���Ƃ���ł���܂��B. �@��ʁA����ڂ̕�W���s�����Ƃ���A�������t���ꂽ�\�Z�z��啝�ɏ���\�������������A�{���Y�ƕ����Ɍ�������Ƃ̔M�ӂ̍��܂肪���ꂽ���̂ƐS���������Ă���Ƃ���ł���A���̔M�ӂɉ����Ă������Ƃ��{���Y�Ƃ̈�������������Ɍq������̂Ɗm�M���Ă���Ƃ���ł���܂��B �@����ɁA���݂��{���Y�ƕ����̋N���܂ƂȂ鑽���̊�Ƃ��\����\�肵�Ă��邱�Ƃɉ����A�������̂ɂ��x����擙�ɂ����ẮA���ꂩ��Z���̕��X�̋A�҂Ɍ�������g���n�߂��悤�Ƃ��Ă���i�K�ŁA�����̎�g��i�߂Ă������߂ɂ͉���������ꂽ�ٗp�������邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���A�{�⏕���͓��Y�n�敜���Ɍ����������͂ƂȂ���̂ł���܂��B �@���ẮA�����ЊQ����̖{���Y�Ƃ̕�����}�邽�߂ɂ́A�����O����̊�Ɨ��n�̈�w�̑��i��}��{�⏕���x�̌p�����K�{�ł��邱�Ƃ���A�ȉ��̎����ɂ��ċ����v�]�������܂��B �E�ӂ����Y�ƕ�����Ɨ��n�⏕���̗\�Z�g�[�ɂ��� �����ЊQ����̖{���̈���������Y�ƕ�����}�邽�߁A�{�⏕���̗\�Z��啝�Ɋg�[���邱�ƁB �@����24�N5��31�� �@�@�@�o�ώY�ƕ���b�@���V���� �l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������m���@�����Y�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@���ˍF�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������������@�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������H��c���A����@���J�r�Y �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������H��A����@�D�c�q�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������ƒc�̒�����@�V�V���p |
|
|
|
| �������Y�Ă̐M�������邽�߁A�����Ɍ����Ԑ����\�z����K�v�����邱�Ƃ���A������Ƃ̍����ɂ��A���y�ь��ɑ��v�]�����o�������܂����B | |
  |
|
24�N�Y�Ă̑S�܌����Ɋւ���ً}�v�� |
|
| �@�����d�͕�����ꌴ�q�͔��d�����̂��A24�N�Y�Ă̑S�܂�ΏۂƂ��������̐������邱�Ƃ����\����A��ʁA�ߋ��̐��Y�ʂɊ�Â����s�������Ƃ̌����@��̔z���䐔�����蓖�Ă�ꂽ�Ƃ���ł���܂��B �@�������Ȃ���A�s�������ł́A�@��s�����w�E���鐺��o�������x��邱�Ƃ����O���鐺�Ȃǂ��オ���Ă���Ƃ���ł���܂��B �@���ẮA�{���Y�Ă̐M�������邽�߂ɂ��A���ǂ������̐����\�z���邱�Ƃ��K�v�ł���܂��̂ŁA���L�����ɂ��āA�����v���������܂��B �P�D��ʎ����ꂽ�����@��̑䐔�ł́A�V�Ă̏o�����܂łɌ������I�����邱�Ƃ�����Ȓn�悪���邱�Ƃ���A���₩�Ɍ����ł���悤�A�\���ȑ䐔���m�ۂ��邱�ƁB �@�Ȃ��A�lj��w���ɔ����o��ɂ��āA�s������Y�ғ��ɕ��S�]�ł���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB �Q�D�Ă̑S�܌����́A�{���A�����s���ׂ����̂ł��邱�Ƃ�����A�����ɕK�v�s���ȏ��o��ɂ��āA�s������Y�ғ��ɕ��S�]�ł���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB �@����24�N5��31�� �@�@�@�������m���@�����Y�� �l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�� �� �F �� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������������@�� �� �� �� |
|
|
|
|
| 24�N�Y�Ă̑S�܌����Ɋւ���ً}�v�� |
|
| �@�����d�͕�����ꌴ�q�͔��d�����̂��A24�N�Y�Ă̑S�܂�ΏۂƂ��������̐������邱�Ƃ����\����A��ʁA�ߋ��̐��Y�ʂɊ�Â����s�������Ƃ̌����@��̔z���䐔������芄�蓖�Ă�ꂽ�Ƃ���ł���܂��B �@�������Ȃ���A�s�������ł́A�@��s�����w�E���鐺��o�������x��邱�Ƃ����O���鐺�Ȃǂ��オ���Ă���܂��B �@���ẮA�������̂��Ȃ���ΕK�v�̂Ȃ������ł��邱�Ƃ����͏\���F������A�{���Y�Ă̐M���Ɍ����A���ǂ������̐����\�z�ł���悤�A���L�����ɂ��ċ����v���������܂��B �P�D��ʁA����莦���ꂽ�����@��̑䐔�ł́A�V�Ă̏o�����܂łɌ������I�����邱�Ƃ�����Ȓn�悪���邱�Ƃ���A���₩�Ɍ����ł���悤�A�\���ȑ䐔���m�ۂ��邽�߂̍����[�u���s�����ƁB �Q�D�Ă̑S�܌����́A�{���A�����s���ׂ����̂ł��邱�Ƃ�����A�����ɕK�v�s���ȏ��o��S�z�ɑ�������[�u���s�����ƁB �@����24�N5��31�� �@�@�@������b�������@�g�c�� �l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�� �� �F �� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������������@�� �� �� �� |
|
|
|
| ���q�͑��Q�c��ɂ�錴�q�͑��Q�����̊��S���{�����߂�ً}�v�]���s���{���͕y�˕�����Q�����A�����Ȋw�ȁA�o�ώY�ƏȁA�����d�͋y�і���}�ɑ��v�]�����o�������܂����B | |
  |
|
���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɋւ���ً}�v�] |
|
| �@���q�͍ЊQ�͕��������S�楑S�����ɋy��ł��邱�Ƃ���A����܂ŁA�u���������q�͑��Q�c��v�́A���y�ѓ����d�͂ɑ�����x�ɂ��킽��v�]��v����������ʂ��A���Q�͈̔͂L�������A��Q�̎��ԂɌ��������\���Ȕ������Ō�܂Ŋm�����v���ɂȂ����悤�������߂Ă����Ƃ���ł���B �@�����������A�{�N�R���P�U���A���q�͑��Q���������R����u���Ԏw�j��Ǖ�v�����܂Ƃ߁A����擙�̌������ɔ������_�I���Q������̔����Ɋւ���l�������������ꂽ���A�W�c�̂�s��������́A�u�����̑Ώ۔͈͂�Z�����s���m�v�A�u�����d�͂̑Ή��ɑ������ςːӔC�����v�ȂNj����s���̐����������Ă���B �@���q�͔��d�����̂���P�N�ȏオ�o�߂��������P�U���l���镟�������������O�ɔ��A�����ɂ킽��Z�݊��ꂽ�̋��ɖ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃɂ�閳�튴��ő����ȂǗl�X�Ȋ���Ɠ����Ȃ���A�����ւ̑傫�ȕs��������A���X�������������������Ă���ɂ����āA����擙�̌������ɔ������Q�����́u�w�j�v�́A�Z���ɂƂ��āA���ꂩ��̐����v�ɂ����ċɂ߂ďd�v�ł���B �@���́A�n��̏Z����s�����̐����\���ɓ��܂��A��Q�҂̂��ꂼ�ꂪ�����⎖�Ƃ̍Č����ʂ������Ƃ��ł��锅�����v�����~���ɂȂ����悤�A���m�A��̓I�ȁu�w�j�v�̍쐬�A�����d�͂ւ̎w�������s���A���Ƃ��Ă̐ӔC���Ō�܂Ŋm���ɉʂ����ׂ��ł���B �@����āA�Q�O�O���l���������̑��ӂƂ��āA���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɖ��L�ɂ��Ă̑��}�ȑΉ��������v�]����B �P �S�Ă̑��Q�́u�w�j�v�ւ̔��f�� (1) ���q�͔��d�����̂��Ȃ���ΐ����邱�Ƃ̂Ȃ������S�Ă̑��Q�ɂ��āA���Q�͈̔͂L�������A���������S�楑S������S���Ə���Ώۂɔ�Q�̎��ԂɌ��������\���Ȕ������Ō�܂Ŋm����v���ɂȂ����悤�A��O���A��l���́u�w�j�v�̍���ɂ��A�X�ɋ�̓I�����m�Ɏ������ƁB (2) ���́A�����I�Ȏ��_�ɗ����A����e�s�����A���Ǝғ��̔�Q�̎��Ԃ╜���Đ��Ɋւ���l�������܂��A�S�Ă̑��Q�ɂ��ď\���Ȕ������Ԃ��m�ۂ���ƂƂ��ɁA���̑S�ӔC�̉��ŁA�����O�ʂɗ����āA��屢A�ҥ�ڏZ�ɂ����鐶���⎖�Ƃ̍Č��Ɍ�������ڂ̂Ȃ�����u���邱�ƁB (3) ���q�͑��Q�̔����Ɋւ���@���Ɋ�Â��a���̒�����s���u���q�͑��Q�������������Z���^�[�v�ɂ��ẮA�����̐\�����Ȃ���钆�A�a�𐬗����x�����Ă�����ԓ��܂��A��Q�҂̐v�����~���ȋ~�ς̊ϓ_����A�\�������̌��������ӏ��ւ̐ݒu�A����ψ����̑�����}��A�g�D�̑̐����������邱�ƁB �Q �����d�͂ɑ���w���� (1) ���̐ӔC�̉��ŁA�u�w�j�v�͔����͈͂̍ŏ����̊�ł��邱�Ƃ𓌋��d�͂ɉ��߂Đ[���F��������ƂƂ��ɁA���ӂ������đS�Ă̔����������t���A���₩�Ɏx�������s���A��Q�̎��ԂɌ��������\���Ȕ������m���ɍs�킹�邱�ƁB (2) ��Q�҂̉~���ȋ~�ςɌ����A��Q�҂̎��_�ɗ������u�w�j�v�̏_��ȉ��߂̉��ŁA�ʋ�̓I�Ȏ�����\���ɓ��܂������ߍׂ��ȑ��Q�̗ތ^�����s���A���̔�������𑁋}�����m�ɒ����邱�ƁB (3) �u���q�͑��Q�������������Z���^�[�v������u������v��u�a�𒇉�āv�ɂ��ẮA��Q�҂̍��ӂ�O��ɁA�����d�͂Ɏ����`���킹��ƂƂ��ɁA��Q�҂��瓌���d�͂ւ̒��ڐ����ɂ����Ă��A�����܂��đΉ������A�v�����~���ɔ������s���悤�������߂邱�ƁB �R ���{�ɂ����w�����ɌW�鑹�Q (1) ����擙�̌��������ɌW�鑹�Q�i�S�́j �A���{�ɂ�����擙�̌��������ɌW�鑹�Q�ɂ��ẮA���ꂼ��̋��A�s�����A�Z���̒u����Ă����ӌ����\���ɍl�����A�Z���ɑ傫�ȍ�����s�����������Ȃ��悤�z�����Ȃ���A�_��ɑΉ����邱�ƁB �C�A�҂����Z���A�V���ȓy�n�ł̐�������]����Z���̂��ꂼ�ꂪ�����̍Č��⎖�Ƃ̍ĊJ�������S�ɉʂ������Ƃ��ł���܂ŁA�����I�������Ȏ��_�ɗ����āA�\���Ȕ������Ԃ��m�ۂ��邱�ƁB �E�����_�őz�肳��鑹�Q�Ɍ��肷�邱�ƂȂ��A����V���ɐ����邱�ƂƂȂ������Q�ɂ��Ă��m���ɔ����̑Ώۂɂ��邱�ƁB �G��Q�҂̑����̐����Č���ړ]�擙�ɂ�����R�~���j�e�B�̈ێ����܂ސ�����ՑS�ʂ̍Č���}��ɂ́A�Z���⎖�Ǝ҂̈ӌ��ɉ����������d�͂ɂ�鑬�₩�Ȕ����͂��Ƃ��A�����O�ʂɏo���ӔC�̂���Ή����K�v�ł��邱�Ƃ���A�V���ȗ��@�[�u������ɓ���Ȃ���A�����I���n���瓌���d�͂ƍ��ɂ�����~�ς̖������S�i�����ƕ⏞�j�m�Ɏ������ƁB �I���������ɑ��Ďx�����锅�������̐Ő���̎戵���ɂ��ẮA��Вn��S�̂ɂ�����Ő��݂̍���܂��Ȃ���A��Q�ҋ~�ς̎��_���\���ɔ��f�������̂Ƃ��邱�ƁB (2) ���_�I���Q �A�����ɂ킽��A�҂�����ȏZ���ɑ��ẮA�ڏZ��]�������������邱�Ƃ܂��A���Ԃf�����Ԏӗ��I�����̐��_�I���Q�̏\���Ȕ�����⏞���s���A�m���ɋ~�ς��Ȃ����悤�ɂ��邱�ƁB �C���w�������܂ł̊��Ԃ������������ꍇ�ɂ́A�����܂ł̊��Ԃɉ������lj��I�������m���ɍs����悤�ɂ��邱�ƁB (3) �������l�̑r�����͌����� �A�y�n�⌚���̔����́A�ƌv�⎖�ƌo�c�ɋy�ڂ��e�����傫���A��Q�҂̏����v�ɕs���ł��邱�Ƃ���A�������̑S�̂ɌW�郍�[�h�}�b�v�������ƂƂ��ɁA���w�������O�̍������܂ޑ��Q�̋�̓I�ȗތ^����i�߁A���Q�̎Z����@���ɂ��āA���}����̓I�Ɏ������ƁB �C������̔��w�����ɂ����Ă��A���ꂼ��̏Z���ɕs�����������Ȃ��悤�ɂ���ƂƂ��ɁA��Q�҂̈�l��l���[������\���Ȕ������Ȃ����悤�ɂ��邱�ƁB �E���Z�������y�є��w�������������ɂ�����s���Y�ɂ��ẮA���{�w���ɂ�蒷���̔����������Ǘ��s�\�ȏ�ԂɂȂ������Ɠ��ɂ�肻�̉��l������ꂽ���Ƃ���A�A�ҍ�����ɏ����������ƂȂ�悤�ɂ��邱�ƁB �G�Â��Ɖ��╶�������̎w��������������̈�ʓI�Ɏs�ꐫ��L���Ȃ��s���Y�ɌW������̎��̔������O�̉��l�ɂ��ẮA���Z�̎��Ԃ╶���I���l���܂��A���Y�����̋q�ϓI���l�����\���ȕ]���z�ƂȂ�悤�ɂ��邱�� �I���Y�̔����ɂ��ẮA���ː������̕t�����̌�����ʂɔc�����邱�Ƃ͒���������ł��邱�Ƃɉ����A�����̊Ǘ��s�\�ɂ��A�]���Ɠ��l�̎g�p�͍���ł��邱�Ƃ���A���z�Ȃ��̂����̂Ȃ����̂������A�ꊇ����̔����z�Ƃ���ȂǁA�v�����~���Ȕ�Q�ҋ~�ς̊ϓ_�ɗ������Z���𑁋}�Ɏ������ƁB �J�_�n�A�X�ѓ��ɂ��ẮA�c�_���ɂƂ��ĕs������֕s�\�Ȑ��Y�v�f�ł��邱�Ƃɉ����A�����ɂ����ː��ʂ̒ጸ�ɂ͒����Ԃ�v����ƂƂ��ɁA�����̕s�k�쓙�ɂ��L�͈͂ɍr�p���i�ނ��Ƃ���A�����I�ɐ��ݏo�����t�����l��c�Ƒ��Q�A�Ǘ���p�����܂ޔ�����⏞���̍l�����m�Ɏ������ƁB �L�����̓����Q��ƒ{���ɍr�炳�ꂽ��Q�A�n�k���ɂ��Ɖ���Q�������̕��u�ɂ��g�債����Q�ȂǕ����I�ȗv�������鑹�Q�ɂ��Ă��A�����̔��w�����ɔ����Ǘ��s�\�ɂȂ������Ƃɂ������̉��l���r��������������̂Ƃ��đ����A�m���ɔ����̑Ώۂɂ��邱�ƁB (4) �c�Ƒ��Q �A�I���ɂ��ẮA���̑O�̌o�c��ԂɊ��S�ɉ���܂ŁA�\���Ȋ��Ԃ��m�ۂ��邱�ƁB �C�V���Ȓn��ɂ����Ď��Ƃ��ĊJ��]�Ƃ���ꍇ�ɂ��ẮA���Ƃ̍ĊJ��]�Ƃ̂��߂ɕK�v�Ȑݔ���p�����m���ɔ����̑Ώۂɂ��邱�ƁB �E�]�ƥ�]�E��Վ��̉c�Ɠ��ŐV���ɓ������v���̑��Q�z����̍T���ɂ��ẮA���̓w�͂��\���ɓ��܂������̂Ƃ��邱�ƁB �G������u�̂���v��u�����h���̑r���ɔ������Q�ɂ��Ă��m���ɔ����̑Ώۂɂ��邱�ƁB (5) �A�J�s�\���ɔ������Q �A�I���ɂ��ẮA���̑O�Ɠ����A�܂��͓����̏A�J���c�ނ��Ƃ��\�ɂȂ�܂ŁA�\���Ȋ��Ԃ��m�ۂ��邱�ƁB �C�]�E��Վ��̏A�J���ɔ��������鎑�i�̎擾��p�ȂǐV���Ȍo�ϓI���S�ɂ��Ă��A�m���ɔ����̑Ώۂɂ��邱�� �E�]�E��Վ��̏A�J���ŐV���ɓ������^���̑��Q�z����̍T���ɂ��ẮA���̓w�͂��\���ɓ��܂������̂Ƃ��邱�ƁB �S ���ً}���������̑��Q (1) ���ً}�����������̑؍ݎ҂⑁���i��P�����͑�Q���j�ɋA�҂����Z���ɂ��Ă��A���҂Ɠ����̐��_�I���Q�̔������m���ɍs����悤�A�u���q�͑��Q�������������Z���^�[�v�ɂ����āu������v�����肷�邱�ƁB (2) ����p�y�ѐ��_�I���Q�̏I���ɂ��ẮA�����Q�S�N�W�����܂ł�ڈ��Ƃ���Ƃ���Ă��邪�A�㉺�������܂ރC���t���̖{�i�������å��������Ǝ{�ݓ��̑��ƍĊJ���̐������S�ʂɂ����镜����K�ɔc�����A�K�����������s���Ă������ƁB (3) ���ً}���������ɂ���������ɂ��ẮA�����ɂ킽�����]�V�Ȃ�����Ă�����ԓ����l�����A���Y���̏Z���������ɋA�҂��A�����Č����ʂ������Ƃ��ł���悤�ɂ���ϓ_������A��Q�̎��ԂɌ��������������s����悤�A��̓I�Ȕ�����m�Ɏ������ƁB �T ����I���ɌW�鑹�Q (1) �����S��ɂ������Q�̎��ԂɌ��������������v�����~���ɂȂ����悤�A��薾�m�Ɂu�w�j�v�ɔ��f�����邱�ƁB (2) �����������ꂼ��̔�Q�̎��Ԃ܂��A�u���q�͑��Q�������������Z���^�[�v�ɂ����āA��̓I�Ȍʎ����ތ^��������u������v�Ƃ��Č��\����ȂǁA�v�����~���ɔ�Q�ҋ~�ς��s�����ƁB �U �������ɌW�鑹�Q (1) �����S��ɂ���������̏���������̎��{�A����ɔ����@��̍w�����ɗv�����p��S�Ĕ����̑ΏۂƂ��A�v���ɔ������Ȃ����悤���m�Ȋ�𑁋}�Ɏ������ƁB |
|
| �����Ȋw��b�@����@�����@�l �o�ώY�Ƒ�b�@�}��@�K�j�@�l ����24�N4��27�� ���������q�͑��Q�c���@�������m���@�����Y�� ����i�`�O���[�v�����d�͌������̔_�{�Y�����Q���������������c���@�������� ������������H��A�����@�c�q�����Y ����������s�����@�����s���@���ˍF�� ����������������@���������@�������� |
|
|
|
|
���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɋւ���v���� |
|
| �@���q�͍ЊQ�͕��������S��ɂ��܂˂��y��ł��邱�Ƃ���A����܂ŁA�u���������q�͑��Q�c��v�́A���x�ɂ��킽��v����������ʂ��A�����S�楑S������ΏۂɁA���Q�͈̔͂L�������A��Q�̎��ԂɌ��������\���Ȕ������Ō�܂Ŋm�����v���ɍs���� ���������߂Ă����Ƃ���ł���B �@�����������A�{�N�R���P�U���A���q�͑��Q���������R����ɂ����āu���Ԏw�j��Ǖ�v�����܂Ƃ߂��A����擙�̌������ɔ������_�I���Q������̔����Ɋւ���l�������������ꂽ���A�����d�͂ɂ�锅���̍l��������̕��@�������m�ɂ���Ă��炸�A�����̏Z���͍���̐����v�𗧂Ă邱�Ƃ��ł����ɂ���B �@���q�͔��d�����̂���P�N�ȏオ�o�߂��������P�U���l���镟�������������O�ɔ��A�����ɂ킽��Z�݊��ꂽ�̋��ɖ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃɂ�閳�튴��ő����ȂǗl�X�Ȋ���Ɠ����Ȃ���A�����ւ̑傫�ȕs��������A���X�������������������Ă��錻�����������Ǝ~�߁A���q�͍ЊQ�̌����҂Ƃ��Đ��ӂ������Ĕ�Q�҂Ɛ^���Ɍ��������A����������l��l�������⎖�Ƃ̍Č������S�ɉʂ������Ƃ��ł���\���Ȕ������m�����v���ɍs���ׂ��ł���B �@����āA�Q�O�O���l���������̑��ӂƂ��āA���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɖ��L�ɂ��Ă̑��}�ȑΉ��������v������B �@�Ȃ��A���v���ɑ���́A�����Q�S�N�T���P�W���i���j�܂łɎ������ƁB �P �S�Ă̑��Q�̊m�����v���Ȕ����� (1) �u�w�j�v�͔����͈͂̍ŏ����̊�ł���Ƃ̔F���̉��ŁA�u�w�j�v�ɖ��L����Ă��Ȃ����Q���܂߁A���Q�͈̔͂L�������A���������S�楑S������S���Ə���ΏۂɁA���ӂ������đS�Ă̔����������t���A�_����₩�Ȏx�������s���A��Q�̎��ԂɌ��������\���Ȕ������m���ɍs�����ƁB (2) ��Q�҂̉~���ȋ~�ςɌ����A��Q�҂̎��_�ɗ������u�w�j�v�̏_��ȉ��߂Ɖ^�p�̉��ŁA�ʋ�̓I�Ȏ�����\���ɓ��܂������ߍׂ��ȑ��Q�̗ތ^�����s���A���̔����������@���𑁋}�����m�Ɏ������ƁB (3) �u���q�͑��Q�������������Z���^�[�v������u������v��u�a�𒇉�āv�ɂ��ẮA��Q�҂̍��ӂ�O��Ɏ����ƂƂ��ɁA��Q�҂̒��ڐ����ɂ����Ă��A�����܂��đΉ����A�v�����~���Ȕ������s�����ƁB (4) �����݂̂Ȃ炸�S���e�n�ɔ��Ă����Q�҂̂ق�����҂�Ⴊ���ғ��̔�Q�҂ɑ��鐿�����@���̎��m�̐��𑁋}�ɋ������A�S�Ă̔�Q�҂��~���ɔ����������s�����Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�ƁB �Q ���{�ɂ����w�����ɌW�鑹�Q (1) ����擙�̌��������ɌW�鑹�Q�i�S�́j �A���{�ɂ�����擙�̌��������ɌW�鑹�Q�ɂ��ẮA���ꂼ��̋��A�s�����A�Z���̒u����Ă����ӌ����\���ɍl�����A�Z���ɑ傫�ȍ�����s�����������Ȃ��悤�z�����Ȃ���A�_��ɑΉ����邱�ƁB �C�����_�őz�肳��鑹�Q�Ɍ��肷�邱�ƂȂ��A����V���ɐ����邱�ƂƂȂ������Q�ɂ��Ă��m���ɔ������邱�ƁB (2) ���_�I���Q �A�����ɂ킽��A�҂�����ȏZ���ɑ��ẮA�ڏZ��]�������������邱�Ƃ܂��A���Ԃf�����Ԏӗ��I�����̐��_�I���Q�̏\���Ȕ������s�����ƁB �C���w�������܂ł̊��Ԃ������������ꍇ�ɂ́A���Ԃɉ������lj��I�������m���ɍs���悤�ɂ��邱�ƁB �E���w�������������y�ы��Z�������ɂ����鐿�����@�ɂ��ẮA���P�ʂ������ԕ��̈ꊇ�x��������I���\�Ƃ���ȂǁA��Q�҂��ꂼ��̏ɉ������_��ȑΉ����s�����ƁB (3) �������l�̑r�����͌����� �A�y�n�⌚���̔����́A�ƌv�⎖�ƌo�c�ɋy�ڂ��e�����傫���A��Q�҂̏����v�ɕs���ł��邱�Ƃ���A������x�������̔����S�̂ɌW�郍�[�h�}�b�v�������ƂƂ��ɁA���w�������O�̍������܂ދ�̓I�ȑ��Q�̎Z����@������@���𑁋}�Ɏ������ƁB �C������̔��w�����ɂ����Ă��A���ꂼ��̏Z���ɕs�����������Ȃ��悤�ɂ���ƂƂ��ɁA��Q�҂̈�l��l���[������\���Ȕ������s�����ƁB �E���Z�������y�є��w�������������ɂ�����s���Y�ɂ��ẮA���{�w���ɂ�蒷���̔����������Ǘ��s�\�ȏ�ԂɂȂ������Ɠ��ɂ�肻�̉��l������ꂽ���Ƃ���A�A�ҍ�����ɏ������������s�����ƁB �G�Â��Ɖ��╶�������̎w��������������̈�ʓI�Ɏs�ꐫ��L���Ȃ��s���Y�ɌW������ɂ��ẮA���Z�̎��Ԃ╶���I���l���܂��A���Y�����̋q�ϓI���l�����\���Ȕ������s�����ƁB �I���Y�̔����ɂ��ẮA���ː������̕t�����̌�����ʂɔc�����邱�Ƃ͒���������ł��邱�Ƃɉ����A�����̊Ǘ��s�\�ɂ��A�]���Ɠ��l�̎g�p�͍���ł��邱�Ƃ���A���z�Ȃ��̂����̂Ȃ����̂������A�ꊇ����̔����z�Ƃ���Ȃǂ̎Z���𑁋}�Ɏ������ƁB �J�_�n�A�X�ѓ��ɂ��ẮA�c�_���ɂƂ��ĕs������֕s�\�Ȑ��Y�v�f�ł��邱�Ƃɉ����A�����ɂ����ː��ʂ̒ጸ�ɂ͒����Ԃ�v����ƂƂ��ɁA�����̕s�k�쓙�ɂ��L�͈͂ɍr�p���i�ނ��Ƃ���A�����I�ɐ��ݏo�����t�����l��Ǘ���p�����܂ޔ�������m�Ɏ������ƁB �L�����̓����Q��ƒ{���ɍr�炳�ꂽ��Q�A�n�k���ɂ��Ɖ���Q�������̕��u�ɂ��g�債����Q�ȂǕ����I�ȗv�������鑹�Q�ɂ��Ă��A�����̔��w�����ɔ����Ǘ��s�\�ɂȂ������Ƃɂ������̉��l���r��������������Ƃ͖��炩�ł��邱�Ƃ���A���q�͔��d�����̂Ƒ������ʊW�����鑹�Q�Ƃ��Ċm���ɔ������s�����ƁB (4) �c�Ƒ��Q �A�V���Ȓn��ɂ����Ď��Ƃ��ĊJ��]�Ƃ���ꍇ�ɂ��ẮA���Ƃ̍ĊJ��]�Ƃ̂��߂ɕK�v�Ȑݔ���p�����m���ɔ������邱�ƁB �C�]�ƥ�]�E��Վ��̉c�Ɠ��ɂ���ē������v���ɂ��ẮA�m���ɔ����z����T�����Ȃ��悤�ɂ���ƂƂ��ɁA���ɔ������s�������Ə����ɑ��Ă��k���đΉ����邱�ƁB �E������u�̂���v��u�����h���̑r���ɔ������Q�ɂ��Ă��m���ɔ������邱�ƁB (5) �A�J�s�\���ɔ������Q �A�]�E��Վ��̏A�J���ɂ���ē������^���ɂ��ẮA�m���ɔ����z����T�����Ȃ��悤�ɂ���ƂƂ��ɁA���ɔ������s�����ΘJ�҂ɑ��Ă��k���đΉ����邱�ƁB �C�]�E��Վ��̏A�J���ɔ��������鎑�i�̎擾��p�ȂǐV���Ȍo�ϓI���S�ɂ��Ă��A�m���ɔ������邱�ƁB �R ���ً}���������̑��Q (1) ���ً}�����������̑؍ݎ҂⑁���i��P�����͑�Q���j�ɋA�҂����Z���ɂ��Ă��A���҂Ɠ����̐��_�I���Q�̔������m���ɍs�����ƁB (2) ���ً}���������ɂ���������ɂ��ẮA�����ɂ킽�����]�V�Ȃ�����Ă�����ԓ����l�����A���Y���̏Z���������ɋA�҂������Č����ʂ������Ƃ��ł���悤�ɂ���ϓ_������A��Q�̎��ԂɌ��������������s�����ƁB �S ����I���ɌW�鑹�Q (1) �����������ꂼ��̔�Q�̎��Ԃ܂��A�u���Ԏw�j��Ǖ�v���̏_��ȉ��߂Ɖ^�p�ɂ��A�\���Ȕ������s�����ƁB (2) �����Q�S�N�P���ȍ~�̑��Q�ɂ��Ă��A��Q�̎��ԂɌ��������v�����m���Ȕ������s�����ƁB �T �������ɌW�鑹�Q (1) �����S��ɂ���������̏���������̎��{�A����ɔ����@��̍w�����ɗv�����p��S�Ĕ����̑ΏۂƂ��A�v���ɔ������s�����ƁB |
|
| �����d�͊������ �@�@������В��@���V�@�r�v�@�l ����24�N4��27�� ���������q�͑��Q�c���@�������m���@�����Y�� ����i�`�O���[�v�����d�͌������̔_�{�Y�����Q���������������c���@�������� ������������H��A�����@�c�q�����Y ����������s�����@�����s���@���ˍF�� ����������������@���������@�������� |
|
|
|
  �@���1��ڂƂȂ镜���Đ����c��́A����V���Ɏ����Îᏼ�s���A�n�ӂ��킫�s���A������͎}��o�ώY�Ƒ�b�������o�[�ɉ����܂����B �@���1��ڂƂȂ镜���Đ����c��́A����V���Ɏ����Îᏼ�s���A�n�ӂ��킫�s���A������͎}��o�ώY�Ƒ�b�������o�[�ɉ����܂����B��c�ł͕��앜����b�A�ז���E�������̂̎����y�эĔ��h�~�S����b�A�}��o�ώY�Ƒ�b����Đ��Ɍ���������̉ۑ�A�����J���E�Y�Ƒn�����_�\�z�A�����̏A�����Đ���{���j���q�i�f�āj���ɂ��Đ���������A�{������o�Ȃ̍����m�����͂��߁A���˕����s���A�����Îᏼ�s���A�n�ӂ��킫�s���Ȃǂ��炻�ꂼ������ۑ蓙�ɂ��Ĕ������Ȃ���܂����B |
|
|
|
| �����{��k�Ђ���1�N���}���A�]���ɂȂ�ꂽ���X�ւ̈����̐��������ƂƂ��ɁA�u�V���ӂ����܁v�̑n���Ɍ����Č�������ۂƂȂ��Ď��g�ނ��Ƃ𐾂����߁A�Ǔ����y�ѕ����Ɍ������V���|�W�E�����J�Â���A���ˉ���J���̎����q�ׂ܂����B�V���|�W�E���ł́A�w�ӂ����ܐ錾�x�����\����A�����Ɍ����Ă̌��ӂ������O�֔��M�������܂����B �w�������͕K���A�������ӂ邳�Ƃӂ����܂����߂��܂��B�������͕K���A���͂ƏΊ炠�ӂ��ӂ����܂�z���Ă����܂��B�����Ď������́A���̂ӂ����ܕ����̎p�𐢊E�ցA�����ւƓ`���܂��B�x �i�ӂ����ܐ錾��蔲���j |
|
  |
|
|
|
| �n�������Njy�ђn���o�ώY�Ƌǂɂ��Č��s����Ƃ��ĉ��L�̂Ƃ���ً}���c���s���A�����ȁA���y��ʏȁA�o�ώY�Əȋy�і{���I�o����c���ɋً}�v�]�������܂����B |
|
| �n�������Njy�ђn���o�ώY�ƋǑ����Ɋւ��錈�c |
|
| �@�����{��k�Ђ́A���k�n�����͂��߂Ƃ���L�͂Ȓn��ɐr��Ȕ�Q���y�ڂ��A���݁A���������ĕ����E�����Ɍ����������Ȏ��g�݂��s���Ă���B �@����̑�k�Ђł́A���В��ォ��n�������ǂ�n���o�ώY�ƋǂƎs��������̂ƂȂ��āA�v���������ȋ~��������C���t���E�Y�Ƃ̕������s����ȂǁC�n��ɂ����鍑�̏o��̖��������߂ĔF�����ꂽ�B �@������ɁA���ݍs���Ă��鍑�̏o��@�֔p�~�������͒n���ڊǂ̋c�_�́A�������������{��k�Ђ̋��P��S���ӂ݂邱�ƂȂ��A���k�̃C���t���E�Y�Ƃ̕�����x�点��݂̂Ȃ炸�A�n�k�A�Ôg�A�����Q���̑�K�͂Ȏ��R�ЊQ�̊댯���ɏ�ɂ��炳��Ă���䂪���ɂ����āA�����̈��S���S����鍑�̑̐�����̉������邱�ƂɂȂ�A�傫�Ȋ�@������������Ȃ��B �@����āA���̏o��@�֔p�~�ɂ��ẮA�ّ��ɔp�~�_�݂̂�i�߂�̂ł͂Ȃ��A�^�̒n���������v�̎����̂��߂ɂ��A�n��Z���̈��S���S�ɒ��ڐӔC��L���A�Y�ƁE�ٗp�����ׂ���b�����̂̈ӌ����[���ɔ��f������ŋc�_���s���A�܂�����Ƃ����̏o��@�ւƏ[���ȘA�g���S�ۂ����悤�v�]���A�����Ɍ��c����B |
|
�@����24�N2��6�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s���� �@���� �F�� |
|
|
|
| ���������Đ����ʑ[�u�@�̊T�v�A�������̊J���Ȃǂɂ��āA���앜�����S����b�A�ז쌴�����̂̎����y�эĔ��h�~�S����b��������������ƁA�ӌ��������s���܂����B��c�ɂ́A�{���̐��˕����s�����o�Ȃ��܂����B�o�Ȃ̎s����������́A�����̕⏞�A�[�I���C�g�s���ɂ�鍢��A���u����̊m�ہA�C���t���̐����A������҂̋A�҂Ɍ������肾�āA�S�̃P�A�̕K�v���A���ː��ʑ���̌��\��������X�ӌ����o����܂����B�i�����͂������j | |
  |
|
|
|
| �����{��k�Ђ̔�Ў҂ɑ���x�������Ƃ��ċ��s�{�X�L�b�X�W���|���l����q���p�X�L�[�E�F�A�[�Ȃǂ̖h������A���ݏZ��ɏZ��ł����Ў҂̌��ւ��͂��������܂����B | |
  |
|
|
|
| ��18�q�͑��Q���������R��������������w�j�Ɋւ��A�����̑Ώۋ��������S��Ƃ��A���ׂĂ̌������̑ΏۂƂ���悤�ɋ��߂�ً}�v���������m�����͂��߂Ƃ������q�͑��Q�c��ɂčs���A�{��玺���Îᏼ�s���A��ؔ��͎s���A�R���쑽���s�����Q���������܂����B�o�ώY�ƏȁA�����Ȋw�ȁA����}�A�����}�A�����}�y�ь��I�o����c���ɑ��v�]��������������܂����B | |
      |
|
���������S�楑S�����̢����I���ɌW�鑹�Q�v���̊m���Ȕ����Ɋւ���ً}�v�] |
|
| �@�����Q�R�N�P�Q���U���Ɍ��q�͑��Q���������R����ɂ����āA�u���Ԏw�j�Ǖ�v�����܂Ƃ߂��A�u����I���ɌW�鑹�Q�v�͈̔͂������ꂽ���A����A��ÁA���Òn���̎s�������ΏۊO�Ƃ���A�{���̔�Q�̎��Ԃ�S�����f�������̂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �@���q�͔��d�����̂̔����ȗ��A�u�����v�Ƃ��������Ōh���̓I�ƂȂ�A�q�ǂ������̓]�o��]�Z��ł̍��ʂ⌧�O�h���{�ݓ��̗��p���ہA�������i���o�[�̎����Ԃւ̍��ʓI�s�ׂȂǁA�ޏk�������ł̐�����]�V�Ȃ����ꂽ��A�������Y�i�̊����Ȃǖ{���ɑ��镗�]��Q�������Ȃ������S��A�����镪��Ō����ɐ����Ă���A�S�Ă̕��������������ɂ킽��傫�ȐS�̏��������Ƃ͕�����Ȃ������ł���B �@�u���Ԏw�j�Ǖ�v�̑ΏۊO�Ƃ��ꂽ�s�����ɂ����Ă��A�w�Z�ł̉��O�����̐�������ː�����ւ̕s���ɂ�鐶����̑����ȂǁA�l�X�ȑ��Q�����Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B �@�܂��A���w�����̌������ɔ����A�Z���̋A�ғ��Ɍ�������̓I�Ȏ�g�݂��i�߂��Ă������ƂɂȂ邪�A�u�������l�̑r����������ɔ������Q�v�ɂ��ẮA���܂��ɑ��Q�͈̔͂̏ڍׂȗތ^����Z���̍l���������m�Ɏ�����Ă��炸�A�������܂������s���Ă��Ȃ��ɂ���B �@���́A���������������������Ǝ~�߁A����������l��l�̔�Q�̎��Ԃ܂����\���Ȕ������v�����m���ɍs����悤�A�u�w�j�v�ɖ��m�ɔ��f�����邱�Ƃ͂��Ƃ��A������̂ƂȂ�����Q�ҋ~�ς��s���ȂǁA���q�͔��d�����̂��Ȃ���ΐ����邱�Ƃ̂Ȃ������S�Ă̑��Q�ɂ��āA���Ƃ��Ă̐ӔC���Ō�܂ʼnʂ����ׂ��ł���B �@����āA�Q�O�O���l���������̑��ӂƂ��āA���L�ɂ��Ă̑��}�ȑΉ��������v�]����B �P �����S�楑S�����́u����I���ɌW�鑹�Q�v�́u�w�j�v�ւ̔��f (1) ���_�I��ɂ⎩��I���ɔ�����p�A������̑�����p�ȂǁA�������ꂼ��̔�Q�̎��Ԃ܂��A�u����I���ɌW�鑹�Q�v�������S�楑S������ΏۂɊm���ɔ��������悤�A�u�w�j�v�ɖ��m�ɔ��f�����邱�ƁB (2) ��Q�̎��ԂɌ��������\���Ȕ������m���ɍs����悤�A�K�Ȕ������Ԃ��m�ۂ��邱�ƁB �Q �u�������l�̑r����������ɔ������Q�v�̗ތ^���� ���w�����̌������⏜���̏��܂��A���w�����O���܂߂����Q�̋�̓I�ȗތ^����i�߁A�X�ɏڍׂ����m�Ɂu�w�j�v�ɔ��f������ƂƂ��ɁA�����S�ӔC�������Ď�̓I�ɁA�����̔����͈́A�Z�����̑S�̑������x�����̎������̃��[�h�}�b�v�𑁋}�Ɏ������ƁB �R �u���q�͔�Q���}�����v�ɂ���Q�ҋ~�ς̑��}�Ȏ��{�Ə\���ȍ����̊m�� (1) ���q�͔��d�����̂ɂ��[���ȉe�����Q�������Ă�����̂́A���s�̘g�g�݂ɂ��ʂ̔����ł͉�������Ȃ����̂ɂ��ẮA�u���q�͔�Q���}�����v�̊��p�ɂ���āA������̂ƂȂ�����Q�ҋ~�ς𑁋}�ɍs�����ƁB (2) �����d�͂ɂ�鑹�Q�����y�э�����̂ƂȂ��Ď��{����~�ςɕK�v�ȏ\���ȍ������m�ۂ��邱�ƁB �S �����d�͂ɑ���w���� (1) �u�w�j�v�͔����͈͂̍ŏ����̊�ł��邱�Ƃ𓌋��d�͂ɐ[���F�������A�u�w�j�v�ւ̋�̓I�Ȕ��f��҂��ƂȂ��A�u���Ԏw�j�Ǖ�v�Łu����I���ғ��ɌW�鑹�Q�v�̑ΏۂɂȂ�Ȃ���������A��ÁA���Òn���̎s�����ւ̏\���Ȕ������m���ɍs�킹�邱�ƁB (2) ��Q�҂��ꂼ��̌ʋ�̓I�Ȏ���ɂ�鑹�Q�ɂ��āA�_��v���ȑΉ���������ƂƂ��ɁA��Q�҂̒u����Ă��錵����������\���ɓ��܂��A���ӂ������đS�Ă̔����������t���A���₩�Ɏx�������s�킹�邱�ƁB |
|
����23�N12��22�� ���������q�͑��Q�c���@�������m���@�����Y�� �������s�����@�����s���@���ˍF�� �������������@���������@�������� ���������Òn���������@�w�}���@������ ��������Ö떃�������@�k���������@�����q�� �����������n���������@���Ò����@��֏��� ������������n���������@�I�q�����@���c�K�� �����������͒n���������@���������@�������� �������s�c��c�����@���킫�s�c��c���@�g�c�� �����������c��c�����@���c���c��c���@�ؓc���� ���������Òn�������c��c�����@�w�}�c��c���@���N�� ��������Ö떃�����c��c�����@�֒c��c���@���V�� �����������n�������c��c�����@�O�����c��c���@�p�c�Ɉ� ������������n�������c��c�����@�����c��c���@��ؓ��j �����������͒n�������c��c�����@��葺�c��c���@����ڐ��� |
|
|
|
| ��18�q�͑��Q���������R��������������w�j�Ɋւ��A�����̑Ώۋ��������S��Ƃ��A���ׂĂ̌������̑ΏۂƂ���悤�ɋ��߂�ً}�v���ˉ�A�����Îᏼ�s���A��ؔ��͎s���A�R���쑽���s�����獲�����m���ɑ��s���܂����B | |
  |
|
�ً}�v�� |
|
| �@����A��18�q�͑��Q���������R��������������w�j�ŁA�����Ώۂ̒n�悪���肳�ꂽ���Ƃɂ́A����[�����ł�����̂ł͂Ȃ��A�����̑Ώۋ��������S��Ƃ��A���ׂĂ̌������̑ΏۂƂ��邱�Ƃ��������߂���̂ł���B �@���w�����o�Ă��Ȃ��n�悩��̎���I�ɔ����l���A�����ɂƂǂ܂����l�����l�ɔ����̑ΏۂƂȂ������Ƃɂ́A���̕]���͂ł��邪�A�����̑Ώۋ��Ƃ�������n��̎�����\�����܂������̂łȂ��A���������A���˔\�̐��_�I�s���ɐ��������邱�Ƃ͂ł����A����̋��|��s��������Ȃ��畜�������ĕK���Ɏ��g��ł���Z���̋C�����ɗ��������̂ł͂Ȃ��B �@����āA����̎w�j�𑁋}�ɉ��P���A���_�I���Q�����������S��A���ׂĂ̌����S�����ΏۂƂ��邱�Ƃ����ɋ��������|����悤�v������B �@�����Q�R�N�P�Q���W�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@���ˁ@�F�� |
|
|
|
| ���q�͑��Q�c��ɂ�錴�q�͑��Q�����̊��S���{�����߂�ً}�v�]���s���{���͕y�˕�����Q�����A��c�A���앶���Ȋw��b�A�}��o�ώY�Ƒ�b�y�ъe���}�ɑ��v�]�����o�������܂����B | |
  |
|
| ���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɋւ���ً}�v�] |
|
| �@�u���������q�͑��Q�c��v�́A�����Q�R�N�X���Q���A������������v�c�����āu���q�͑��Q�����̊��S���{�����߂鑍���N���v���J�Â��A���y�ѓ����d�͂ɑ��A���ځA�v�]��v�����s�����Ƃ���ł���B �@�����d�͂ɑ��ẮA��ʁA�����̕��j��l�������������߁A�u���J����v���s�������A�w�Ǝ��̔��f�ɂ�葹�Q�͈̔͂�F�肷�邱�Ƃ͍���ł���x�Ɖ��������悤�ɁA�����҈ӎ����S���݂�ꂸ�A�u���Ԏw�j�v���������o�Ȃ��l�������炩�ɂȂ����B �@���́A�����d�͂ɑ��A�u�w�j�v�͔����͈͂̍ŏ����̊�ł���Ƃ̔F���̉��ŁA���q�͍ЊQ�̌����҂Ƃ��Đ������_��ɑΉ�����悤�w������ƂƂ��ɁA��Q�̎��ԂɌ��������\���Ȕ������v���ɍs����悤�A�u�w�j�v�ւ̑��₩�Ȕ��f�A������̂ƂȂ�����Q�ҋ~�ς̎��{�ȂǁA���q�͔��d������Ƃ��Đ��i���Ă����ӔC���Ō�܂Ŋm���ɉʂ����ׂ��ł���B �@����āA�Q�O�O���l���������̑��ӂƂ��āA���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɖ��L�ɂ��Ă̑��}�ȑΉ��������v�]����B �P �����d�͂ɑ���w���� (1)�u�w�j�v�͔����͈͂̍ŏ����̊�ł��邱�Ƃ𓌋��d�͂ɐ[���F��������ƂƂ��ɁA���ӂ������Ă��ׂĂ̔����������t���A���₩�Ɏx�������s���A��Q�̎��ԂɌ��������\���Ȕ������m���ɍs�킹�邱�ƁB (2) ���̎����ɂ��ẮA���q�͔��d�����̂ɋN�����Ē����I���[���Ȕ�Q�������Ă��邱�Ƃ��\���ɓ��܂��A�����҂ł��铌���d�͎���ɂ��K�A�_��ȑΉ��������邱�ƁB �E�n�k�A�Ôg���ɂ�镡���I�v���������Q �E���w�������̎���ɂ����铐���Q�A�ƒ{���ɂ���Q �E�����̓]�E�A�]�ƂȂǓ��ʂ̓w�͂��s�����҂ւ̔z�� (3) ��Q�҂ɑ傫�ȕ��S�������Ȃ��悤�A���������葱���̊ȑf���𑁋}�ɐi�߁A�ŏI�I�ȁu���ӏ��v�ɂ��ẮA��Q�҂��[�����锅�������S�ɂȂ��ꂽ��Ɏ����킵���s����� ���ɂ����邱�ƁB �Q ���ׂĂ̑��Q�́u�w�j�v�ւ̔��f ���q�͔��d�����̂��Ȃ���ΐ����邱�Ƃ̂Ȃ��������ׂĂ̑��Q�ɂ��Ċm���ɔ����̑ΏۂƂȂ�悤�A�X�Ȃ�ތ^����i�߁A���ɁA���̎����ɂ��ẮA�u�w�j�v�ɋ�̓I�����}�ɔ��f�����邱�ƁB (1) ���ׂĂ̌����̐��_�I���Q �����S��A���ׂĂ̌����̐��_�I���Q���̑Ώۂɂ��邱�ƁB (2) ���Ԃ̌o�߂ɔ������_�I���Q�̑��z ���_�I���Q�̊�z�����Ԃ̌o�߂ɔ������z�͍s�킸�A���z���邱�ƁB (3) �ً}�����������؍ݎ҂̐��_�I���Q ���҂Ɠ����̔������s����悤�ɂ��邱�ƁB (4) ���w����������̏\���Ȕ������Ԃ̊m�� ���w���̉�����ɂ����Ă��A�A�҂̗L���ɂ�����炸�A�����s�������S�ɂȂ��Ȃ�܂ŁA���_�I���Q���̔������s����悤�ɂ��邱�ƁB (5) ����I���ɔ�����p ����I���ɔ�����ʔ��h����A����������ɂ��āA�����̑Ώۂɂ��邱�ƁB (6) ���]��Q��ɗv�����p ���Ǝ҂⎩���̂����{���镗�]��Q���ŏ��ɂƂǂ߂邽�߂̑�ɗv�����p���̑Ώۂɂ��邱�ƁB (7) ���`���Y�Ɋւ��鑹�Q ������u�̂���v��u�����h�ȂǁA�m�I���Y�����܂ޖ��`���Y�Ɋւ��鑹�Q���̑Ώۂɂ��邱�ƁB (8) ��Q�Ҏ��炪���{���鏜���E�����ɗv�����p �����S��ɂ�����������̏����A�����ɗv�����p�����ׂĔ����̑Ώۂɂ��邱�ƁB (9) �������l�̑r���E�����ɔ������Q ���w�����O���܂߁A�l�X�ȃP�[�X�ɑΉ��\�ȋ�̓I�A�ڍׂȗތ^���𑁋}�ɍs�����ƁB (10) �n�������c�̂̑��Q �Ŏ������m���ɔ����̑Ώۂɂ��邱�ƁB �R ������̂ƂȂ����~�ϓ��̎��{ (1) ���q�͔��d�����̂ɂ��e���E��Q�̎��Ԃ͂�����̂́A���s�̘g�g�݂ɂ�锅���ł͉�������Ȃ����̂����邱�Ƃ���A������̂ƂȂ�����Q�ҋ~�ς��s�����ƁB �E���q�͔��d�����̂ɋN�������l���̌������n�ߒn��R�~���j�e�B�̕���A�g�ӂ����܁h�u�����h�̑r���E�C���[�W�̒ቺ�A�l�I�����̗��o�Ȃǂɂ��n��o�ώЉ���S�ʂɂ����钷���I�ȉe���A�픘���ɂ�鏫���̐����ւ̕s���Ƃ���ɔ�������I���ȂǁA�S�����ɐ����Ă����Q�ɑ��A�u���q�͔�Q���}�����v���ɂ���đΉ����邱�ƁB (2) �����d�͂ɂ�鑹�Q�����y�э�����̂ƂȂ��Ď��{����~�ςɕK�v�ȏ\���ȍ������m�ۂ��邱�ƁB |
|
�����Q�R�N�P�P���Q�S�� ���������q�͑��Q�c�� ��@�@�������m���@�����Y�� ����@�i�`�O���[�v�����d�͌������̔_�{�Y�����Q���������������c���@�������� ����@���������H��A�����@�c�q�����Y ����@�������s�����@�����s���@���ˍF�� ����@�������������@���������@�������� |
|
|
|
| �������I�o�̍���c���ƌ����e�s���Ƃ̈ӌ���������s���܂����B�����{��k�Ђ���̕����E�����Ɍ����A�e�s�������錻��Ɖۑ�ɂ��Ĉӌ��������܂����B�e�s������́A�����ӔC�������ĕ��˔\������y�э����x���Ȃǂ����߂锭��������܂����B | |
    |
|
|
|
| ��3��ڂ̉�c��{���s�ŊJ�Â��܂����B���{�{���s�����爥�A������A�{���s�̓�����������������{���s�̌����ƍ���̎��g�݂ɂ��Ă̐�����k�Ђœ|���{���s�����̎��@���s���܂����B�܂��A�e�s�Ԃł̏��������s���A������Ƃ̐i�����ɂ��Ĉӌ��������܂����B | |
    |
|
|
|
| �����{��k�Ђ̔�Ў҂ɑ���x�������Ƃ��ē�������s�����܁E���b�O�E�H�[�}�[�Ȃǂ̖h������A���ݏZ��ɏZ��ł����Ў҂̌��ւ��͂��������܂����B | |
      �i��܂������肵��������肨��̂��莆���܂����B�j |
|
|
|
| �ז����b�A���R����b���������������A�s�������ɑ��A�����̃��[�h�}�b�v�̐������s���܂����B�o�Ȃ������˕����s���A���{�{���s���A�O�ۓ�{���s���A�m�u�c�ɒB�s���炩��́A���u����̊m�ۂ⒆�Ԓ����{�݂̐ݒu�ꏊ�E���ԁA�ŏI������̌��A�R���ċp��̑��݂ȂǗl�X�Ȉӌ��v�]���o����܂����B�i�����͂������j | |
  |
|
|
|
| �����珜����p�ɂ��ẮA�T�~���V�[�x���g�����̒n��ɂ����ẮA�����x���̑ΏۊO�Ƃ���Ƃ̕��j�������ꂽ���Ƃ��A���ˉ��蕜�����{���������n���{���A���q�͍ЊQ���{�����n���{���y�ь��ɑ��A�f�ōR�c������|�A�v�����s���܂����B | |
  |
|
�R�@�@�c�@�@�� |
|
| �@������ꌴ�q�͔��d�����̂ɔ������w����O�œ��X�������Ă��錧���̑����́A���ː��̕s��������Ȃ���A�q�ǂ������ĉƑ�����邽�߁A����I�ɏ������s���A�����Ɍ��̐������ɖ߂邱�Ƃ�����Ă���B�܂��A�s����������O�ւƔ��Ă��鑽���̌���������B �@����A���Ȃ��������u�����v��̍���ɂ��āv�ɂ����āA���w�����O�ɂ�����lj�������ʂ��N�ԂT�~���V�[�x���g�����̒n��́A�����ː��ʂ������Ǐ��I�ȏ�����p������������̎x���͂Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ����B �@���̂��Ƃ́A���������ĕK���Ɏ��g��ł��錧���̐S���S���������Ă��Ȃ����̂ŁA����[���ł�����e�ł͂Ȃ��B �@�����̏����ɔ�����p�́A�S�āA���q�͔��d������Ƃ��Đ��i���Ă����������S���ׂ����̂ł���B �@����āA����̊��Ȃ����������j�ɑ��A���d�ɍR�c����B �@����23�N9��29�� �������{�� �@�@���n���{�����@�g �c�@��@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�@���ˍF�� |
|
�v�@�@�]�@�@�� |
|
| �@������ꌴ�q�͔��d�����̂ɔ������w����O�œ��X�������Ă��錧���̑����́A���ː��̕s��������Ȃ���A�q�ǂ������ĉƑ�����邽�߁A����I�ɏ������s���A�����Ɍ��̐������ɖ߂邱�Ƃ�����Ă���B�܂��A�s����������O�ւƔ��Ă��鑽���̌���������B �@����A���Ȃ��������u�����v��̍���ɂ����āv�ɂ����āA���w�����O�ɂ�����lj�������ʂ��N�ԂT�~���V�[�x���g�����̒n��́A�����ː��ʂ������Ǐ��I�ȏ�����p������������̎x���͂Ȃ����Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B �@���̂��Ƃ́A���������ĕK���Ɏ��g��ł��錧���̐S���S���������Ă��Ȃ����̂ŁA����[���ł�����e�ł͂Ȃ��B �@�����̏����ɔ�����p�́A�S�āA���q�͔��d������Ƃ��Đ��i���Ă����������S���ׂ��ł���B �@����āA����̊��Ȃ����������j��P�A������p�������S�z���S���邱�Ƃ����ɋ��������|����悤�v�]����B �@����23�N9��29�� �@�������m���@�����Y���@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�@���ˍF�� |
|
|
|
| ��2��ڂ̉�c���J�Â��A�ɓ�����撲���������A���R���n��U���ے��A���{���n��U���ە��ے�����u���q�͍ЊQ�ɂ���Вn��̍Đ��Ɋւ�����ʖ@�ɂ��āi�����Đ����ʖ@�i���́j�j�v�A���茧�����E�����v��ے�����u�����������r�W�����v�ɂ��Ă��ꂼ�����������܂����B �܂��A�e�s�Ԃł̏��������s���A���ꂼ��̏����v�擙�ɂ��Ĉӌ��������܂����B | |
  |
|
|
|
| ������ꌴ�����̂ɌW�鑹�Q�����̊��S���{�����߂镟���������N�����������L�O�قōs���܂����B�����N���ɂ́A�����̎y�ыc��c�����400�l���Q�����܂����B����A�����Ȋw�ȋy�ѓ����d�͂ɑ���v���������s���܂����B | |
  |
|
���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɋւ���ً}�v�] |
|
| �@���q�͔��d�����̂̔������甼�N���o�߂��悤�Ƃ��Ă��邪�A�����Ɏ����̓r��ł���A���q�͍ЊQ�́A�����S��ɐr��ȑ��Q�������Ă���B �@���������̌������A���ː��ɂ��댯��������邽�߂ɔ���]�V�Ȃ�����A���ݏZ��ŕs���Ȑ����𑗂�A���Ǝ҂͎��ƍĊJ�Ɍ����Č����ɓ��ݏo�����Ƃ��Ă��邪�A�ċN�̌��ʂ��͌������A�ɂ߂Č������ɒu���ꑱ���Ă���B �@�����������A����W���T���A���q�͑��Q���������R����ɂ����āu���Ԏw�j�v�����肳�ꂽ���A�������̔�Q���\���ɔ��f�������̂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �@��X�����ɖ]�ނ��Ƃ́A�R���P�P���̎��̈ȑO�̐����ɖ߂邱�Ƃł���A�{�����̂ɂ���ĕ���������������l�X�ȑ��Q�́A���ׂĔ�������邱�Ƃ��匴���ł���B �@�����d�͂́A�X�����̐�����t�A�P�O�����̎x�����J�n��ڎw�����Ƃ�\�������Ƃ���ł��邪�A���q�͍ЊQ�̌����҂ł��邱�Ƃ�Y�ꂸ�A�u���Ԏw�j�v�ɖ��L����Ă��Ȃ����Q�ɂ��Ă����L�������̑ΏۂƂ��ׂ��ł���A���́A���q�͔��d������Ƃ��Đ��i���Ă����ӔC�̉��ŁA�Ō�܂Ŋm���ȋ~�ς��ʂ����ׂ��ł���B �@����āA�Q�O�O���l�����̑��ӂƂ��āA���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɖ��L�ɂ��Ă̊m���ȑΉ��������v�]����B �P ��Q�̎��ԂɌ��������m�����v���A�\���Ȕ��� ���q�͍ЊQ�ɔ������Q�́A�����ɂ킽��A�����S��ŗl�X�ȕ���ɋy��ł��邱�Ƃ���A����܂łɔ�����A�����č�����ł��낤���Q�ɂ��ĕ��L���Ƃ炦�A���̐ӔC�̉��ŁA��Q�̎��� �Ɍ��������m�����v���A�\���Ȕ��������s�����ƁB �Q ���]��Q�A�Ԑڔ�Q���̌o�ϓI���Q (1) ���]��Q�ɂ��ẮA���q�͔��d�����̂Ƃ̑������ʊW���ʂ̗��ɂ�苁�߂��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A���Q�͈̔͂���蕝�L���Ƃ炦�A�����̑ΏۂƂȂ鑹�Q�̍X�Ȃ�ތ^����i�߁A�u�w�j�v�ɖ��m����̓I�ɔ��f�����邱�ƁB (2) ���]��Q���ŏ��ɂƂǂ߂邽�߁A���Ǝ҂̂��ꂼ�ꂪ�w�͂��Ď��{���Ă��镗�]��Q��ɗv�����p���m���ɔ����̑ΏۂƂȂ�悤�u�w�j�v�ɖ��m�Ɏ������ƁB (3) �Ԑڔ�Q�́A�����S��ł����鎖�Ǝ҂ɐ����Ă���A�c�ƁA������͈̔͂́A�n���I�ɂ����肳��Ă��邱�Ƃ���ʓI�ł���A�����̑ΏۂƂ���v���Ƃ��āA���B�擙�́u����v���Ȃ����Ƃ����������߂邱�Ƃ͎��Ԃɑ����Ă��Ȃ����Ƃ���A���}�Ɂu�w�j�v�̌��������s�����ƁB (4) �Ԑڔ�Q�ɔ�����֕i���m�ۂ��邽�߂ɗv�����lj��I��p�ɂ��Ă��A�m���ɔ����̑ΏۂƂȂ�悤�u�w�j�v�ɖ��L���邱�ƁB (5) �o�ϓI���Q�́A�Ǝ�ɂ���Ď⒲�B���̊����n�悪���� �����Ȃǂ̓��ꐫ�����邱�Ƃ��\���ɓ��܂��A�X�Ȃ�ތ^�����s���u�w�j�v�ɋ�̓I�Ɏ������ƁB �R �����E������p�� ���ː��ɂ�鉘���́A���{�ɂ����w�������z���čL�͈͂ɐ����Ă��邽�߁A���ׂĂ̌����̌�����p�A�����S��ɂ�����������̌����A�����ɔ�����p�A����ɂ́A���ː��ɂ�錒�N��Q��������邽�߂̑�ɗv�����p�ɂ��āA�m���ɔ������̑ΏۂƂȂ�悤�u�w�j�v�ɖ��m�ɔ��f�����邱�ƁB �S ���_�I���Q�A������ (1) ���_�I���Q �A���q�͍ЊQ�ɔ����������܂˂�����Ă��鐸�_�I�ȋ�ɂ́A��ʓI�E���ۓI�s������뜜���ɂƂǂ܂�Ȃ��W�R���̋ɂ߂č������Q�ł��邱�Ƃ��u�w�j�v�ɖ��m�ɔ��f�����A�������邱�Ƃ��ł����ɑ؍݂��Ă���҂��܂߁A�����S��A���ׂĂ̌��������̑ΏۂƂ��A�����̔F�ۂɓ������āA�ʎ���ɂ�锻�f�Ɉς˂��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB �C�u���Ԏw�j�v�Ŏ����ꂽ���Q�z�̎Z����@�ɂ��ẮA��Q�҂̎��ԂɌ������������ƂȂ�悤�A����ɂ��敪�̌��������s���A���Q�̊�z�������グ�A�ꗥ�Ɉ��z�̎Z��Ƃ��A���z�̐�����ɂ��ẮA�ʂɊm���Ȕ������Ȃ����悤�ɂ��邱�ƁB �E���q�͔��d�����̂������Ɏ����̓r��ɂ����āA���̒������ɔ����s����ő����A�����ɑ����]���ȂǁA���_�I�ȋ�ɂ͓����Ƃɑ��債�Ă������̂ł���A�܂��A���ݏZ��ւ̈ړ]�ɔ���������X�ɑ������邱�Ɠ����\���ɓ��܂��A���_�I���Q�̊�z�����Ԃ̌o�߂ɉ����Č��z����̂ł͂Ȃ��A�ނ��둝�z�����Ă����悤�A�u���Ԏw�j�v�̍l�����𑁋}�Ɍ��������ƁB �G�ً}���������ł́A������������I�Ȕ����߂��Ă���ɂ�������炸�A�u���Ԏw�j�v�ɂ����āA6��20���ȍ~�ɔ����J�n�����ҁi�q�ǂ��A�D�w�A�v���ҁA���@���ғ��������j��ΏۊO�Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A���������Ƃ�Ă��Ȃ��B���{�͍����݂�����I�Ȕ������߂Ă���̂ł��邩��A�����Ȑ������j�Q���ꑱ���Ă��鎩��ɑ؍݂��Ă���҂��܂߁A����ɔ��������鐸�_�I���Q�ɂ��Ċm���ɔ����̑ΏۂƂ��邱�ƁB �I���w�����������ꂽ��ɂ����Ă��A���q�͔��d������ ���̂��̂����S�Ɏ������A�����̎��{�ɂ���ĕ��ː��̔픘�ɑ���s�����Ȃ��Ȃ�܂ŁA���̊Ԃ̐��_�I��ɂɂ��Ă��������̑ΏۂƂ��邱�ƁB (2) ������ ���ː������ɂ�鉘���̊댯�������O���Čh���������Ȃ�S������������L���Ă���Ƃ��Č����S��̕��]��Q�����ׂ����Q�ƔF�߂邱�ƂƂ����l�������\���ɓ��܂��A������ɗv�����p�ɂ��Ċm���ɔ������̑Ώۂɂ��邱�ƁB �T �����̌����� �ً}���������̉����A��������n�_�̐ݒ蓙�A�����̌������ɓ������ẮA�n��Z���ɍ����������Ȃ����Ƃ���ɁA������������]�V�Ȃ�����A���͐V���ɔ������߂���Z���͂��Ƃ��A���w���̉����ɔ����A���Z���ɑ��鐶���x���ɖ��S�������ƂƂ��ɁA���̎��ԂɌ��������\���Ȕ��������s�����ƁB �U �����I�Ȏ��_�ɗ����������ƏI���̐ݒ� ���q�͔��d�����̂��������A���͐��{���ɂ����w����o�א����w�������������ꂽ��ł����Ă��A��Q�҂̐����⎖�Ƃ̗��Ē����ɂ͑����̊��Ԃ�v���邱�Ƃ���A��Q�҂̂��ꂼ�ꂪ�����⎖�Ƃ̍Č����ʂ������Ƃ��ł���܂ŁA���̊ԂɕK�v�ƂȂ�l�X�Ȕ�p�ɂ��Ċm���ɔ������̑ΏۂƂ���ƂƂ��ɁA�����̏I���܂ł͏\���Ȋ��Ԃ�ݒ肷�邱�ƁB �V �����E�g�̓I���Q ���ː��픘�ɂ�錒�N��Q����ɔ������N��Ԃ̈����ȂǁA���q�͔��d�����̂ɋN�����Ĕ���������E�g�̓I�ȑ��Q�ɂ��ẮA���L���������I�ɂƂ炦�A�Ō�܂Ŋm���A�\���ɔ��������Ȃ����悤�u�w�j�v�ɖ��m�Ɏ������ƁB �W ���Q���������葱�� (1) ���q�͑��Q�̔����Ɋւ���@���Ɋ�Â��a���̒�����s���u���q�͑��Q�������������Z���^�[�v�y�ь��q�͑��Q�����x���@�\�@�Ɋ�Â����k�����ɂ��ẮA��Q�҂̐\�����ɂ����闘���ɔz���������̕����ӏ��ɐݒu����ȂǁA��Q�҂ɕ��S�Ȃ��~���ɔ������̎葱�����s�����Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�ƁB (2) ���Q�����̐����ɂ����ẮA�i�ׂɂ�邱�ƂȂ��A���ڌ���a���̒���ɂ��A��Q�҂��\���ɔ[���ł��鍇�ӂɓ������Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�ƁB �X �n�������c�̂̑��Q ���q�͔��d�����̂ɋN�����Ēn���Ŏ��Ɍ����������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��邱�Ƃ���A���Y�����������̑ΏۂƂ��A�n�������c�̂��{�����̂ɔ����Ď��{�����l�X�Ȏ��Ƃɂ��Ă��m���ɔ������̑ΏۂƂȂ�悤�u�w�j�v�ɖ��m�ɔ��f�����邱�ƁB 10 ���ʖ@�i���q�͑��Q�����j�̐��� ���ʂ̌��q�͍ЊQ�́A���j�I�ɂ��ނ����Ȃ��r��ȍЊQ�ł���A�l�X�ȕ���ōL�͈͂������I�ɑ��Q�������Ă��邱�Ƃ���A���s�@�̘g�g�݂ɂƂ���邱�ƂȂ��A���ʖ@�̐��蓙�ɂ��A��Q�҂̎��ԂɌ��������\���Ȕ��������s�����ƁB |
|
���t������b�l ������b�l �����Ȋw��b�l �_�ѐ��Y��b�l ���q�͌o�ϔ�Q�S����b�l ���q�͑��Q�����x���@�\�S����b�l �����{��k�Е������S����b�l ����23�N9��2�� ���������q�͑��Q�c�� ��@�@�������m���@�����Y�� ����@�i�`�O���[�v�����d�͌������̔_�{�Y�����Q���������������c���@�������� ����@���������H��A�����@�c�q�����Y ����@�������s�����@�����s���@���ˍF�� ����@�������������@���������@�������� |
|
| ���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɋւ���v���� |
|
| �@���q�͔��d�����̂̔������甼�N���o�߂��悤�Ƃ��Ă��邪�A�����Ɏ����̓r��ł���A���q�͍ЊQ�́A�����S��ɐr��ȑ��Q�������Ă���B �@���������̌������A���ː��ɂ��댯��������邽�߂ɔ���]�V�Ȃ�����A���ݏZ��ŕs���Ȑ����𑗂�A���Ǝ҂͎��ƍĊJ�Ɍ����Č����ɓ��ݏo�����Ƃ��Ă��邪�A�ċN�̌��ʂ��͌������A�ɂ߂Č������ɒu���ꑱ���Ă���B �@�����������A����W���T���A���q�͑��Q���������R����ɂ����āu���Ԏw�j�v�����肳�ꂽ���A�������̔�Q���\���ɔ��f�������̂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �@��X�����ɖ]�ނ��Ƃ́A�R���P�P���̎��̈ȑO�̐����ɖ߂邱�Ƃł���A�{�����̂ɂ���ĕ���������������l�X�ȑ��Q�́A���ׂĔ�������邱�Ƃ��匴���ł���B �@�o�ϓI�ȑ��Q��_�I���Q�A�n�������c�̂̑��Q�����ł��A���̌�̂P�N�ԂłQ���~�̋K�͂ɏ����̂Ǝ��Z���Ă���A���ア�܂ő����A�ǂ��܂Ŋg�債�Ă����̂��\�����ł��Ȃ��ɂ���B �@�����d�͂́A�X�����̐�����t�A�P�O�����̎x�����J�n��ڎw�����Ƃ�\�������Ƃ���ł��邪�A���q�͍ЊQ�̌����҂ł��邱�Ƃ�Y�ꂸ�A�u���Ԏw�j�v�ɖ��L����Ă��Ȃ����Q�ɂ��Ă����L�������̑ΏۂƂ��ׂ��ł���B �@�ȏ�A�Q�O�O���l�����̑��ӂƂ��āA���q�͑��Q�����̊��S���{�Ɖ��L�ɂ��Ă̊m���ȑΉ��������v������B �P ���Q�����͈̔� (1) �u�w�j�v�̑Ώۂ̗L���ɂ�����炸�A���q�͔��d�����̂��Ȃ���ΐ����邱�Ƃ̂Ȃ��������Q�ɂ��āA���̎����ɂ͓��ɗ��ӂ��A��Q�҂����߂���̂͂��ׂĔ������邱�ƁB �A���_�I�ȋ�ɂ́A����]�V�Ȃ�����Ă��邱�ƂɂƂǂ܂炸�A���{�ɂ��w�������z���Č����S��ŕ��ː��ɂ��s���ɂ��炳��Ă��邱�Ƃ���A���ׂĂ̌����̐��_�I���Q���m���ɔ����̑ΏۂƂ��邱�ƁB �C���{�w���ɂ����ɔ������_�I�ȋ�ɂ́A�����Ƃɑ��債�A���ݏZ��ւ̈ړ]�ɂ�萶����X�ɑ������邱�Ɠ��Ɋӂ݁A���Ԃ̌o�߂ɔ������_�I���Q�̊�z�̌��z�͍s�킸�A��Q�҂̎��Ԃɍ��킹�A�ނ��둝�z���Ĕ������邱�ƁB �E�ً}��������擙�ɂ����Ď���ɑ؍݂��Ă���҂̐��_�I��ɂ����̑�����p�����m���ɔ����̑ΏۂƂɂ��邱�ƁB �G�u���Ԏw�j�v�ɂ����āA���ː������ɂ�鉘���̊댯�������O���Čh���������Ȃ�S������������L���Ă���Ƃ��Č����S��̕��]��Q�����ׂ����Q�ƔF�߂邱�ƂƂ��ꂽ�l�������\���ɓ��܂��A������ɔ�����p�ɂ��Ċm���ɔ����̑ΏۂƂ��邱�ƁB �I���ː��픘�ɂ�錒�N��Q����ɔ������N��Ԃ̈����ȂǁA���q�͔��d�����̂ɋN�����Ĕ���������E�g�̓I�ȑ��Q�ɂ��ẮA���L���������I�ɂƂ炦�A�Ō�܂Ŋm���ɔ������邱�ƁB �@���q�͎q�͔��d�����̂ɋN�����Ēn���Ŏ��Ɍ����������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��邱�Ƃ���A���Y���������̑ΏۂƂ���ƂƂ��ɁA�n�������c�̂��{�����̂ɔ����Ď��{�����l�X�Ȏ��Ƃɂ��Ă��m���ɔ����̑ΏۂƂ��邱�ƁB (2) �n�k�E�Ôg�ɂ�鑹�Q�Ƃ̋敪�����R�Ƃ��Ȃ����A�����I�v��������ꍇ�ł����Ă��A���q�͔��d�����̂ɂ���Ē����I���[���Ȕ�Q���Ă��邱�Ƃ���A���ׂČ��q�͑��Q�Ƃ��Ĕ������邱�ƁB (3) �����d�͂͂���܂ŁA����̂悤�Ȏ��͔̂��������Ȃ����Ƃ������咣���Ă����̂ł��邩��A��Q�҂ɂ͖{�����̂����O�ɑz�肵�A���Q�̉���A�����̑[�u�����҂���Ă��邱�Ƃ𗝗R�ɑ��Q�����𐧌����邱�Ƃ͒f���čs��Ȃ����ƁB (4) �܂��A���Ǝ҂ɂ͎�����ɂ����鎖�O�̃��X�N���U�����҂���Ă��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��āA���Q�͈̔͂����肵�Ȃ����ƁB �Q ���Q���������̎葱�� (1) ��Q�҂̑����~�ς�}�邱�Ƃ��ŗD��ɁA��Q�҂̈ӂ����݁A���ӂ������Ĕ����̎葱����i�߁A���ڌ��ō��ӂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�ƁB (2) ��Q���Q�O�O���l�������ׂĂɋy��ł��邱�ƁA�܂��A�����̔��ɂ��A���Q���ؖ�����؋����ނ̎��W������ȏɂ��邱�Ɠ��܂��A�u���Ԏw�j�v�ɖ��L����Ă���Ƃ���A��Q�҂ɂ��ؖ��̒��x�̊ɘa�ⓝ�v�f�[�^���ɂ��Z����@��p����ȂǁA���������葱���̕��S�y����}��A�v���Ȕ������s�����Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�ƁB (3) ��Q�҂ւ̑��Q�������~���ɐi�߂邱�Ƃ��ł���悤�A��Q�҂̗����ɔz���������S��͂��Ƃ�茧�O�ɂ����Ă������̐��������ł���̐��𑁋}�ɍ\�z����ƂƂ��ɁA�������ڂ̎Z�����n�߁A�����̗l���A�葱�����ɂ��Ă̐�����K�Ɏ��{���邱�ƁB �R �������̎x���� �v���ȋ~�ς��K�v�Ȕ�Q�҂̎��ԂɊӂ݁A���q�͍ЊQ�̌����҂Ƃ��Ă̐ӔC�̉��A�����z�̑S�z���ŏI�I�Ɋm�肷��O�ł����Ă������Ԃ��Ƃ̎x�������s���ȂǏ_��ɑΉ�����ƂƂ��ɁA�����̎�t����͑��₩�Ɏx�������Ƃ��ł���̐��𐮂��邱�ƁB �S �W�c�̓��Ɠ����d�͂̋��c ���������̕��@���̋��c�ɂ����ẮA�W�c�̂�s�����A���̈ӌ����\���ɑ��d����ƂƂ��ɁA���ӂ������Ē��J�ɑΉ����A��Q�҂��[���ł��郋�[���Â�����s�����ƁB |
|
| �����d�͊������ �@�В��@���V�@�r�v�@�l ����23�N9��2�� ���������q�͑��Q�c�� ��@�@�������m���@�����Y�� ����@�i�`�O���[�v�����d�͌������̔_�{�Y�����Q���������������c���@�������� ����@���������H��A�����@�c�q�����Y ����@�������s�����@�����s���@���ˍF�� ����@�������������@���������@�������� |
|
|
|
| ������ꌴ�����̂̕��˔\������߂��{���s�s�������N���J�Â���܂����B�_�ƁA���H�ƁA�ό��Ƃ�PTA�Ȃǖ�1,200�l���Q�����܂����B���ł́A������ꌴ�����̂̑����̎����ƕ⏞�̐��̊m�������߂錈�c�����̑����A�o�Ȃ�������c�����ɗv�]��������������܂����B | |
.jpg)  |
|
|
|
| �������肵�Ă��镜���r�W�����Ɋւ��A�e�s���ƍ����m���Ƃ̈ӌ��������s���܂����B�����d�͕�����ꌴ�q�͔��d�����̂ɔ������]��Q��⌧���哱���Ĕ픘���ʂ̒ጸ��}�邱�ƁA�܂��A���ꂫ�̏����̑�����Ȃǂ̈ӌ����o����܂����B | |
    |
|
|
|
| �����d�͕�����ꌴ�q�͔��d���̎��̔����ɔ������]��Q�̈�|�ƌo�ς̉�}�邽�߁A���s�����Âɂ��L�����y�[������w�ōs���܂����B �����P�R�̑S�Ă̎s���o�W���A�āE���イ��E�g�}�g�Ȃǂ̔_�Y������H�i�A�n���Ȃǂ�̔��������܂����B |
|
    |
|
|
|
| �����{��k�Ђ���̈�������������E�������߂����A�e�s�Ԃ̘A�g��[�߂邽�߂ɁA�e�s�Ԃł̏������⌧�ЊQ���{���Ƃ̋��c�̏�A�����̏�Ƃ��Č��s������ɓs�s�̕����A�g��c��ݒu���܂����B��P��ڂ̉�c�ł́A����撲�������ؗ���������Ă��u�������r�W�����v�ɂ��āA���ЊQ���{�������NJ�撲���`�[���Îs���������Q�����u���q�͑��Q�����v�ɂ��Ă��ꂼ�����������܂����B | |
  |
|
|
|
| �����{��k�Ђɂ��X�Βn���n�i�ǂ̕���Ȃǂ������������Ă��邱�Ƃ���A�����̑��i��}�邽�ߌ����y�ؕ����ɑ��ً}�v�����s���܂����B�Ȃ��A�v�]�ɂ͐��ˉ�Ɠn�ӂ��킫�s�����Q�����܂����B | |
  �@ �@�@ �@�@ �@ |
|
�����{��k�ЂɌW���n�ЊQ�������Ƃ̍��ɕ⏕���x�̊g�[���ɂ��� |
|
| �@����23�N3��11���ɔ������������{��k�Ђ́A�䂪���ϑ��j��ő�ƂȂ�}�O�j�`���[�h9.0���L�^���A�������h��Ƃ��̌�P��������Ôg�ɂ��A�����̎����ҁE�s���s���҂��o���ق��A�Z���̉Ɖ�������{�݂�����E���o����ȂǓ��k�n���𒆐S�ɖ��\�L�̔�Q�������Ă���B �@�����̂ɂ����ẮA��Ђ���2�������o�߂������A��Ў҂̋~��������ЊQ�����ɉs�ӎ��g��ł���Ƃ���ł��邪�A�Ɖ����̐�����Ղ�Љ�C���t���̕����͍���ȏ������Ă���B �@���ẮA��K�͐��y�����n�������h�~���Ƃɂ��āA�S�z����Ƃ���ƂƂ��ɑΏۖʐς�ː��Ȃǂ̍̑�v����啝�Ɋɘa������ʑ[�u�����{���邱�ƁB�܂��A���K�͏Z��n����ǎ��Ƃ�Z��n����ǎ��Ƃɂ��Ă��A�⏕���𐓏グ���A�̑�v�����ɘa�������[�u�����{���邱�ƁA�܂��A�t�ɂ��Z�Ɣ�Q���~�ς��邽�߁A�u�ЊQ�ɌW��Z�Ƃ̔�Q�F���^�p�w�j�v�̈�w�̌��������s�����Ƃɂ��āA���ɂ����Ă����ɑ�����������悤�v�]����B�@�܂��A���ɂ����ẮA���K�͂ȋ}�X�Βn���n�i�ǂ̕���Ȃǂ������������Ă��邱�Ƃ���A�����̑��i��}�邽�߁A���K�͋}�X�Βn����h�~���Ƃ����̕⏕���ƂƂ��đn�݂��邱�Ƃ�v�]����B �@����23�N5��24�� �@�������m���@�����Y���@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�@���ˍF�� |
|
|
|
| 5��23���ɐ��ˍF����i�����s���j���m�u�c�ɒB�s���A25���ɎO�ۓ�{���s���̂��Ƃ�K���Q���̐������܂����B | |
    |
|
|
|
| 5��6���ɐ��ˍF����i�����s���j�����Ɖ�Îᏼ�s���A�R���쑽���s���A��ؔ��͎s���A�y�˓c���s���A�����{�{�s���̂��Ƃ�K���Q���̐������܂����B | |
    |
|
|
|
| 4��14���ɐ��ˍF����i�����s���j�����J�G�����n�s���A���䏟���쑊�n�s���A15���Ɍ����v�S�R�s���A�n�ӌh�v���킫�s���A���{����{���s���̂��Ƃ�K���Q���̐������܂����B | |
        |
|
|
|
3��11�������̓����{��k�Ђ̔�Вn�����E����̂��ߗ������ꂽ�S���s����X��i�����s���j�ɑ��A���ˉ���v�]�����o�������܂����B
    |
|
���k�n�������m���n�k�ɔ��������E�����ɂ�����v�]�� |
|
| �T�D������������Ɠ��ւ̎x�� 1�D�������x���[�u �i1�j��Ў����̂����{���镜���E�������Ƃɗv�����p��ł̌��Ɠ��ɂ�錸���ɑ��ẮA����̎����̉^�c�Ɏx�Ⴊ�����Ȃ��悤�����I���p���I�ȍ����[�u���u���邱�ƁB�܂��A���ɕ⏕�E���S�����ɂ��ẮA��Вn������̎���ɉ����ď_��ɑΉ��ł���悤�Ȓ��̘g�����ꊇ��t�Ƃ��邱�ƁB �i2�j�ЊQ�ɌW�镜��������y�щ����������̍ЊQ�Ή��̂��߂̍������v�̑����A�y�є�Ў҂ɑ��錸�Ƒ[�u���ɂ�錸�������l�����A�O�|����t�ȂǁA���ʌ�t�ő[�u���n�ߖ��S�ȍ����[�u���u���邱�ƁB �i3�j��ԁA�x���ɂ�����Ή��E���̐l������܂߁A���^�c�o��S�ʂɂ��č����[�u���u���邱�ƁB �i4�j�������N�ی����Ƃ̔�ی��҂����Ў҂̈�Ô�S���Ə����ɔ����A�ی��҂���n�������̂̕��S���������邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�����[�u���u���邱�ƁB 2�D�x���̐��̐��� �@���ƓI�ۑ�Ƃ��Ĕ�Вn��̕����E�������v��I���v���ɐi�߂邽�߁A�������𑁊��ɑn�݂��A�Ȓ��̘g�g�݂�����I���ꌳ�I�Ȏ��g�݂��s�����ƁB �U�D�����Y�Ɗ�Ղ̕�������� 1�D���C�t���C���̑��������x�� �@���퐶���Ɍ������Ȃ��㉺�����A�d�C�A�K�X�A�ʐM�Ȃǂ̃��C�t���C����������Вn�̑����ł͕s�ʂƂȂ��Ă���A��Ў҂̐�����o�ϊ����̉ɑ傫�ȏ�Q�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�����̑����̑S�ʓI�ȕ����ɂ��āA�����I�Ȏx�����܂߁A���i�̑[�u���u���邱�ƁB 2�D�����{�ݓ��̑��������x�� �i1�j���H�E�͐�E�����E��`�E�`�p�ȂǓs�s�I�@�\��s�������̊�ՂƂȂ�����y�؎{�݂̕����ɂ��āA�����̘g�g�݂ɂƂ���Ȃ��_��\���ȍ����[�u���u���邱�ƁB �i2�j���S�Ȏs�������̈ێ��Ɍ������Ȃ������{�݁A��Î{�݁A�Љ���{�ݓ��̕����ɂ��āA���̐ݒu��̂̔@�����킸�A�����̘g�g�݂ɂƂ���Ȃ��_��\���ȍ����[�u���u���邱�ƁB 3�D�Y�Ɗ�Ղ̑��������x�� �i1�j��Q�����̂ɂ�����`�p�@�\�̑���������}��ƂƂ��ɁA����̂悤�ȑ�ЊQ���ɂ������ʂ╨���̋��_�ƂȂ��v�`�p�̋@�\������}�邱�ƁB �i2�j�V�������n�߂Ƃ���S���Ԃ̑���������}�邱�ƁB 4�D�p�����������ɑ�������x�� �@��Вn�̕����A������i�߂邽�߁A�L��I���c��ɔ��������k�Дp������v�����K�ɏ������邱�Ƃ��ł���悤�A�K�v�ȑ̐��̐����ƍ��킹�A���v�̍����[�u���u���邱�ƁB �V�D��Ў҂̐����Č��� 1�D�����x�� �i1�j���A�H�����͂��߁A�e��̐����K���i�ɂ��āA��Ў҂ɑ��ď\���ȗʂ�����I���p���I�ɋ��������悤�K�v�ȑ[�u���u���邱�ƁB���ɃK�\�������̔R���̊m�ۂɂ��ẮA��Ў҂̐����ێ��̂ق��A��Вn�ɂ�����e�ʂ̕������������x���邽�߂ɕK�v�s���ł��邱�ƂɊӂ݁A���i�̑[�u���u���邱�ƁB �i2�j��Ў҂̌��N���ێ����邽�߁A��Î{�݂̑���������A��Ï]���ҁA���i�̊m�ۓ��ɂ��ĕK�v�ȑ[�u���u���邱�ƁB���ɔ��ł́A�����̒������ɔ����A�������������ƂȂ��Ă��邽�߁A�q���ʂɂ�������P�͂��Ƃ��A�����^���P�A�̏[�����ɂ��Ă����}�Ȏx�����s�����ƁB �i3�j�ЊQ�Ŏ��V���b�N���ɑΉ��ł���悤�A���_�Ȉ�A�ی��t�A�Ō�m�A�Տ��S���m���̊m�ۂɂ��āA�l�I�E�����I�Ȏx�����s���A�S�̃P�A���\���ɂł���悤�z�����邱�ƁB �i4�j���������������x�ɂ��ݕt�i�ً}�����Z���j�̌��x�z�������グ��ƂƂ��ɁA�ݕt����ɘa���邱�ƁB 2�D���ݏZ�����Z������x���� �i1�j�Z���������������̔�Ў҂���������]�V�Ȃ�����Ă��邱�Ƃ���A���}���ݏZ���v���ɒ��邱�Ƃ��ł���悤�A���ݗp�n�⎑�ށE�{�H�Ǝ҂̊m�ۓ��ɂ��ē��i�̑[�u���u���邱�ƁB �i2�j��Ў҂̐�����Ղ̉Ɍ����āA�ЊQ���쎑�����x���̊g�[��A��n�̕����A�Z���̕�C�E�Č��ɗv���鎑���I�ȉ������s���ȂǍő���̎x������u���邱�ƁB 3�D�o�ώx����ٗp�� �i1�j�_�ѐ��Y�Ƃɑ���x�� �@�ƒ{�p������_�Ǝ��ޥ�_�A�_�ѐ��Y�ƂɊւ���K�v�����̈���I�m�ۂɂ��ē��i�̔z�����u���邱�ƁB �A�Ôg�ɂ��_�n�̊����A���`�̑���Ȃǒn��̊�I�Y�Ƃł���_�ѐ��Y�Ƃ���œI�ȑŌ��������Ƃ���A�_�n�E�_�Ɨp�{�݁A���`�E�D���{�ݓ��̑��������Ɍ����čő���̎x���[�u���u����ƂƂ��ɁA���킹�ďW���̍Đ����\�Ƃ���@�I�g�g�݂�����ȂǍL�͂Ȏ��g�݂��s�����ƁB �i2�j������Ƃɑ���x�� �@�n��o�ς̕����ɂ́A������x���钆����Ƃ⏤�X�X���̈ꍏ�������������肪�s���ł���A�������Y�Ǝ{�݁A���Y�ݔ����̕����ɑ���V���ȕ⏕���x�̑n�݂�A���ʂ̎��ƌp���E�ĊJ�Ɍ��������Z�E�Ő��[�u���u����ȂǁA���͂Ȏx�����s�����ƁB �A������Z���ɂ���я��H�����ɂĎ�舵���ЊQ�����ݕt�̗D���[�u�ɂ��āA���ړI�Ȕ�Q�������Ǝ҂̂ق��A������~���̊ԐړI��Q�������Ǝ҂ɑ��Ă��L���K�p�ł���悤�A�������ɘa���邱�ƁB �B�M�p�ۏ؋���̕ۏؘg�ɂ��āA��ʘg���тɊ����̓��ʘg�Ƃ͕ʂɁA�k�Ђ̉e���Ōo�c�Ɏx����������Ă����Ƃ����p�ł���⏞���x��n�݂��邱�ƁB �i4�j�ٗp���� �@��Ў҂̐����Č��Ɍ����Čٗp�̈ێ���}��ƂƂ��ɁA�����E�������Ƃɂ����Ă͔�Вn��̎��Ǝ҂��ق������ȂǁA��Ў҂̐����ێ���A�Ɛ�̊m�ۂ̂��߂ɕK�v�ȑ[�u���u���邱�ƁB �A�ٗp�ی����Ƌ��t�ɂ����āA�x�ƂɌW�����[�u�ɂ��ẮA�ЊQ�ɂ�钼�ړI�Ȕ�Q���Ă��Ȃ������Ƃ̋x�~��p�~��]�V�Ȃ����ꂽ���Ǝ҂܂őΏۂ��g�傷��ƂƂ��ɁA���E�ɌW�����[�u�ɂ��āA�ЊQ�~���@�K�p�n��ȊO�̎��Ə��ł����Ă��k�Ђ̉e���ɂ�莖�Ƃ̋x�~��p�~��]�V�Ȃ����ꂽ���Ə��ɂ܂Ŋg�傷�邱�ƁB �B��Вn�ɂ�����ٗp��Ƃ��āA�]���̒Z���I�ȂȂ��ٗp�ł͂Ȃ��A�����I�E�p���I�Ȍٗp�ƂȂ�ٗp�n�o���Ƃ̑n�݂ȂǁA���{�I�Ȍٗp������{���邱�ƁB �i4�j �������� �����֘A�̐H����Ζ����i���̐k�Ђɂ��֏�l�グ���N���Ȃ��悤�Ď��̐����������邱�ƁB 4�D�q��ĥ����x�� �i1�j��Ў����̏A�w�Ɋւ����p�ɂ��āA���ɂ����đS�z�S���邱�ƁB �i2�j��Ђ����������k����c���A����ҁA��Q�ғ��ɑ��ĕK�v�ȋ���A���E�����T�[�r�X���K�ɒł���悤�A�K�v�ȃX�^�b�t�̊m�ۂ��܂߁A���v�̑[�u���u���邱�ƁB �W�D����̖h�Б��� 1�D�h�Б����̌���������� �@����̒n�k���ɂ�関�\�L�̔�Q�����P�Ƃ��A�e��h�Б�ɂ��Ĕ��{�I�Ȍ��������s�����ƁB�܂��A��Вn�ɂ�����h�Ћ@�\�̑��������E������}��ƂƂ��ɁA���l�̍ЊQ���J��Ԃ��Ȃ��܂��Â����i�߂邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���u���邱�ƁB �X�D���q�͍ЊQ�ւ̑Ή� 1�D�����d�͕�����ꌴ�q�͔��d���ɂ����鎖�̂ɂ��ẮA���́A�ӔC�������Ă������i���u���A�ꍏ���������Ԃ̎����ɑS�͂Ŏ��g�ނ��ƁB �@�܂��A���Ԃ̐[���ɔ�������悪�g�傳�ꂽ�ꍇ�́A���̐ӔC�ɂ����āA�R�~���j�e�B�̐}�����𑬂₩�Ɋm�ۂ��邱�ƁB 2�D���ӏZ���ւ̎x���� �i1�j���̂ɂ����҂ɑ���ǍD�Ȑ�������K�v�����̊m�ۂ͂��Ƃ��A�����ɕs����^���Ȃ��[�u���u����ƂƂ��ɁA�X�N���[�j���O�⏜���̎��{�Ȃǖ��S�̔����Ñ[�u���u���邱�ƁB �i2�j���ː��ʂ𑪒肷��n�_��啝�ɑ��₷�ȂNJ����j�^�����O�̏[������}��A���ӏZ���ւ̕s��������}�邱�ƁB �i3�j���n��ւ̔���]�V�Ȃ����ꂽ�s���̐����Č��ɑ��A�A�E��̊m�ۂ͂��Ƃ��A�����̏A�w�x�����A���S�y���Ɏ�����[�u���u���邱�ƁB �i4�j����]�V�Ȃ����ꂽ���Ƃɂ�萶�����s���̑����⏞�ɂ��āA���͐ӔC�������đ��₩�ɕۏ�[�u���u���邱�ƁB 3�D���q�͔��d���̎��̂̉e���Ŕ�ЁE���ꂽ���X�ւ̎x���� �@��ЁE���ꂽ���X�̐����ۏ�ɂ�����x�����ɂ��āA���y�ѓ����d�͂��ӔC�������Ĉ�����������x��n�݂��A���{���邱�ƁB 4�D���]��Q���� �i1�j���ӂɗ^����e�����ɂ��Đv�����킩��₷�������L���s���ƂƂ��ɁA���k������ݒu����Ȃǎ��ӏZ���̕s��������}�邱�ƁB�܂��A���m�ȑ��萔�l�Ƃ��̉e�����𑬂₩�ɍL�邱�Ɠ��ɂ��A���Ӓn��ɂ����镗�]��Q�����ɖh�~���邱�ƁB �i2�j�_�{�Y���̏o�א����ɂ��ẮA���P�ʂł͂Ȃ��A�Ȋw�I�����Ɋ�Â��n��ʂ̑[�u�Ƃ��邱�ƁB�܂��A�o�ג�~�╗�]�ɂ��_�{�Y�Ƃւ̔�Q�ɑ��ẮA����̐��Y�E���Ɗ����Ɏx�Ⴊ�����Ȃ��悤�A�\���ȕ⏞�Ǝx���𑬂₩�ɍs���A���]��Q�ɔ��������ɂ��č��͍���̕⏞���܂ߊ��S�ȕ⏞�����邱�ƁB 5�D���q�͔��d�����̔�Ў����̋y�юx�����s�������̂ɑ��鍑�ɂ��S�ʓI�Ȏx���̐��̊m�� �i1�j���w���E�����ޔ��w���⎩����̗v���Ɋ֘A���鎩���̂ɂ����ẮA���O�ւ̍L��I�Ȕ����]�V�Ȃ�����A�܂��A����@�\���ړ]���鎩���̂�����ȂǁA��s���s�����Ȓ��Œn���͍������ɂ߂Ă���B����āA�s���@�\�̕⊮���܂߁A���I�E�l�I�x�������̑S�ʓI�ȐӔC�ƍ������S�ōs�����ƁB �i2�j����]�V�Ȃ����ꂽ�Z���������Ȃǂ̎x�������Ă��鎩���̂ɑ��āA�S�ʓI�ȍ����x���[�u�����̐ӔC�ōu���邱�ƁB �@����23�N4��2�� �@�S���s�����@�X���v�@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�@���ˍF�� |
|
|
|
| �����d�͂̏�������A������P���q�͔��d���̔p�F�̕��j���o���ꂽ���Ƃɑ��A���ˉ���玟�̂Ƃ���R�����g�\���܂����B �w�������s�������܂ŋ����v�����Ă���������P���q�͔��d���̔p�F�ɂ��ẮA30���ɓ����d�͂̏�������p�F�̕��j���o���ꂽ�B���̂��Ƃ�O��Ƃ��āA�����d�͂ɂ́A���������ꍏ���������Ԃ̎����������]�ށB�x |
|
|
|
 ������P���q�͔��d���̎��̂ɔ����_�{�Y���̏o�ג�~�ƕ��]��Q�ɑ���⏞�����ɑ���������������悤���{���m���ɑ��A�ً}�v�����s���܂����B�Ȃ��A�v���͌�������Ƃ̘A���Ŏ��{�������܂����B ������P���q�͔��d���̎��̂ɔ����_�{�Y���̏o�ג�~�ƕ��]��Q�ɑ���⏞�����ɑ���������������悤���{���m���ɑ��A�ً}�v�����s���܂����B�Ȃ��A�v���͌�������Ƃ̘A���Ŏ��{�������܂����B |
|
|
������ꌴ�q�͔��d�����̂ɂ��_�{�Y���̏o�ג�~���т� ���]��Q�ɑ���⏞�Ɋւ���ً}�v�� |
|
| �@�����d�͕�����ꌴ�q�͔��d��������o���ꂽ���ː������ɂ��_�{�Y���������g�傷�钆�ŁA���{�͐H�i�q���@�̎b���l������ː����������o���ꂽ���Ƃ���A���q�͍ЊQ�����ʑ[�u�@�Ɋ�Â��[�u�Ƃ��ĕ������Y�̌����y�уz�E�����\�E�A�u���b�R���[�A�L���x�c�Ȃǂ̖�̏o�ג�~���w���������܂����B �@��n�k�̔�Q�ɑ����A���ː������̉����ɂ��o�ג�~�ƕ��]��Q���g�債�A�o�א����ɂȂ����_�{�Y���ȊO�ł������肪�����ԕi�┄���_��̔j���A�̔����ۂȂǂ��������ł���A�_�Ǝ҂͐�s���s���������炭��s���Ƃ��̂Ȃ��{��ɕ�܂�Ă���܂��B ���_�ł́A�����̏o�ׂ��ł����A�p�����������Ă��邾���łȂ��A�������S���r�₦�����ŁA�������R����A�l����Ȃǂ̎x������]�V�Ȃ�����Ă���A�o�c�𑱂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���܂Œǂ����܂�Ă���܂��B �@�܂��A�a����{�A�{�{�ȂǁA�{�Y�o�c�����l�̊�@�I�ɂ���܂��B ����ɁA�엿��_��A�R���A�J�͂ȂǁA���z�̌o��������č���Ă����̂��A�Ƃ������f�̎������}���Ă���܂��B �@���ẮA�����̈��S�m�ۂ�}��ƂƂ��ɁA���{�_�Ƃ����A�_�Ǝ҂���]�������Ĉ��S���Ĕ_�Ƃ𑱂��邱�Ƃ��ł���悤�A���̎����ɂ��č��ɑ������v���肢�܂��B �P�@�_�{�Y���̏o�ג�~�y�ѕ��]��Q�ɂ���Q���Ă��鐶�Y�ҕ��тɊ֘A���Ǝ҂ɑ��A���₩�ɕ⏞�����������A����̍Đ��Y�����A���Ɗ����Ɏx�Ⴊ�Ȃ��\���ȕ⏞�A�x�������{���邱�ƁB �Q�@�b���l����_�Y�������o���ꂽ�ꍇ�ɁA���P�ʂŏo�א�������̂ł͂Ȃ��A�Ȋw�I��������ɂ����n��ʂ̏o�א����Ƃ��邱�ƁB �R�@�_�Y���̌�����Ɣ͈́E���@�m�ɂ��A���ː��̑���A�픘���Ԃ̔c���A�����̐�����������ƂƂ��ɁA�H�̈��S���m�ۂ��邽�߂ɏ����J��O�ꂵ�A���ʋ@�ւ����҂Ɏ��m���s���A�s�������A���]��Q�h�~�ɓw�߂邱�ƁB �S�@����̕Ă��Ȃǂ̍�t���ɑ���_�Ƃ̕s�����������邽�߁A���Ƃ��đ��}�Ɏw�j�������ƂƂ��ɁA���ː��̉e���͈͂ɂ���_�n�ɂ��ẮA�����ɋ��_�̎��Ԓ������s���c���ɓw�߂�ƂƂ��ɁA����y��ɂ�錟�؍͔|���s���K�Ȏw���ɂ�����A���킹�č�t�����Ȃ��Ă��⏞�̑ΏۂƂ���悤�藧�Ă��u���邱�ƁB �@����23�N3��24�� �@�������m���@�����Y���@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�@���ˍF�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������������@�@��a�莟 |
|
|
|
3��11�������̓����{��k�Ђɂ�蔭������������P���q�͔��d���̎��̂ɂ��āA���Ԃ̎����Ɍ��������}�ȑΉ����}����悤���ˉ��菼�{���m���y�я��䓌���d�͕������������ɑ��A�ً}�v�����s���܂����B�Ȃ��v���͌��s�c��c����Ƃ̘A���Ŏ��{���A��z���s�c��c������Q���������܂����B
  |
|
| �ً}�v�� |
|
| ���ʂ̐k�Ђɂ�镟����ꌴ�q�͔��d���ɂ����鎖�̂́A�������ɂƂ��đ�ϗJ�����鎖�ԂɊׂ��Ă���A�����̕s����{��͋Ɍ��ɒB���Ă���B �@�������Ȃ���A���������̌��ʂ��������Ȃ����˔\�R��ɑ��A�����d�͂̑Ή��͂��Ƃ��n���ւ̏����\���Ƃ͌����Ȃ��ɂ���A�ŗD�悳���ׂ����Ԃ̎����Ǝ��ӏZ���� �͂��߂Ƃ��������̈��S�m�ۂւ̑Ή����x��Ă��邱�Ƃ͐��Ɉ⊶�ł���B �@����ɂ́A���̂悤�ȋً}���Ԃɂ����āu�p�F�̌����v�̕\���Ȃlj�Ђ̕ېg�┭�d�{�݂̈ێ���D�悵�Ă���Ƃ����錻�݂̑Ή��𑁋}�ɂ��炽�߁A���Ԃ̎����ɑS�͂������Ď��g�ނ悤�����v������B �@�܂��A�Z���̈��S�����Ӗ��������̑��Ƃ��ẮA�����u���v���������ł��邱�Ƃ������F�����������ƂƂ��ɁA���݁A�N�����Ă���K�\�����ɂ��ẮA���Ɠ��l�ɐ������Ƃ�������̂ł���A���苟�����e�����̂̋��ʂ̉ۑ�ł��邱�Ƃ��\���F���̂����Ή�����邱�Ƃ��d�˂ėv������B �@����23�N3��22�� �@�������m���@�����Y���@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�@���ˍF�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�c��c�����@�@��z���v |
|
| �ً}�v�� |
|
| �@���ʂ̐k�Ђɂ�镟����ꌴ�q�͔��d���ɂ����鎖�̂́A�������ɂƂ��đ�ϗJ�����鎖�ԂɊׂ��Ă���A�����̕s����{��͋Ɍ��ɒB���Ă���B �@�������Ȃ���A���������̌��ʂ��������Ȃ����˔\�R��ɑ��A�����d�͂̑Ή��͂��Ƃ��n���ւ̏����\���Ƃ͌����Ȃ��ɂ���A�ŗD�悳���ׂ����Ԃ̎����Ǝ��ӏZ�����͂��߂Ƃ��������̈��S�m�ۂւ̑Ή����x��Ă��邱�Ƃ͐��Ɉ⊶�ł���B �@����ɂ́A���̂悤�ȋً}���Ԃɂ����āu�p�F�̌����v�̕\���Ȃlj�Ђ̕ېg�┭�d�{�݂̈ێ���D�悵�Ă���Ƃ����錻�݂̑Ή��𑁋}�ɂ��炽�߁A���Ԃ̎����ɑS�͂������Ď��g�ނ悤�����v������B �@�܂��A�Z���̈��S�����Ӗ��������̑��Ƃ��ẮA�����u���v���������ł��邱�Ƃ������F���̂����Ή�����邱�Ƃ��d�˂ėv������B �����Q�R�N�R���Q�Q�� �@�����d�͊�����Ё@������В��@�������F�@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�����@�@���ˍF�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�c��c�����@�@��z���v |