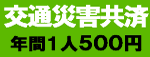平成27年度県予算編成に対する要望
|
※PDF版のダウンロードはこちらからできます。
・目次 ・要望文
|
◆総務部関係
各被災自治体においては、復旧・復興を最優先課題として取り組んでいるところであるが、さらに迅速かつ円滑に復興事業を進めていくためには、被災地の財政需要の変化を的確に捉え、復興に要する経費に対する財源措置の充実及び継続的な確保を図ることが不可欠であるため、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 自治体の東日本大震災及び原子力災害からの復旧・復興に最後まで対応するとともに、社会資本整備交付金(復興枠)や東日本大震災復興交付金などの特別な財政支援については、平成27年度までとされている集中復興期間の終了後も自治体の復旧・復興が果たされるまで継続すること。
併せて、東日本大震災復興交付金については、自治体の意見を踏まえ、弾力的な運用を図ること。
2 震災復興特別交付税については、復旧・復興事業の地方負担分、地方税の減収分等を全額措置することとされているが、復旧・復興のより一層の加速化や、さらなる持続的・安定的な財政運営を進めていくため、平成27年度及び集中復興期間終了後も引き続きこれらの事業が完了するまで継続すること。
3 普通交付税の算定のうち「地域の元気創造事業費(仮称)」については、地域経済活性化の成果を反映するとされているが、特に「第一次産業産出額(道府県分)」や「農業産出額(市町村分)」については、県内では原発事故災害による影響が強く伸び率が期待できないため、「地域経済活性化の成果」において不利な条件とならないよう特殊事情を考慮し算定すること。
4 市町村合併に伴う普通交付税の算定の特例(合併算定替)については、平成28年度から段階的な減額となるが、被災自治体の実情を踏まえ、「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」により起債の延長が可能となる期間まで、特例措置を延長すること。
5 病院建設改良に係る病院事業債について普通交付税措置の対象となるのは、1㎡当たり建築単価30万円までとされているが、震災の影響による労務単価や資材の高騰に加え、消費税増税の影響により、建築費が増加し建築単価を抑えることが困難となっているため、対象となる標準単価について見直すこと。
|
◆企画調整部関係
福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想の
早期実現について |
福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想については、廃炉に向けた最先端の研究を確実に進めるとともに、国内外の産学連携と関連産業等の集積を促進するものであり、去る6月23日には、国の研究会の報告書がとりまとめられるとともに、6月24日には、「経済財政運営と改革の基本方針2014」に地域経済の将来ビジョンとして位置づけられたところである。
当該構想の具現化は、原子力災害で被災した地域の復興・再生のエンジンとなることから、地域産業への波及と実効性が担保されるよう、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 具体的な制度・事業・推進体制を早期に構築すること及び中・長期的な財源を確保すること。
2 浜通り地域の復興に向け、県が主体となって、積極的に浜通り地域の各自治体との調整を行うこと。
3 様々な分野にわたる研究機関を原子力災害被災地に設置するなど、研究拠点の形成等について主体的かつ積極的に取り組むこと。
一刻も早い復興を図るため「福島県復興ビジョン」に基づき「福島県復興計画」が策定されているが、震災からの早期復興を図るためには「福島県復興計画」の迅速かつ着実な推進が重要であることから、これらに必要な予算を確保するよう要望する。
また、各自治体が策定する震災復興計画を確実かつ、効果的に進めるため、復興に向けた取組に対する総合的な相談、支援窓口の設置及び震災復興計画への総合的な財政支援制度の創設を要望する。
原子力災害により再生可能エネルギーに対する関心が高まる中、県においては「原子力に依存しない安全・安心で継続的に発展可能な社会づくり」を復興計画に掲げており、2040年度頃を目途に、県内エネルギー需要の100%以上を再生可能エネルギーで生み出すことを目標としている。
よって、県内における再生可能エネルギーの普及を一層推進するため、次の事項について要望する。
1 「再生可能エネルギー事業可能性調査補助金」、「地域再生太陽光発電モデル事業」等の各種補助制度の平成27年度以降も継続するとともに、導入等に対する支援制度の更なる拡充を図ること。
2 再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事業については、平成27年度までの事業とされているが、事業年度を延長すること。
3 木質バイオマス発電施設建設に対する補助率を嵩上げすること。また、将来の安定的な運営のため、県内における、間伐材、建設廃材等、発電チップの原材料の安定供給に向けたシステムづくりを支援すること。
4 住宅用太陽光発電システムの設置を更に進めるため、住宅用太陽光発電設備設置補助事業を平成27年度以降も継続すること。
5 設備利用率が高く、安定供給が可能な小水力発電の導入を促進するため、設置工事に対する補助制度を創設すること。
6 ペレットストーブ、薪ストーブ、太陽熱利用等の住宅用新エネルギー設置に対する支援制度を拡充すること。
7 浮体式洋上風力発電実証実験への積極的な支援を図るとともに、関連産業の集積に向けた調査研究の実施、風力発電の研究や試験を行う拠点施設の誘致、海域利用に係るコンセンサスの形成及び漁業者との共存に向けた取組などを行うこと。
社会保障・税番号制度の導入に伴い、自治体においては、住民基本台帳システムをはじめ関係業務システムの構築・改修や運用に当たり、非常に大きな負担となっている。
よって、導入スケジュールに配慮し、速やかに必要な情報提供を行うとともに、その経費については、社会保障・税番号制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、地方に新たな経費負担が生じないように、国の全額財政措置について特段の措置を講じるよう要望する。
地域間の情報格差(デジタルディバイト)解消に向けた、情報通信基盤整備についてのユニバーサルサービス化の推進を図るため、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 総務省の情報通信利用環境整備推進事業の要件を緩和し、光回線等の超高速ブロードバンド未整備地区における情報通信基盤整備に対する財政支援を行うこと。
2 総務省の無線システム普及支援事業(携帯電話等エリア整備事業)における財政支援を拡充し、携帯電話不感地域解消に向けた取組を積極的に推進すること。
原子力災害は多岐にわたって大きな影響を及ぼす未曾有の災害であり、震災からの復旧・復興と異なる前例のない長期間の財政負担を要するため、県全体の復旧・復興には原子力災害に特化した施策を国が責任をもって展開することが不可欠である。
よって、原子力災害の早期収束へ向けた着実な取組とともに、正確な情報の提供に努め、施設の長期的・安定的な安全管理が図られるよう、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 現行法体系にとらわれない特別措置をその時々の状況に即し速やかに実施すること。
2 東日本大震災復興交付金について、津波被災地のみでなく原子力災害地域でも活用できるよう対象要件を拡充すること。
3 福島再生加速化交付金について、対象事業及び対象地域を拡充すること。
原子力災害により避難を余儀なくされている長期避難者等の生活拠点の形成に向け、復興公営住宅の整備の方向性等がまとまり、住む場所の見通しはほぼ立ったところである。
今後は、復興公営住宅の整備を早期かつ着実に進めるとともに、入居後のコミュニティ形成に主眼を移す必要があり、避難者同士はもちろん、周辺住民との良好な関係構築が非常に重要となってくるところである。
よって、今後のコミュニティ形成に向けた取組の強化対策として、復興公営住宅に併せて、市民と避難者とが日常的に交流できる施設の整備が必要であることから、次の事項について要望する。
1 コミュニティ形成に資する施設整備は避難元及び避難先自治体に関わる広域的なことであることから、県が主体で行うこと。
2 交流や憩いの場となる、「(公認)パークゴルフ場」等のニュースポーツ施設や、市街化調整区域の仮設住宅の跡地などを活用した「市民農園」、帰還判断がつかない人も利用できる納骨堂のほか、遊歩道や展望台を備え、市民も避難者も利用できる、緑豊かで、樹木葬も可能な「墓地公園」など、復興公営住宅の整備に併せ、地元住民と避難者とが日常的に交流できる施設を整備すること。
3 復興公営住宅を整備することによる急激な人口増加による影響や従来からのコミュニティとの関係性を勘案しながら、地元住民の意向・要望を十分に踏まえながら整備を行うこと。
劇場、音楽堂等における専門的人材の確保に係る
県独自の財政支援について |
国は、劇場、音楽堂等の活性化を図るため、平成24年に「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」を施行し、同法に基づく「劇場、音楽堂等の事業活性化のための取組に関する指針」を平成25年に告示した。
今後、劇場、音楽堂等の設置者又は運営者である地方公共団体が、同法等の本旨に沿い、「質の高い事業」を実施していくためには必要な専門的人材を配置することが求められるが、財政上の理由により、その配置が困難な場合が想定される。
よって、劇場や音楽堂等の設置者や運営者の財政状況に左右されず、「質の高い事業」が実施出来るよう、専門的人材の人件費について、県独自の財政支援を講じるよう要望する。
|
◆生活環境部関係
食品については、モニタリングによる安全性の確認と風評被害の払拭が最重要課題となっていることから、今後とも安全性の確認及び風評被害の払拭のため継続した体制整備が必要である。
よって、迅速かつ円滑な検査実施体制の構築のため自家消費野菜等放射能検査事業を継続するとともに、必要な財政支援及び技術的支援を講じるよう要望する。
生活バス路線は、モータリゼーションの進展に伴い、路線数・利用者数ともに年々減少の一途を辿っている。
自治体においても高齢者や年少者などの交通弱者を守るため、便数維持に努めているが、自治体における財政負担は増大している。
県においては、「市町村生活交通対策事業補助金」等により、各市町村を支援しているが、補助対象・補助率が限られていることから、未だ十分ではない状況にある。
よって、自治体バス運行などの市町村生活交通路線について、引き続き補助を行うとともに、次の事項について要望する。
1 「市町村生活交通対策事業補助金」における路線収支率、輸送量、運行回数などの要件緩和及び補助率の拡充を図ること。
また、道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、市町村が運営主体となる市町村運営有償運送を補助対象としているが、同条に規定する特定非営利活動法人等が運営主体となる過疎地有償運送についても、補助対象とすること。
2 「地域公共交通確保維持改善事業」について、市内完結バス路線を対象とするなどの補助対象の拡充及び補助要件の緩和を図るとともに、国の「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」に協調し、県においても補助対象として、地域内フィーダー系統路線を加えること。
また、平成27年度までとなっている特定被災市町村の指定による補助対象要件の緩和措置を延長すること。
3 バス路線の維持のほか、バス待合所整備など付帯的な部分も含め、公共交通の利便性を高める市町村、交通事業者及び地域の取組に対して財政支援を図ること。
鉄道軌道輸送対策事業費補助については、中小の鉄道事業者を対象に、保安度の向上又は輸送の継続に資するための既存施設の改良・更新を支援するために、鉄道事業者に対し補助をするものであるが、地域鉄道が保有する車両や橋梁、トンネル等は急速に老朽化が進んでいる一方、事業者の経営状況は厳しさを増している。
よって、老朽化施設対策への予算増額を含めた支援拡充など、地元自治体の補助にあたり、県の協調補助による市町村の負担軽減が図られるよう要望する。
阿武隈急行緊急保全整備事業費等補助については、地域の振興及び住民福祉の増進に寄与するため補助を行っているところであるが、阿武隈急行線の安全運行の確保及び住民の生活交通の維持、確保を図るため、引き続き協調補助を行うとともに現行補助率を維持するよう要望する。
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により避難者を受入れている自治体においては救急件数が増加している状況にある。
このため、救急搬送体制を強化することが重要課題となっているが、震災復興措置として実施されている本事業が廃止となった場合、消防本部での高規格救急車の整備や救急救命士の養成を図ることが財政上大変厳しいものとなる。
よって、県内消防本部において安定的かつ持続的に救急医療が提供できる体制を構築するため、救急業務高度化推進事業による支援を平成27年度以降も継続するよう要望する。
自治体においては、住民の安全を守るため空間放射線量率の放射能測定を行っている。
空間線量に関しては、測定機器の貸出しを住民に行ったり、自治体で計測した線量をホームページ等で公開、又は放射線量マップを作成、配布し情報を提供している。
しかしながら、東京電力福島第一原発で昨年8月に行われた3号機のがれき撤去により放射性物質が飛散し、周辺市町村において農作物から放射性物質が検出されるなど、営農活動に著しく影響を及ぼしており、また、モニタリングポストについては、特定避難勧奨地点等の比較的放射線量が高い地域の住民等から、更なる設置の要望があることから、次の事項について要望する。
1 原子力発電所周辺市町村を含めた定時降下物の測定を強化するとともに迅速かつ適切に情報を提供すること。
2 モニタリングポストの設置については、平成27年度においても必要な予算を確保こと。
3 県の支援で購入した機器の校正に関する「線量計等緊急整備支援事業」を今後も継続すること。
原子力災害対策に係る取組については、福島第一原子力発電所の事故が未だ収束しておらず、予断を許さない状況にあることや、福島第二原発に関しても、福島第一原発の事故を踏まえると、常に不測の事態に備える必要があることから、有事の際の初動体制及び住民避難の計画等の整備や、市、関係機関、住民等が冷静かつ円滑に対応できるよう備えるための訓練が必要となる。
よって、次の事項について要望する。
1 市町村が行う地域防災計画原子力災害対策編及び避難計画の改訂に係る所要の財政措置を講じること。
2 市町村が行う原子力防災訓練実施に係る所要の財政措置を講じること。
企業等が自ら削減することが困難な温室効果ガスについて、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量を購入すること等で埋め合わせるカーボンオフセット制度が注目されている。
よって、都市部の企業等がカーボンオフセット活動に取り組みやすい環境を作り出すための研究を進め、また、山村部で取り組む団体に対し、各種制度に対する申請手続きや検証への支援等に取り組むよう要望する。
有害鳥獣(ツキノワグマ、サル、イノシシ等)被害対策に係る
支援について |
近年、県内各地でクマの目撃情報、被害情報が増加し、特に、人への負傷事故や生活区域に出没したツキノワグマは、その習性から、出没を繰り返すことによる被害の拡大が心配される。
また、サル・イノシシ・カワウ等の有害鳥獣による農作物被害の区域も年々拡大し、農家の生産意欲を減退させ、日常生活においても不安を抱えているところである。
よって、地域住民の安全の確保と農作物被害や森林被害を軽減するため、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 ツキノワグマ、サル、イノシシ等の個体数調査等を実施し、個体数調査に向けた保護管理計画の早期再検討を行うこと。
2 昼間行動し人里を縄張りにする新世代のクマが増えていることや、以前は見られなかったイノシシの被害が急速に増えていることから、これら有害鳥獣の生態調査を早急に行い、効果的な対策に役立てること。
3 各種調査や被害実態を踏まえ、第11次鳥獣保護事業計画に記載された原発事故の影響への対応のうち、狩猟者育成及びイノシシ捕獲体制の整備を早急に取り組むこと。
4 捕獲時に早急かつ安全に対応できるよう、麻酔銃が使用できる者の配置、県と警察との協力体制の確立、及び専門的知識を有する人材の育成を図ること。
5 有害鳥獣捕獲の許可事務については、地域住民の安全安心のために今後とも迅速な事務処理を実施すること。
6 ツキノワグマの捕獲許可権限については、第11次鳥獣保護事業計画により希望する市町村へ緊急時のみに限定した銃器による捕獲許可の権限が移譲されたが、地域住民及び捕獲作業の安全を確保するため、箱わなによる捕獲許可の権限を希望する市町村に対し早期に移譲すること。
7 市町村が単独で実施している、有害鳥獣駆除に係る経費や住民を対象とした農作物被害対策補助等に係る費用に対する、県の支援制度を確立すること。
8 冬眠明けのクマから山菜採りなど春先の人的・作物被害を防ぐため、年度当初に対策活動が展開できるよう、鳥獣被害防止総合対策交付金の迅速な交付決定を行うこと。
9 森林環境税を活用した集落周辺の森林整備と緩衝帯設置等の支援策を拡充すること。
10 クマ剥ぎ被害の原因の究明と被害防止のための効果的な対策を実施すること。
11 雑木や雑草が繁茂した河川内は、クマにとって恰好の移動ルートや一時的生息場所となっているため、市街地への出没ルートに当たる河川雑木および雑草の計画的な伐採を実施すること。
12 猟友会員の減少は全県的に顕著であり、捕獲・駆除を行う人材の育成確保が急務であることから、今後の捕獲業務を担う人材の育成確保及び狩猟装置整備等のための支援等を充実すること。
13 群れで移動するサルなどは市町村境界を越えた広域的な被害が見られるため、県と市町村とが連携した効果的な被害防止施策や体制の構築を図ること。
14 福島県カワウ保護管理計画(第2期計画)における個体数調整の実施方法について、生息地に向けた銃猟は試験的に翁島コロニー(猪苗代町)に限られているが、翁島コロニーより推定被害額の多い山都コロニー(喜多方市)においても生息地に向けた銃猟を認めること。
合併処理浄化槽設置整備事業の予算確保並びに合併処理
浄化槽維持管理費に係る県費補助制度の創設について |
自治体においては、合併処理浄化槽設置整備事業を実施し、その設置普及に取り組んでいるところであるが、浄化槽法及び建築基準法の一部改正に伴い、浄化槽新設時における合併処理浄化槽の設置が義務づけられていることや、水環境の保全を図るため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えにも努めていく必要がある。
このような状況の中、平成21年度から新築住宅の合併処理浄化槽設置に対する県浄化槽整備事業費補助金の廃止や同補助金の削減など県費負担の改正等が行われ、自治体の負担が増加する事態となっている。
よって、合併処理浄化槽設置整備事業の促進と補助金の確保及び合併処理浄化槽使用者の負担軽減と適正維持管理の促進を図るため、県費補助制度を創設するよう要望する。
また、「集会施設」に係る浄化槽の設置補助について、国費においては昨年度より補助対象となったことから、県費においても同様の措置を講じるよう要望する。
原子力発電所事故により流出し、地表等に滞留している放射性物質は、除染することが最善・最適な解決策であり、国及び東京電力が全額費用を負担し、一刻も早く除染事業を実施することが急務である。 よって、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 除去土壌等の中間貯蔵施設への円滑な輸送に向けて広域自治体としての役割を果たすこと。
2 現場で保管され処分が待たれている廃棄物や除去土壌等については放射能濃度に関わらず、安全に管理することのできる中間貯蔵施設へ、ロードマップどおり平成27年1月から輸送すること。
3 仮置き場として設置可能な県有地の情報提供と整備を図ること。
4 放射性物質を含む全ての下水汚泥は放射能濃度に関わらず、適正に処理するため、減容化対策の施設整備と最終処分場を確保するとともに、それらに係る財政支援を講じること。
5 農業系汚染廃棄物処理事業補助金について、焼却施設等の施設完成後の運び込みが完了するまで事業を継続すること。
6 線量低減化活動支援事業や他の事業で公園、学校、保育所を除染し設置した仮置き場の事後モニタリングや管理費を交付金の対象とすること。
7 低線量地域(除染対象区域外)の側溝汚泥については、空間線量率に関わらず、その処理や仮置き場等にかかる経費について財政措置を講じること。
8 除染事業の実施主体である自治体の費用負担が発生することのないよう、除染対策事業交付金の原資の確保に万全を期すこと。
9 労務単価については、県内統一の単価になっており、同じ除染作業を行っていても、特殊勤務手当の支給は認められておらず、作業員の確保に苦慮していることから、実態を把握し、適正な単価設定をすること。
10 除染に伴う原形復旧措置に関する制限を緩和するとともに、除染方法に関する協議についても簡素化し、除染実施者である市町村が現場の状況に応じた除染方法を速やかにかつ柔軟に選択できるようにすること。
11 除染に伴う原形復旧措置については、実態に即した標準単価を設定するなど、全額を財政措置の対象とすること。
12 新たな除染手法・技術を検証し、より有効な手法は積極的に採用するとともに、自治体がすぐに採用できる体制を整備すること。
13 仮置き場における国有林など積極的に国有地を提供すること。
14 側溝土壌や道路などにおいて、除染後、再び汚染が確認された際は、堆積物の除去による低減効果が明らかであるため、同じ手法による除染であっても、フォローアップの除染を実施可能とし、その除染経費についても財政措置の対象とすること。
15 池沼、河川、山林等の除染について責任を持って対応すること。
除染作業は、迅速に実施することが最も効果的であるため、居住する生活空間についての放射線防護の観点での除染は、一通り終えたところについても、必ずしも市民の安心に結びついていない状況にある。
現在、行われている除染作業は、放射線防護の観点より、環境回復の側面が非常に強く、このままでは除染作業の終期が見通せないとともに、復興ビジョンに結びつかないため、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 環境回復での作業か、地域の課題解決に向けた事業かを選択し、放射線防護の観点からの除染を終息させるための制度を、財源措置とともに創設すること。
2 市民の安心に向けたリスクコミュニケーションの取組について、具体的な交付金メニューがないため、財源措置を伴う新たな制度を創設すること。
原子力損害賠償は、被災地に寄り添い、長期的な視点に立った対応が必要となる。
よって、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 原子力損害の賠償に関する法律第3条に基づく各被災自治体による損害賠償請求については、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針に基づき完全賠償とするよう東京電力に対し強く指導するとともに、早期解決に向けた積極的な措置を講じること。
2 被災者が公平に賠償を受けられるよう、文部科学省設置の原子力損害賠償紛争解決センターが行っている和解仲介等のこれまでの事例を基に、原子力損害賠償紛争審査会が定める指針に賠償の基準を明確に盛り込むこと。
3 原発事故により風評被害を受けた観光業者及び商工業者をはじめ、農産物の出荷制限や風評被害など全ての損害について、補償内容及び手続きを明確にするとともに、迅速かつ適正な賠償を行うよう、東京電力に対し強く指導すること。
4 市民や企業が自ら行った除染費用については、東京電力が全額賠償するよう強く指導すること。
| ふるさとふくしま帰還支援事業(広報誌送付事業)の継続について |
東日本大震災及びそれに伴う原子力発電所事故の影響により、今なお多くの市民が市外に避難している状況にある。
そのような中、行政情報を適切に発信して、市外避難者の帰還を促進するため、原発避難者特例法上の避難住民及び特定住所移転者に対し、県のふるさとふくしま帰還支援事業(広報誌送付事業)を活用し、市の広報紙や放射線に関する取組などの情報を送付している。
原発避難者特例法上、指定市町村及び指定都道府県は、特定住所移転者に対し、市町村及び県の情報を提供することが義務付けられている一方で、現在、県においては、来年度の事業継続が不透明な状況にある。
よって、平成27年度も、市及び県の情報を継続して避難者に提供し、市外避難者の帰還促進が図られるよう、ふるさとふくしま帰還支援事業(広報誌送付事業)の継続を要望する。
|
◆保健福祉部関係
医療保険制度の中核として重要な役割を担ってきた国民健康保険制度は、所得者や高齢者を多く抱えるなど構造的な問題を抱えており抜本的な改革が必要となっている。
また、東日本大震災、原子力災害の影響による国民健康保険税収入の減少や医療費が増加傾向にあることなどにより国保財政は危機的な状況に陥っている。
よって、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 療養給付費の国庫負担割合の引上げなど国保財政基盤の拡充・強化を図り、実効ある措置を講じること。
2 市町村国保事業に対する指導監督及び県調整交付金による財源調整機能を担う県においても財政措置を講じること。
3 市町村国保の都道府県化に向けては、県と市町村とで適切な役割分担がなされるよう、また、現場の混乱を招かないよう丁寧かつ十分に協議すること。
4 各種医療費助成制度等市町村単独事業の実施に伴う療養給付費負担金及び普通調整交付金の減額措置の廃止又は補填などの支援策を講じること。
5 特定健康診査に係る財政措置など十分な支援策を講じること。
また、特特定健康診査・特定保健指導の実施率等による後期高齢者医療支援金の加算・減算措置を撤廃すること。
6 特定健診・保健指導の義務化に係る保健師等の確保対策について十分な財政措置を講じること。
7 平成27年度に拡大される保険財政共同安定化事業の実施に当たり、医療費適正化や保健事業に取り組み、医療費を出来るだけ伸ばさないよう取り組んでいる市町村に対し、インセンティブを損なわないよう、県独自で財政措置を講じること。
また、東日本大震災の影響を考慮し現行の国民健康保険調整交付金要綱に定める「保険者の責めによらない特別事情に対する支援」の内、「その他特別な事情に対する支援」を平成27年度以降も継続すること。
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、障がい者などが地域の中で安心して生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助、日常的な金銭管理、書類等の預かりサービスを行うもので、県から補助金を受けた県社会福祉協議会が、市社会福祉協議会に委託し事業を実施しており、事業の財源は国が2分の1、県が2分の1とされている。
市社会福祉協議会では専門員を配置して事業を行うが、その人数は契約締結件数から配置基準により雇用しなければならず、基準を満たす人数の配置には、県及び国からの補助金は配置費用と大きく乖離しており、自主財源で補填し基準を満たし対応しているが、恒久的な自主財源の確保は困難である。
よって、高齢化が進行し年々利用者が増える中、市民が安心して事業を利用できるよう必要な予算を確保するよう要望する。
| 生活保護に至らない生活困窮者に対する生活支援の充実について |
近年の原油価格は、国の円安誘導策に加え、世界的な石油製品の需要の増加と相まって高値で推移しており、結果として灯油価格や電気代等にも影響を及ぼし、とりわけ生活困窮者の家計に対しては大きな影響を及ぼしている状況にある。
灯油代については、国県の財政支援に基づく福祉灯油緊急支援事業を実施した平成19年度当時と比べ18リットルあたり200円以上も高騰しており、積雪寒冷地においては、電気代等も合わせると、冬期間の光熱費支出額が大幅に増加することとなっている。
積雪寒冷地に暮らす、生活保護に至らない生活困窮者に対するセーフティネット関連施策として国・県の財政支援制度として制度化されることにより、当該生活困窮者に係る国県の定義が明確化されるとともに、当該財政支援を踏まえつつ、各市町村はそれぞれの判断に基づき事業に取り組みやすい環境の整備が期待される。
よって、積雪寒冷地に暮らす、生活保護に至らない生活困窮者に対し、冬期間における暖房経費の増嵩に係る支援制度を構築するよう要望する。
| 放課後児童クラブ整備補助金の財源確保と拡充について |
児童福祉法の改正に伴い、平成27年4月から放課後児童健全育成事業の対象年齢が拡大されることに伴い、早急に受け皿となる施設を整備する必要があり、財政支援が不可欠である。
よって、補助要望すべてに応えられるだけの財源を確保するとともに、補助基準額を増額するよう要望する。
また、リースによる施設整備についても補助対象とするなど柔軟な対応を講じるよう要望する。
東日本大震災や原子力発電所事故の影響による福祉・介護職員の避難により、深刻な職員不足の状況が続いており、その育成・確保は喫緊の課題である。
よって、次の事項について要望する。
1 県として介護職員を直接確保し、介護施設に配置するための事業の創設や、全国から介護職員の就業を促進するための制度(住宅確保も含む)を構築すること。
2 福祉・介護人材育成・確保支援事業補助金について
(1) 平成26年度から新規採用職員住まい支援事業及び就労支援金支給事業の補助対象者の条件が、「フルタイムの非正規雇用」まで拡大されたところであるが、事業所によっては、介護職員に限らず理学療法士や看護師、介護支援専門員等も必要な場合があることから、全ての職種に対象を拡大すること。
(2) 新規採用職員中堅介護職員就労支援事業は、新たに採用する職員への給与の加算分に対する補助であるが、事業所においては従来の職員との給与のバランス上、新規職員に限った加算は実施困難であることから、職員の定着を図るためにも、施設職員全体への加算について検討すること。
3 「福島避難解除等区域生活環境整備事業」の対象区域を見直すなど、施策や財政支援の措置を総合的・効果的に講じること。
4 ケアマネージャーや介護職員の養成事業について充実を図るとともに、人材を求めている事業所に対する紹介事業など新たな施策を講じること。
地域包括ケアシステムの構築に向けた介護人材等の
育成・確保等の推進について |
医療・介護総合確保促進法には、都道府県は、医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画を作成し、医療に関する事業のほか、公的介護施設等の整備に関する事業、介護従事者の確保に関する事業等を定めることとされ、これら介護の総合的な確保のための事業は、平成27年度から実施するとの方針が、すでに国から示されている。
介護従事者の確保及び勤務環境の改善のための事業等は、地域における介護を総合的に確保するために、重要な事業である。とりわけ、地域包括ケアシステムの構築、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業等)推進体制の構築、運営にあたる多様なサービス提供主体等を支えるコーディネーター育成、介護従事者の育成確保等を、広域的に推進する必要がある。
よって、次の事項について要望する。
1 都道府県計画策定にあたっては、市町村等の実情を充分に勘案して作成するとともに、コーディネーター、介護従事者の育成確保等を広域的に推進するために必要な予算を確保すること。
2 都道府県事業の実施に充てる基金の造成に当たって、必要な財源を確保すること。
震災後3年以上が経過している現在においても、今なお仮設住宅での生活を強いられている高齢者が数多くいることから、これらの者に対する相談、生活支援、見守り等のケアが必要となっている。
また、仮設住宅の設置期限については、平成28年3月まで延長されたところであり、仮設住宅居住高齢者の見守りや生活支援を継続して実施していく必要がある。
よって、平成27年度においても、地域支え合い体制づくり助成事業(仮設住宅等被災高齢者等生活支援事業分)を継続して実施するよう要望する。
介護保険制度について、要介護認定者やサービス利用者の増加とともに、介護保険給付費や介護保険料は増加の一途をたどっており、全国的にも大きな課題となっている。
介護保険制度は、高齢者福祉を支える大きな柱であり、今後ますます増加が見込まれる介護ニーズに対応するためには、当該制度を維持していくことが必要不可欠である。
よって、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 介護保険制度の安定的な運営のため、介護給付・予防給付の費用負担について、公費負担の割合を大きくするよう見直すとともに、国と地方の負担割合を見直し、国の負担割合を大きくすること。
2 事業計画の見直し毎に介護保険料は増額の一途を辿っており、被保険者に対する負担は大きいため、保険料水準の抑制策を講じること。
3 想定を上回る介護保険給付の負担増に対し、被災自治体の実情を勘案して、現在交付している調整交付金の優先的な配分や、新たに臨時交付金を創設するなどの財政措置を講じること。
ひとり親家庭に対する支援の一つである医療費助成制度は、現在、ほとんどの市町村で、受診時に医療費を一旦支払い、その後に助成を行う償還払いの方式をとっている。
そのため、受診した医療費の支払いができない、医療費の支払いを不安に受診を控えているなどの相談が寄せられている。
現行のひとり親家庭医療費助成事業補助制度は、支払った医療費から1世帯同一受診月あたり1,000円を除いた額が助成対象となっているため、事務が繁雑化するだけでなく、医療機関等にも大きな負担増となっている。
よって、ひとり親家庭の自立を促進し、安心して子育てができる環境整備に寄与するためにも、ひとり親家庭医療費助成事業補助金の1登録世帯同一受診月1,000円控除を廃止するよう要望する。
| 18歳以下の県民医療費無料化に係る財政支援について |
平成24年10月から18歳以下の県民の医療費が無料化されたが、小学校1年生から3年生までは各市町村が独自に助成を実施していることから、県補助対象者は小学校4年生から18歳までとなっている。また、就学前の子どもについては、現行の乳幼児医療費助成事業補助金制度で対応している。
このように子どもの年齢によって取扱いや要件、財源が異なることは事務管理が繁雑になるうえ、複雑化した制度は住民の混乱を招くことから、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 現行の乳幼児医療費助成事業補助金交付要綱を廃止し、制度の一本化を図り、小学校1年生から3年生も含めた、0歳から18歳までの医療費全額の補助金を交付されるとともに、現行制度において補助対象外とされている審査支払手数料についても補助対象とすること。
2 医療費の自己負担にかかる部分の助成ばかりでなく、国民健康保険制度における国・県支出金の減額措置分及び医療給付の波及増分についても助成すること。
3 当該制度が持続して運用できるよう継続的な財源確保を図ること。
幼稚園及び保育所保育料の無償化は、すべての子どもに対して質の高い幼児教育及び保育を受ける機会を確保するための環境整備として有意義な政策であるとともに、原子力災害により県外へ避難した避難者の帰還を促す政策でもある。
よって、次の事項について要望する。
1 保護者負担を軽減するため、幼稚園及び保育所に係る保育料の無償化に必要な予算を確保すること。
2 避難指示区域内の子どもが市立保育所へ入所する場合、自治体独自に行っている保育料の減免による減収に対して財政支援すること。
保育所を利用している子どもの安心・安全を確保する観点から、保育所の建物の耐震化を図ることは重要であり、東日本大震災級の地震の発生も今後も懸念されることから早急に耐震化が必要な状況にある。
しかしながら、現在、公立保育所の耐震化に対する国、県の補助制度がなく、耐震化を推進するうえで、財源確保は急務となっている。
よって、公立保育所の耐震化を早期に実施するために補助制度を創設するよう要望する。
| 保育所等給食検査体制整備事業補助金の継続及び拡充について |
子どものより一層の安全・安心を確保するため、安心こども基金を活用した保育所等給食検査体制整備事業補助金が平成24年度に制定されたところである。
この制度の放射能検査機器購入の補助、検査用試料代の補助等により、保育所等給食の検査体制を整備し、維持しているが、給食に対する不安を払拭するためには長期間を要する。
よって、来年度以降も保育所等給食検査体制整備事業補助金を継続するとともに、同補助金を拡充し、検査体制維持のための消耗品等の費用についても補助対象とするよう要望する。
屋内運動施設及び屋内遊び場の整備及び管理・運営に係る
財政措置について |
子どもの健全な発育には、発達段階に応じて必要な遊びや運動を必要な時期に行うことが不可欠であり、既存の屋内型運動施設だけの対応では全ての子どもたちに運動する機会を提供することは不十分であることから、新たな屋内型運動施設の整備が必要である。
よって、次の事項について要望する。
1 発達段階に応じた運動プログラムを確立すること。
2 屋内運動施設や屋内遊び場の整備に係る助成制度を拡大すること。
3 施設の管理・運営に要する経費、スタッフの研修を含む新たな人材の育成に要する経費について財政措置を講じること。
4 屋内遊び場確保事業を継続すること。
| 子ども・子育て支援新制度移行に係る財政支援について |
国が進める子ども・子育て新制度については、少子化の進行や共働き世帯の増加等の子育て家庭をめぐる環境変化に対応するため、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の施設型給付及び小規模保育事業等に対する地域型保育給付を創設し、平成27年度から子ども・子育て新制度に移行する予定となっているが、1号認定(3歳以上の幼稚園利用の児童)と小規模保育事業等を利用する3号認定(2歳以下の小規模保育事業にかかる児童)の児童については、新たに市町村の負担を求めるものである。
さらに、6月に示された利用者負担額の上限は、利用者の所得階層により金額設定がされているものの、全国平均の料金設定になっており、大多数の利用者は現状の料金設定より負担増になる。
よって、地域の実情を勘案した料金設定の見直し、または負担軽減措置などの対策を講じるよう要望する。
また、現在示されている内容で事業が開始される場合は、負担軽減の対策に多額の財源が必要となるため、新制度移行に伴う新たな費用負担に対する財源措置を講じるよう要望する。
平成24年4月の障害者自立支援法等の一部改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する場合、全ての利用者について、平成27年3月までサービス等利用計画(障害者支援利用計画)を作成し、提出が求められることとなった。
しかしながら、サービス等利用計画を作成する「相談支援専門員」は、一定年数以上の実務経験に加え、「相談支援従事者養成研修」の受講を条件としながら研修受講機会が極めて少ないことなどから、全国的にその数が不足している状況にある。
よって、相談支援従事者養成研修(初任者研修)について、本県の広域性を考慮し、複数回また複数箇所で開催する等の受講機会の拡大を図り、相談支援専門員を必要な人数確保することに加えて、現任者の質の確保を図るために研修会を開催するほか、指定特定相談支援事業者の増加や、事業者における相談支援の体制の充実に向けた障害福祉サービス(計画相談支援)の報酬体系の見直しについて特段の措置を講じるよう要望する。
地域生活支援事業は、障がい者及び障がい児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、国で定めた必須事業と、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態をとった市町村事業とで効果的・効率的に実施しているところであるが、地域生活支援事業に対する県の補助率は、要綱により費用の4分の1を補助することができるとされているが、実際には予算の範囲内での補助であり、県補助額は規定に及ばない額となっている。
法に基づく事業を実施するにあたり、不安定な補助金では適正な事業実施に支障が生じるとともに、市町村間でも格差が生まれる可能性がある。
よって、各市町村が確実に事業を実施し、障がい者への支援を円滑かつ効果的に図られるよう補助金制度を見直すなど、必要な予算を確保するよう要望する。
社会福祉施設等施設整備費については、障がい者の地域移行支援の核となる、グループホーム等の地域で暮らす「住まいの場」、生活介護、自立訓練、就労移行支援等の「日中活動の場」、児童発達支援センターの地域支援機能の強化や障がい児入所施設の小規模グループによる療育など、発達障がいを含む障がい児支援の充実を図るための整備を対象に補助するものであるが、近年、施設利用者の増加により、新たな施設の整備が急務となっている。
よって、真に緊急性・必要性の高い施設の早期整備を図るため、必要な予算を確保するよう要望する。
がん検診(胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん、大腸がん)に係る費用については、平成10年度から国・県負担金(補助金)を廃止し、地方交付税をもって措置(一般財源化)されている。
平成20年度から措置された健康増進法、がん対策基本法に基づくがんの早期発見等のためのがん検診及びがん予防事業(健康教育、健康相談)などは、住民の健康保持の観点からも保健事業の根幹をなすものであり、重要な事業である。
よって、健康診査及び健康教育の充実強化を図る観点から、これら事業の財源の確保・拡充を図り、地方負担の軽減について要望する。
また、国が配布している乳がん・子宮頸がん・大腸がん検診の無料クーポン券について今後も実施されるよう特段の措置を講じるとともに、胃がん・肺がん検診などの対象とされていないがん検診のクーポンを配布するよう要望する。
| ホールボディカウンタ導入費用等に係る財政支援について |
原子力発電所事故から3年以上を経過した現在においても、住民の放射線による健康被害に対する不安は未だ払拭されていない状況にありその解消対策は急務である。
自治体においては、住民の放射線に対する不安を解消し、長期にわたる健康管理のため、独自にホールボディカウンタを導入し、内部被ばく検査を実施しているところである。
よって、これら整備に要した経費及び長期的な健康管理に要する全ての費用に係る財政措置を講じるよう要望する。
原子力発電所事故に伴う放射線による健康被害への不安に対し、引き続き住民に対するきめ細かな対策が求められていることから、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 内部被ばく検査について、県が実施主体となった検査体制を増強するための経費及び県内市町村が実施する検査を更に推進していくための経費を確保すること。
また、測定業務に関する放射線技師等の人件費及び運営に要する全ての費用に係る財政支援制度を創設すること。
2 住民全員を対象とした外部・内部被ばく線量調査を実施し定期的な健診・医療の受診及び相談体制を確立すること。
また、特定健診に追加する検査項目に係る経費を確保すること。
3 県外避難者に対する被ばく検査環境の整備を図ること。
4 放射線対策健康管理を推進するため健診(検査)データベース構築後の運用・充実にかかる経費を確保すること。
5 国が定める避難基準値(20mSv/年)以下の地域であっても、住民が原子力発電所事故の被災者であることを公式に認め、住民の長期健康管理(最低30年間)及び疾病対策に全責任を負うこと。
6 長期間にわたる健康管理等を安全・確実に実施するため、県内に複数の専門医療施設を設置すること。
7 県民健康調査「甲状腺検査」の結果行われた通常診療等について19歳以上の県民については、県民健康調査の枠組みと捉えて無料で実施すること。
また、「健康診査」については、避難区域や避難区域外に関わらず、同一の検査項目による検診を行うこと。
8 県民健康調査の結果に関して、追跡調査を実施するなど疫学調査をしっかり行い、責任を持って人体に対する放射線の影響を明らかにするとともに、その健康に及ぼす影響に関する正しい知識を啓発すること。
9 特定健康診査及びがん検診などの市民検診の枠組みをなくし、年齢にかかわらず全ての住民に速やかに健康診断を実施できるよう特別の法制化、検診実施体制の整備・支援、市町村・各保険者の財政負担の軽減を図ること。
| 安定ヨウ素剤の配備と服用にかかる適正な対応について |
放射性ヨウ素による被ばくを阻止または低減するために、吸入する直前の安定ヨウ素剤の服用が効果的であると言われており、原発から数十キロ圏の自治体には安定ヨウ素剤が配備・備蓄されていたが、空前の大事故による混乱の中で安定ヨウ素剤の正しい服用が行われなかった。
安定ヨウ素剤の配布については、平成25年9月施行の原子力災害対策指針で配布体制が示されたところであり、緊急時に迅速な配布が困難であれば市町村の判断で事前配布することができることとなっている。
よって、県として全県民に事前配布するため安定ヨウ素剤の配備を行うよう要望する。
なお、服用指示にかかる情報伝達方法の再整備や安定ヨウ素剤の効果、副作用、服用時期等の情報周知及び子供用ヨウ素剤の開発について特段の措置を講じるよう要望する。
地震、津波、原子力発電所事故に伴う放射能の問題及び風評被害は、かつて経験したことのないものであり、これらの事態は、地域医療の要である医師の招へいにあたって新たな障害となっている。
また、放射能問題により避難等指示区域以外の地域でも、多くの医療従事者が県外に流出しており、これら医療従事者の確保が急務となっていることから、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 地域医療に従事する医師を確保するため、大学医学部の募集定員における地域枠の拡大や、地域医療現場への一定期間従事を義務化するなど実効性のある措置を講じること。
2 地域医療の復興・再生が早急かつ円滑に進むように、地域の医療環境の変化に応じた二次医療圏における基準病床数を見直すこと。
3 地域医療再生基金の弾力的な運用を行うとともに建築資材や労務費の高騰による事業費増を踏まえ更なる基金の積み増しをすること。
4 救急医療機関に対する財政支援及び救急医療に対応できる専門的な医師を充足・配置すること。
5 地元の医師の確保及び開業医を存続させるために、新規開院時等の財政支援制度を創設すること。
6 公的病院への医師派遣事業を継続・拡大すること。
7 派遣医師を増員すること。
8 コメディカルの人材確保・定着のため、看護師確保・定着のため県が創設した看護職員ふるさと就職促進等補助金制度と同様の補助制度を創設すること。
9 看護師確保に向け、地域に定着する看護師を直接確保し、医療機関に配置するための事業を創設すること。
また、市で独自に実施している看護師修学資金貸与制度に対し、財政支援を講じること。
10 平成26年度に廃止された地域医療再生臨時特例基金事業補助金交付要綱の医師事務作業補助者充実事業の復活及び対象範囲の拡充と必要な財政措置を講じること。
医療体制の充実を図るため、在宅当番医制事業を実施してきたところであるが、国においては当該補助制度の見直しを行い、平成16年度に一般財源化をし、地方交付税により措置している。
市町村が行う事業は住民と直結した業務がその大半であり、とりわけ在宅当番医制事業は、初期救急医療の根幹をなす事業のため、事業が廃止となった場合、第二次及び第三次救急医療体制にも影響が生じ、地域における救急医療体制の確立が困難な状況となり、住民の生命や生活に多大な影響を与える結果となる。
よって、事業実施における財源の確保が確実な方法として国の制度改正に関わらず県においては、在宅当番医制事業補助金の一般財源化について見直しについて特段の措置を講じるとともに、以前行っていた補助制度を復活するよう要望する。
| 電子カルテシステム整備にかかる補助金の拡充について |
地震、津波、原子力発電所事故に伴う放射能の問題及び風評被害により、相双地域の医療供給体制は、医師、看護師をはじめ医療従事者の避難等により不足している状況にあり、地域医療崩壊の危機に瀕している。
こうした医療資源の不足を補完するには病院の機能分化を推進し、周囲の医療機関との連携を強化することで効率的に医療を提供する必要がある。
よって、現在の補助制度では、被災地域である相双地域の各医療機関が電子カルテシステムを整備し、医療連携を推進するには自己財源3分の1の負担が大きく、ネットワークの構築に支障が生じることから、地域医療復興事業補助金交付要綱の「医療情報連携基盤整備事業」における医療情報連携の基盤整備に要する補助金の増額及び補助率を引き上げるよう要望する。
県立リハビリテーション飯坂温泉病院の廃止に伴う新たな
保健福祉等施設整備に対する予算措置について |
平成19年3月末をもって廃止された県立リハビリテーション飯坂温泉病院の跡地については、医療関係、地域代表、保健福祉関係者及び知識経験者からなる「福島市保健福祉等施設整備検討委員会」にて取りまとめられた施設整備の基本方針により、新たな保健福祉等の拠点としての施設整備が求められており、県立リハビリテーション飯坂温泉病院跡地の無償譲渡、拠点施設整備に係る財政的支援及び同病院に併設されている特別養護老人ホーム「福島県飯坂ホーム」の飯坂地区内への移転建築等について合意しているところである。
よって、新たな保健福祉等施設整備に対する予算措置を速やかに行うよう要望する。
| 脳卒中センター整備事業に係る建設コスト高騰への支援について |
平成28年4月開院を目指し、南相馬市立総合病院敷地内に100床規模の脳卒中センターの整備を進めているが、東日本大震災による被災地域である当地域は、復興事業の増加により、建築工事に係る資材費や労務費等が高騰し続けている状況である。
そのため、被災地域における公共工事の入札においては、応札がない場合や予定価格を上回る応札による入札不調も散見される。
今後、さらなる資材費や労務費等の高騰が続き、脳卒中センターとして必要な機能を備えた施設を整備するためには、建設費の見直しや工事発注の際の物価スライド条項の適用等が必要な状況になっている。
よって、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 脳卒中センター整備事業に係る資材費や労務費等の高騰に対応した補助金の増額を行うこと。
2 地域医療再生基金への更なる交付金を増額するとともに、平成28年度以降も同様の事業を継続すること。
近年、国による予防接種制度の抜本的な見直しにより、感染症予防費に要する経費は急激かつ多額の財政負担が生じている状況にある。
予防接種の制度改革により、感染症予防対策が充実することは望ましく、市民にとっても大変有意義な施策である反面、財源に関する課題が解消されない状況となっている。
よって、各市町村の財政状況によって県民の健康管理状況に格差が出ないよう予防接種に対する財政支援を要望する。
自治体においては、住民の安全を守るため飲料水、食品等の放射能計測を行い、放射性物質の量を把握し、安全性の確認、風評被害の払しょくに努めている。
よって、水道水の安全確保のため、放射性物質にかかる水質検査を継続して定期的に実施するとともに、摂取制限等緊急時の飲料水確保のための支援体制を早急に確立するよう要望する。
水道施設の再構築事業並びに水道施設の安全強化のための
施設整備に対する財政支援制度の確立について |
我が国の水道事業は、水道普及が進んだ昭和30年代に建設された施設が多く、これらの水道施設の再構築事業が大きな問題となっており、加えて、最近の水環境変化から生じる水質問題や、鉛製給水管の使用による水道水の汚染問題に対応し、安全でおいしい水を求める住民のニーズに応えるためにも、高水準の施設に再構築しなければならない状況にある。
しかしながら、水道施設の再構築事業は莫大な事業費を要し、料金収入の増加にはつながらないことから、水道事業経営に極めて大きな影響が出ることは必至である。
また、阪神淡路大震災や東日本大震災等、史上空前の大災害による経験から、震災等の大規模災害への対応や米国の同時多発テロを契機としたテロ対策強化への要請に応えるため、水道施設の耐震性能強化及び安全強化に関する事業を推進する必要がある。
よって、浄水場や基幹管路等の水道施設を近代化する再構築事業や鉛製給水管布設替えに対する財政支援体制及び水道施設の安全強化のための施設整備に対する支援体制の確立を早急に図るよう要望する。
|
◆商工労働部関係
東日本大震災や原子力発電所事故の影響により地域内の様々な業種での事業活動が大きな打撃を受け、多くの事業所の操業再開が遅延、見通しがつかない状況にあり、多数の失業者が発生するなど雇用情勢が非常に厳しい状況にあることから、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 緊急雇用創出基金事業を継続して実施するとともに、厳しい雇用状況にある市町村に対し、地域経済の活性化と雇用の安定化を図るための予算配分を行うこと。
2 絆づくり応援事業について、平成27年度以降も継続して実施するとともに、絆支援員の増員など内容の充実を図り被災自治体に対する支援を強化すること。
3 産業競争力強化法に基づき市町村が実施する創業促進支援事業に対する支援制度を創設すること。
4 各自治体の雇用情勢を把握し地域の実情に即した実効性のある就業支援制度及び雇用支援制度の創設を図ること。
5 避難指示区域などにあった事業所が事業を継続・再開するために新規の雇用を行う場合について、これまでの被災者雇用開発助成金などの助成制度に関して、対象事業者・対象労働者の要件の緩和や、支給額の増額などの支援内容の充実、支援期間の延長など、被災企業に対する支援や被災者等の雇用対策を特に強化すること。
6 被災地域における今後の対策においては、短期的な視点での対応を確保しつつ、中・長期的な視点からは、税制面での更なる特例措置を設けることや、市外から人材を呼び込めるよう、アパート等の建設に係る費用の助成や、土地の取得に伴う規制の緩和を行うなど、新たな施策を講じること。
7 求人業種と求職者のミスマッチを低減させるためにも、「ふくしま就職応援センター事業」等の更なる効果的運用と実効性ある支援策を講じるとともに、広く情報発信を行い事業周知を図ること。
8 職業訓練を実施し、企業が必要とする人材を育成すること。
東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により地域内の様々な事業活動が大打撃を受け、多くの事業所の操業再開が遅延するなど、非常に厳しい状況にある。
また、風評被害もあいまって、商工業、観光サービス業は多大な影響を被っている。
このため、国・県においては中小・零細企業等への支援策として新たな補助制度の創設、震災に伴う特別資金での支援など各般の施策を講じているが、事業再開を躊躇している事業者が多くあることから、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 ふくしま復興特別資金制度を平成27年度以降も継続すること。
2 既存の中小小売業者の育成・確保を軸とした買い物支援や地域商業の活性化支援、大型空き店舗の解消及び再開発事業に係る財政措置、税制や融資・助成などを含めた中小企業への総合的な支援策などの活性化策を図ること。
また、企業誘致や増設等に係る整備・開発を速やかに進めるため、土地利用に関する規制緩和及び財政措置を講じること。
3 補助事業を含めた経営支援、技術力強化支援を図るための予算措置を講じること。
4 被災事業者の早期の経営再生を確かなものとするため中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業や、中小企業等復旧・復興支援事業の継続及び補助率や補助限度額の拡充を図ること。
5 既存の中小小売業者の育成・確保を軸とした買い物支援や地域商業の活性化支援、大型空き店舗の解消及び再開発事業に係る財政措置、税制や融資・助成などを含めた中小企業への総合的な支援策などの活性化策を図ること。
また、企業誘致や増設等に係る整備・開発を速やかに進めるため、土地利用に関する規制緩和及び財政措置を講じること。
6 被災地域における先進的な取組を行っている企業等に対し、支援策を講じること。
| 中心市街地活性化に対する各種事業への財政支援について |
中心市街地については、車社会の伸展、巨大商業施設や郊外型ショッピングセンターの出店で消費者が郊外へ流出しており、中心市街地は空洞化の一途をたどっている状況である。
このため、各自治体においてはそれぞれの特性を活かしながら、中心市街地への誘客促進を図るため、ソフト事業を中心とした各種事業を市民と行政が一体となって取り組んでいるところである。
よって、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 商店街での空き店舗対策、創業支援対策、賑わいを創出するイベント等に対する補助制度の拡充や補助率等を嵩上げすること。
2 再開発事業に係る財政措置を講じること。
3 国の関係省庁と緊密な連携を図り、市町村の実情に即した効果的かつ実効性ある支援策を講じること。
東日本大震災及び原子力災害から商工業の復興を図る上では、地域の実情に精通した商工会議所や商工会による経営指導が必要である。
よって、地区商工業の経営指導に必要な機能を備えた商工会館の設置・改修に要する支援のための予算措置を講じるよう要望する。
東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により、旧警戒区域内の事業所においては休業や廃業、事業所移転を余儀なくされ、旧警戒区域外の事業所においても、原子力災害による一時的な生産停止による受注の減少や風評被害、労働力不足などによる事業活動の縮小など、極めて深刻な状況が続いており、企業立地補助金の制度なくしては、風評被害を受けた地域に企業を誘致することは極めて困難である。
よって、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 ふくしま産業復興企業立地補助金を継続するとともに、対象業種の拡大や補助金下限額を緩和するなど要件緩和を図ること。
なお、制度の運用に当たっては、新規地元雇用者を確保する期限を延長すること。
2 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金については、被災地域の実情を踏まえた継続的な対応を図ること。
ふくしま産業復興投資促進特区及び福島復興再生特別措置法における
税の優遇措置の拡充について |
東日本大震災及び原子力災害からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある再生に資することを目的としたふくしま産業復興投資促進特区については、工業団地等の復興産業集積区域において集積業種の事業者が復興に寄与する事業を行う場合、市町村の指定等を受けることにより税制の特例が適用され、また、福島復興再生特別措置法については、避難解除区域等において事業用設備等への投資や雇用を行った際に税制の特例が適用され、企業の復興をはじめ強化が図られる大きな推進力となっている。
しかしながら、いずれの税の優遇措置についても、対象業種や対象区域が限定的なことから多くの事業者が特例を適用することができない状態となっている。
よって、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 ふくしま産業投資促進特区における税の優遇措置について、平成28年3月までとなっている優遇措置期間を延長するとともに、対象業種及び対象区域を拡充すること。
2 福島復興再生特別措置法における税の優遇措置について、避難解除区域等以外の地域で事業を開始する事業者に対しても適用されるよう、対象区域を拡大すること。
原子力災害により被災地における地域経済は、風評被害も含めたあらゆる分野において厳しい状況が続いている。
このような中、地域経済の活性化と安定した雇用の創出を図るため、新たな企業誘致を推進するとともに、受け皿となる拠点の整備が急務であることから、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 工業団地整備に係る新たな補助金を創設すること。
2 工業団地の整備・開発を速やかに進めるため、土地利用に関する規制緩和及び手続きの簡素化を図ること。
3 県所有の未利用地については、県営工業団地としての利活用を図ること。
浮体式洋上風力発電実証実験への積極的な支援と
関連産業の集積に向けた調査研究について |
東日本大震災に加え、福島第一原子力発電所の事故及びそれに伴う風評により、地域経済が大きな被害を受けており、その再生と復興が急務となっている。
また、警戒区域等の周辺自治体では、多くの避難者を受け入れており、新たな雇用の創出も喫緊の課題となっている。
こうした中、本県沖では、国による浮体式洋上風力発電の実証実験が進められていることから、この実証実験を契機として、地域経済の再生と復興、さらには新たな雇用の創出が図られるよう、事業化の実現及び関連産業の集積に向けた積極的な取組みが必要であることから、次の事項について要望する。
1 風力発電関連産業の集積・活動拠点としての小名浜港の利活用及び機能強化を図ること。
2 風力発電関連産業の集積の具現化や既存産業との関わり等に関する各種調査研究を実施すること。
3 風力発電の研究、試験を行う拠点施設を誘致すること。
4 事業化を見据えた海域利用に係るコンセンサスの形成及び漁業者との共存に向けた取組を推進すること。
地域の工業生産を回復させ、成長軌道に誘導するためには、福島第一原発の廃炉作業や除染作業、医療・福祉分野に対応するロボット関連産業に進出し、部品製造産業の復興施策を実施することが必要である。
県においては、災害対応ロボットの開発を通して新たな産業集積を図り、東日本大震災からの復興を促進する復興施策として、平成26年度に「災害対応ロボット産業集積支援事業」が創出されたところである。
よって、当該支援事業の補助期間が単年度(平成26年度)となっているが、研究開発にはある程度の期間を要することから、平成27年度以降も研究開発が継続できるよう支援事業の延長及び予算を確保するよう要望する。
公益財団法人ふくしま科学振興協会に対する
補助金の確保について |
ふくしま森の科学体験センターは、科学技術の振興を図るとともに、地域特性を活かした科学教育の水準の向上と生涯学習の振興に寄与することを目的として、公益財団法人ふくしま科学振興協会が事業の推進及び管理運営に当たっており、次世代を担う青少年の教育施設として利活用が図られているが、補助金の縮減により財政運営上厳しい状況にある。
よって、同センターの運営が図られるよう、同協会に対する財政支援を講じるよう要望する。
東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により一時はサテライトでの実施となっていたが、再開を機に、震災後の地域産業復興に向け、地域の産業復興ニーズに即した高度な職業能力を持つ人材並びに企業立地の進展に応える人材の育成を更に進展させる必要がある。
よって、普通課程の全学科を専門課程に格上げし、同校を県内の職業能力開発施設の拠点校と位置付けした上で、職業能力開発促進法に基づく「職業能力開発大学校」に昇格させるよう要望する。
原子力発電所事故により本県のイメージが低下し、定住人口や交流人口が減少傾向にあり、観光産業等に大きな打撃を受けている。
よって、福島県の現状を伝え、福島県が安心であることを周知するとともに、次の事項について特段の措置を講じるよう要望する。
1 多くの方々に現地に足を運んでもらい安全性を実感していただくとともに、それらの様子がマスコミ等で報道されることが最も効果的であることから、国際的・全国的な会議やイベント等の誘致に積極的に取り組むこと。
2 ふくしまデスティネーションキャンペーンによる観光誘客を図るため、県一丸となった取組を行うとともに、地域の取組に対する支援を行うこと。
3 外国人観光客の入り込みが依然として厳しい状況にあり、インバウンドの充実に向け、福島空港の早期の海外路線の復活と本県への外国人誘客に向けた対策の充実を行うこと。
4 将来のリピーターとなり得る教育旅行の復活について、県が先導的役割を担い、県外の教育委員会や学校などの教育機関、旅行代理店など関係機関に対して教育旅行の復活や誘致をすること。
|
◆農林水産部関係
県においては、農地の放射性物質除去・影響軽減対策技術の確立に向けた各種試験が実施されており可能な技術から実施する方針となっている。
放射性物質の吸収抑制については、福島県営農再開支援事業を活用し、定額補助(10分の10以内)によりカリ肥料等放射性物質吸収抑制資材の散布に係る費用を支援しているが、予算額が限定されており、希望する全ての農地を対象とすることができない恐れがあることから、次の事項について要望する。
1 農地の放射性物質除去・影響軽減対策を平成27年の作付け前に実施できるよう、早期に普及体制を確立するとともに財政措置を講じること。
2 全ての農地を支援対象とするため、十分な予算を確保すること。
3 大豆の放射性物質吸収抑制対策については、カリ肥料のみが対象とされているが、大豆についてはカリ肥料の施用量が多いと大豆のマグネシウム吸収を阻害する場合があることから、マグネシウムを含む肥料である苦土石灰に係る経費を財政措置の対象にすること。
平成24年度から食品の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに厳密化されたことに伴い、生産段階におけるきめ細やかなモニタリングによる安全性の確認と風評被害の払拭が最重要課題となっている。
よって、次の事項について要望する。
1 市町村が要望する県産農林畜水産物のモニタリング体制の充実を図るとともに、必要な財政措置を講じること。
2 米の全量全袋検査に係る検査機器の導入費については、検査機器台数に不足が生じ、円滑な検査が実施できなかった地域協議会に対しても、継続して補助対象とすること。
また、既に導入済みの検査機器については、保守点検料全額を補助対象とすること。
3 漁協が実施する水産物の検査について、検査に係る機器や人員の配備など、検査体制の整備に対して状況に応じた支援をすること。
4 自治体独自の自主検査についても、人件費や物件費等の財源を確保すること。
農産物の販売が厳しい状況にある中、首都圏を中心に本県の農産物等の販売促進キャンペーンへの参加や独自に特産品・観光のPRを実施してきたところである。
県産農産物等に対する風評被害を払しょくするためには、各自治体のみならず、民間事業者も一緒になって取り組む姿勢が重要であり、官民一体となった復興対策が非常に有効であることから、次の事項について要望する。
1 国内外への正確な情報提供や県内産品の販路拡大などの風評被害対策事業の強化及び各種PR販売事業に対し、平成27年度においても、財政措置を講じること。
2 生産者団体や任意団体等が自主的に行う風評被害払拭に向けた販売促進事業等に対して支援措置を講じること。
3 ふくしまの恵みPR支援事業について、現在の対象事業・配分方法を継続し、新たに市町村や地域別で取り組むなど、スケールメリットを生かしたイベントを開催実施すること。
人・農地プランに位置づけられた中心経営体が、利用権設定により農地を集積した場合に、旧担い手への農地集積推進事業において受け手側に交付金が交付されていたが、農業経営基盤強化法の改正により、農地中間管理機構の創設に併せ、この事業が見直しとなり、耕作者集積協力金が創設され、出し手側のみに助成が行われることとなった。
よって、東日本大震災及び原発事故に伴う放射性物質の拡散等により、営農の再開が進まない状況にあることから、今後、営農の再開を進めるために、受け手に対する集積助成金を交付するとともに、経営規模拡大に関する担い手への支援を行う農業経営規模拡大助成金(仮称)を創設するよう要望する。
| 卸売市場施設整備に係る県独自の補助制度の創設について |
東日本大震災及び原子力発電所事故から3年が経過したが、いまだに産地市場である各部の取引数量及び金額ともに深刻な状況が続いており、卸売市場の整備にあたっては、環境負荷の低減や再生可能エネルギー導入も含めた災害等に強い市場づくりを強力に進め、より消費者に親しまれる生鮮食料品等流通の中核をなす重要施設として早急に整備を図る必要がある。
よって、市場の再整備にあたって国が求めるコールドチェーンシステム等への対応に努めるためにも、開設者のみならず場内業者が行う事業に対しても、国の「強い農業づくり交付金」に上乗せした支援を要望する。
また、農林水産物の安定供給のためには、福島県農林水産業振興計画「ふくしま農林水産業新生プラン」に定められた流通・消費対策「県内卸売市場の機能強化」が重要であることから、着実な復興に向けた取組を加速させるため、県独自の補助制度を創設するよう要望する。
県においては、「ふくしま・地域産業6次化戦略」に基づき、地場産農林水産物を活用した新商品・新サービス、新技術の開発のために必要な機械・施設の整備に係る各種補助事業を実施しているが、法人格を有する農林漁業者等が事業対象者となっている。
よって、法人格を有しない農業者や任意団体等の6次産業化の具現化に向けた取組に対し、財政措置を講じるよう要望する。
| 農林業の再生、農産物のブランド化に関する取り組みについて |
原子力災害に対する風評被害の払拭、放射線検査の徹底などの周知、また、消費者の不安解消を図るためには、全県をあげた取組が必要不可欠である。
一日も早く農林業の再生を進めていくためにも、効果的かつ実効性のある対策を講じていくことが極めて重要である。
よって、これまで以上に積極的なPR等を講じるとともに、平成27年度においても十分な予算の確保と農産物のブランド化などの事業の一層の充実を図るよう要望する。
農業者が単独で行う施設整備等への
県独自の補助制度拡充について |
中核農家や新規就農者等の農業者が単独で行うパイプハウスや小型農業用機械購入等においては、国による支援制度がなく、県が独自に補助制度を設け、支援している。
しかしながら、この補助制度の全体予算額が十分でなく、この制度を活用し農業用施設や機械を整備しようとしている意欲ある農業者のニーズに応えきれていない。
よって、より多くの農業者のニーズに応えられるよう、農業者が単独で行う施設整備への県独自の補助制度について予算措置を拡充するよう要望する。
| 「変える!大豆・麦・そば生産力等向上支援事業」の拡充について |
「変える!大豆・麦・そば生産力等向上支援対策事業」における生産力向上支援事業(新技術導入支援)については、前年度からの拡大面積のみが対象となっている。
営農の再開を進める上で、生産物の品質の確保を図るため新技術を活用した適期作業が求められるが、作付拡大分のみが対象の場合、生産コストの関係からその活用が厳しい現状にある。
よって、新技術の導入に当たっては、全面積を対象とするとともに、技術の定着に必要な一定の期間を継続的に補助の対象とするよう本事業の見直しを要望する。
また、放射性物質吸収率が低い菜種は、原発事故被災地の農業再開にとって有効な品種であることから、本事業の対象品種とするよう要望する。
農業従事者の高齢化が進む中で、他産業並みの所得が上げられる農業経営を目指し、効率的かつ安定的な担い手が主体となる農業構造に転換を図るべく、園芸作物、畜産、農産物加工等に取り組み、農業経営の複合化・多角化を推進するための各種事業を実施しているところである。
よって、県単独事業の「産地生産力強化総合支援事業」の拡充及び予算の確保を要望する。
「あんぽ柿」は、原子力発電所事故の影響により、平成23年から24年にかけて全面的な加工自粛を要請され、昨年は、「加工再開モデル地区」の指定により一部の地区で加工を再開したものの、県北地方のあんぽ柿生産者のうち約半数にとどまり、震災前の出荷量1,542t(平成20年~平成22年平均)には遠く及ばず、トレー入れの約180tと限定的な出荷となった。
その要因の一つが、昨年開発された非破壊検査機の性能によるものであり、大量の検査に対応できていないことと、トレー入りの小玉あんぽ柿にしか対応できないことから、主力の化粧箱用の大玉の加工・出荷に対応できないことにある。
よって、化粧箱用の大玉あんぽ柿が検査できる高性能な非破壊検査機の早急な開発、及び既存検査機の改造に必要な予算を確保し、全量検査による出荷再開に向けた全面支援について要望する。
多面的機能支払交付金については、農業資源を維持・継承するとともに環境を保全していくための有効な施策である。
よって、平成27年度から新たに協定を締結し、支援を受けながら活動を行いたいとする集落等の新規地区への当該年度の予算とともに、水路や農道など施設の老朽化に対応した長寿命化の取組に対する資源向上支払の予算を確保するよう要望する。
| 農業集落排水事業改築事業に対する補助要件緩和について |
農業集落排水施設が長期にわたり安定した能力を発揮するためには、施設の稼働状況及び経年変化に対応し、処理施設の更新・改造工事が必要となるが、国庫補助事業の要件としては、改築に要する経費が200万円以上で、1点目として「維持管理が適切に行われている施設で、原則として供用開始後7年以上経過していること」、2点目として「対象人口の著しい増加、処理水の水質基準強化、その他既存の農業集落排水施設を取り巻く条件、又は環境の変化が認められること」のいずれかの条件を満たす施設であることとなっている。
県における運用では2点目の条件のみとなっているが、農業集落排水施設は、農村地域の生活環境の改善等において非常に重要な役割を担うものであるため、「維持管理が適切に行われている施設で、原則として供用開始後7年以上経過していること」の条件でも運用するよう要望する。
本事業の実施により、新たな区画整理とこれに付帯する用排水施設、農道の整備、並びに付帯施設の老朽化に対応した更新及び施設の機能向上整備等が進められ、担い手農家の育成、農地の利用集積、農業の生産性の向上・維持・拡大が期待されるものである。
よって、農業経営の安定と規模拡大を図るため、本事業の促進について要望する。
ふくしま森林再生事業は、市町村が森林所有者に代わって森林の有する多面的機能を維持しながら、放射性物質の低減を図るために各種施策を行う事業として平成25年度に県が創設したものである。
しかしながら、県及び国の補助金交付指令手続きの遅れより、年度当初から事業を執行できない状況にあり、特に平成26年度は、交付指令が6月末までずれ込み、3か月間事業に着手できない状態であった。
よって、効率的な事業執行のため年度当初から着手できるよう、指令前着手届等の事務手続き制度の改善などを行い、適切に予算を執行するよう要望する。
山のみち地域づくり交付金により県において事業着手した区間については、地域住民や関係者は事業の早期完了を切望していることから、山のみち地域づくり交付金事業による着手区間の早期完成について要望する。
国では、低炭素社会の実現、コンクリート社会から木の社会への転換、木材自給率50%を目指し、平成21年12月に「森林・林業再生プラン」が策定され、今後10年間を目途に路網の整備、森林施業の集約化及び必要な人材育成を軸として、効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを進め、木材の安定供給と利用に必要な体制を構築することとした。
また、平成23年度から面的まとまりをもって計画的な森林施業を行う林業事業体に対して、搬出間伐等の森林施業を直接支援する「森林管理・環境保全直接支払制度」を導入したことから、これまで山林未利用材として林内に放置されてきた間伐材が、建築用材等や木質チップとして有効利用されるシステムが構築されたところである。
しかしながら、間伐材を搬出するためには、林業の最も重要な生産基盤である路網整備が必要であり、路網については、造林、保育、素材生産等の森林施業を効率的に行うためのネットワークであることから、とりわけその基幹となる林道の整備促進が必要となる。
よって、林道開設事業における継続事業の早期完成が図られる事業費枠を確保するよう要望する。
森林は、木材の生産のみならず水資源の涵養、土砂の流出・法面崩壊の防止、二酸化炭素の吸収、景観の保全など多様な公益的機能を高度に発揮し、地域形成の上に大きな役割を果たしているところである。
しかしながら、カシノナガキクイムシによる広葉樹の枯損被害や松くい虫による松林への被害が拡大しており、森林の持つ多面的機能への影響が懸念されている。
よって、国県主導による大規模な被害防除対策と、国有林の森林病害虫防除事業に対する予算確保、更には市町村における防除事業の取組に対して、市町村の負担が生じない補助事業の創設について、特段の措置を講じるよう要望する。
| 「ふくしま森林再生事業」で供給される間伐材等の有効利用について |
「ふくしま森林再生事業」の本格的な実施に伴い、間伐材等の供給量の増加が予想され、このことによる木材市場への木材供給の過多と原発事故に伴う風評により市場における木材価格の下落が懸念される。
よって、木材需給のアンバランスを未然に防止するため、搬出される木材の有効利用に関する施策を示すよう要望する。
また、木材利用の木材市場の川下側の施設整備等についても「ふくしま森林再生事業」の補助対象とするなど、本事業実施の効果が川上から川下まで森林・林業・木材産業全般に浸透するよう、その条件整備の施策を拡充するよう要望する。
近年、豪雨等の異常気象により、山崩れ、土石流、地すべり、なだれ等の山地災害が多発していることから、安全で潤いのある生活環境を確保し地域振興・発展を図ることが重要である。
よって、山地災害の未然防止はもとより、災害跡地の復旧、さらには水源かん養機能の維持向上など、保安林の機能を強化する治山事業を積極的に推進するよう要望する。
|
◆土木部関係
県施行建設事業負担金については、地方財政法や道路法等に基づき、負担率5~10%の負担金を納入しているところであるが、自治体においては、東日本大震災及び原子力災害による影響を受け税収が著しく低下し、財政の好転が見えない中、災害からの復旧・復興への財源を捻出しなければならない状況である。
よって、県施行建設事業負担金の廃止又は軽減措置を講じるよう要望する。
被災地域の物流機能の回復を図るとともに、一日も早い復旧・復興に向けて、下記道路の整備促進について特段の措置を講じるよう要望する。
1 社会資本整備重点計画に即した道路整備を着実に推進すること。
2 立ち遅れている地方の道路整備を促進するため、地方が真に必要としている道路整備を計画的に進めるため、十分な予算を確保すること。
3 円滑な交通体系の確立及び被災地方の復興を図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路、一般国道、県道、市町村道等の整備に当たっては、採算性のみでなく地域の実情等を十分勘案し、整備促進を図ること。
○特記事項
・地域高規格道路「会津縦貫南道路」
・一般国道115号「相馬福島道路」(早期供用開始)
・一般国道115号「相馬南バイパス」(4車線化)
・一般国道115号「石田地区(局部改良)」
・一般国道118号「須賀川市~会津若松市間(塚松バイパス)」(早期全線供用開始)
・一般国道118号「若松西バイパス」
・一般国道252号「七日町地区」(電線類地中化)
・一般国道288号「船引バイパス」(早期全線供用開始)
・一般国道288号(歩道設置)
・一般国道294号(拡幅)
・一般国道294号「湊町四ッ谷地区~原地区間」(バイパス化)
・一般国道294号「江花地内(拡幅)」
・一般国道349号「杉沢地区、東新殿地区、戸沢地区」
・一般国道349号「下手度~御代田地区(バイパス)」
・一般国道349号「山城舘~元舟場地区(バイパス)」
・一般国道399号「平北目地区(交差点改良)」
・一般国道399号「平市街地~下平窪地区(早期計画策定)」
・一般国道399号「上小川地区」
・一般国道399号「伊達橋架け替え」
・一般国道401号「北会津町地内」(拡幅)
・一般国道459号「岳下地区、大平地区、百目木地区、田沢地区、東新殿地区、西新殿地区」
・主要地方道「原町川俣線」
・主要地方道「小野富岡線」
・主要地方道「小名浜平線(花畑工区、小名浜工区)」
・主要地方道「いわき石川線(湯本跨線橋工区、笠井工区、深山田地区、皿貝工区、才鉢工区)」
・小名浜道路
・主要地方道「川俣・安達線」
・主要地方道「郡山湖南線」(拡幅・歩道設置)
・主要地方道「小野田母神線」(拡幅・歩道設置)
・主要地方道「本宮三春線」(歩道設置)
・主要地方道「本宮熱海線」(改良)
・主要地方道「長沼喜久田線」(拡幅・歩道設置)
・主要地方道「飯野三春石川線」(拡幅・改良)
・主要地方道「郡山長沼線」(歩道設置)
・主要地方道「須賀川三春線」(歩道設置)
・主要地方道「郡山矢吹線」(歩道設置)
・主要地方道「小野郡山線」(拡幅)
・主要地方道「二本松金屋線」(歩道設置等)
・主要地方道「北山・会津若松線」(自転車歩行者道早期整備)
・主要地方道「福島・保原線」(改良)
・県道「安達太良山線」
・県道「馬場平杉田線」
・県道「原町二本松線」
・県道「須賀川二本松線」
・県道「二本松川俣線」
・県道「木幡飯野線」
・県道「石沢荻田線」
・県道「飯野三春石川線」
・県道「本宮岩代線」
・県道「二本松安達線」
・県道「本宮土湯温泉線」
・県道「岳温泉線」
・県道「岳温泉大玉線」
・県道「田村安積線」(拡幅・歩道設置)
・県道「三春日和田線」(歩道設置)
・県道「相馬亘理線」
・県道「吉間田滝根線」
・県道「谷田川三春線」(拡幅)
・県道「石筵本宮線」(改良)
・県道「芦ノ口大槻線」(拡幅・歩道設置)
・県道「荒井郡山線」(拡幅・歩道設置)
・県道「須賀川二本松線」(交差点改良)
・県道「岩根日和田線」(拡幅・歩道設置)
・県道「江持谷田川停車場線」(歩道設置)
・県道「本宮岩代線」
・県道「本宮常葉線」(改良)
・県道「会津若松・熱塩温泉自転車道」
・県道「湯川・大町線」(安全対策)
・阿賀川新橋梁
・八木沢峠(トンネル工事)
4 高速自動車国道の整備に当たっては、地方に新たな負担を求めることなく、早期に完成させること。
また、直轄方式の高速道路の整備に当たっては地域の実情等を十分に勘案し早期着手を図ること。
○特記事項
・東北中央自動車道
・磐越自動車道(4車線化)
・常磐自動車道(早期全線開通・4車線化・復興インターチェンジ設置)
5 整備中のインターチェンジについては早期完成を図るとともに、周辺アクセス道路等についても整備促進を図ること。また、計画中のスマートインターチェンジの早期事業採択を図ること。
○特記事項
・(仮称)大笹生インターチェンジ及び接続する主要地方道上名倉・飯坂・伊達線(早期建設促進)
・福島松川スマートインターチェンジのアクセス道路である主要地方道土湯温泉線(早期建設促進)
6 都市における安全かつ快適な交通を確保するとともに、健全な市街地の形成、活力と魅力ある快適な都市の形成のために、都市計画道路については、まちづくりと一体となった整備を図るとともに、十分な財源を確保すること。
○特記事項
・県道「豊間四倉線」(防災道路・防災緑地整備)
・県道「福島停車場線(駅前通り)」
・都市計画道路「須賀川駅並木町線」
・都市計画道路「藤室鍛冶屋敷線(新横町工区)」
・都市計画道路「亀賀門田線(国道401号~会津総合運動公園間)」(歩道拡幅整備)
・県中都市計画道路事業の財源確保
7 老朽化した道路橋などの社会資本ストックの維持管理・更新費用の財政措置を講じること。
8 市町村道整備補助の増額及び補助対象事業の拡充を図るとともに、県道の認定基準を緩和し、主要市町村道を県道に昇格させること。
9 社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金を増額及び継続するとともに、使いやすい交付金制度とすること。
10 道路の無電柱化を促進するため、必要な措置を講じるとともに、制度の更なる改善を図ること。
11 地方特定道路整備事業の廃止について、計画的な道路整備事業の実施のため、代替措置を講じるなど財政支援を行うこと。
12 冬期間の交通安全のため、大雪等に対応した道路整備や除雪体制の構築等を図ること。
沿岸部は、津波被害により甚大な人的被害と住家被害が発生し、その被害は内陸部まで及んでおり、現在も震災の爪あとが数多く残されている状況にある。
被災地の復興に当たっては、被災しても人命が失われない「減災」の考え方に基づく災害に強い地域づくりが求められており、また東日本大震災復興会議の「復興への提言」では、これまでの防波堤・防潮堤等の「線」による防御から、河川、道路、まちづくりを含めた「面」による防御への転換が必要であるとの考え方が示されている。
よって、沿岸域における被災市街地の復興に向けて、被災市街地のまちづくりに併せた河川、海岸、港湾に加え、津波防災緑地等の津波防災対策及び海岸保全施設の早期復旧について要望する。
東日本大震災からの復興を進めるためには、災害により住居を失った被災者住宅の早期再建や道路の復旧・復興が必須である。
よって、次の事項について要望する。
1 急傾斜地崩壊対策事業の市町村負担金を原則廃止すること。
2 急傾斜地崩壊対策事業に伴う受益者負担金は、県が直接受益者に負担を求めること。
3 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業及び災害関連緊急急傾斜地対策事業の予算を十分に確保すること。
4 現行災害関連対策事業で採択基準外となっている被災箇所を救済すべく、小規模急傾斜地崩壊対策事業を創設すること。
5 小規模な復旧事業については、一箇所における工事費用の補助対象の下限額を見直し、国庫補助事業として実施できるよう従来の災害復旧費用の適用範囲を拡充すること。
6 道路の復旧・復興事業に伴う水道管の移設等の費用について、道路事業の効果促進事業として財源を確保するなど、占用者に対する財政支援を講じること。
河川の未整備区間については、過去数次にわたる出水等により、住宅・農地等に甚大な被害をもたらしており、加えて近年における都市化の進展や流域内の開発に伴い、各河川の治水機能は著しく低下してきている。
よって、国土保全と市民生活の安定を図るため、河川改修・砂防事業の整備促進を図るとともに、特に災害の恐れのある未整備区間について、早急に整備するとともに次の事項について要望する。
1 河川改修事業については、その緊急性を鑑み、大幅な予算の増額を図ること。
2 治水施設整備と併せて、洪水時の河川情報伝達体制の充実・強化など、ハード・ソフトが一体となった対策の推進、並びに洪水時は元より日常時の適切な河川管理の一層の推進を図ること。
○特記事項
・一級河川「東根川」(遊水池整備)
・一級河川「古川」(河川整備)
・一級河川「伝樋川」(河川整備、遊水池整備)
・一級河川「谷田川」(河川改修)
・一級河川「逢瀬川」(河川改修)
・一級河川「油井川」
・一級河川「鯉川」
・一級河川「安達太田川」
・一級河川「針道川」
・一級河川「羽石川」
・一級河川「六角川」
・一級河川「払川」
・一級河川「若宮川」
・一級河川「木幡川」
・一級河川「小浜川」
・一級河川「移川」
3 高水敷上の樹木や経年的な土砂堆積によって生じる中州などについては、洪水時の水位上昇につながることから、流下能力維持のため樹木伐採や下流からの土砂しゅん渫などの対応を図ること。
4 阿賀川旧河川の水質浄化等の再生を早急に図ること。
5 二級河川については、浸水想定区域を早急に見直すこと。
6 夏井川河口閉塞対策工事について、引き続き抜本的な対策を講じること。
二級河川の河川敷の草刈り等については、現在、流域の行政区等の河川愛護団体のボランティア活動により実施されているところであるが、各河川愛護団体から報償の値上げが要望されているほか、住民の高齢化などにより、河川愛護団体の解散・撤退が見受けられている。
また、新規で河川愛護団体を結成した場合、草刈り等の報酬が無償となる「うつくしまの川・サポート制度」が適用されることから、新規の河川愛護団体結成が減少傾向にあり、二級河川の河川敷の草刈り等を地元河川愛護団体等のボランティア活動により継続していくことが年々困難となってきている。
よって、二級河川の適正な維持管理のための草刈り等について、河川愛護団体等に対する財政支援の拡充や、管理者である県の直営による実施など、継続して取り組むことができる体制を構築するよう要望する。
太平洋沿岸の港湾については、津波で甚大な被害を受けており物流機能の回復・強化を図るため、早期に復旧する必要がある。
よって、次の事項について要望する。
1 小名浜港について
(1)東港地区国際物流ターミナルにおける大水深耐震強化岸壁等の早期整備
(2)特定貨物輸入拠点港湾(石炭)としての安定的かつ効率的な海上輸送網形成に向けた取組の実施
(3)エネルギー産業の集積につながる港湾機能の充実
(4)客船誘致のための航路等整備
(5)3・4号倉庫跡地を含めたアクアマリンパーク再整備に向けた検討
(6)小名浜港復旧・復興方針に基づく剣浜(現マリーナ)地区の早期復旧
2 相馬港について
(1)沖防波堤の早期復旧整備促進及び復旧期間中における段階的かつ着実な静穏度の確保
(2)1号~2号ふ頭岸壁等港湾施設の早期復旧整備促進及び復旧期間中における安全な港湾荷役環境の確保
(3)多目的国際ターミナルである3号ふ頭の着実な整備・早期完成と3号ふ頭における大規模地震対策の推進
(4)海上コンテナ航路等利用促進のためのポートセールス活動の強化
(5)5号ふ頭危険物取扱用地の分譲促進及び港湾関連用地の積極的な利用促進
土地区画整理事業は、道路、公園等の都市基盤整備と良好な宅地を総合的に整備することにより、健全な市街地の形成を図ることのできる、まちづくりの根幹的事業である。
よって、住みよい生活環境や円滑な都市活動を実現するため、十分な予算を確保するよう要望する。
下水道は、地域の生活環境、公共用水域の水質改善に必要不可欠な施設であるとともに良好な水循環を維持するなど、環境保全にも大きな役割が期待されている。
しかしながら、下水道整備には多額の費用を要するため、現在の厳しい財政状況において、財源確保に苦慮している状況にある。
よって、本事業の整備促進が図られるよう当該補助金の拡充、補助率の復元及び資本費の負担継続を要望する。
また、「猪苗代湖及び裏磐梯湖沼水環境保全推進計画」において、下水道や農業集落排水施設等の整備及び接続加入の促進について盛り込まれていることから、猪苗代湖及び裏磐梯湖沼周辺の下水道整備や接続促進に対する新たな補助制度を創設するよう要望する。
原子力発電所事故による避難者支援の応急仮設住宅用地として、市町村から無償で県に提供してきたところであるが、市町村においては厳しい財政状況の中、新たな財源の確保を図るため、保有財産の有効活用に取り組んでいるところである。
よって、原子力災害に伴う避難等が長期化すると予測されることから、仮設住宅用地の賃貸料について財政措置を講じるよう要望する。
庁舎は、災害時の防災拠点としての機能を有しており、耐震性が低い庁舎については、早急に耐震化を図る必要がある。
耐震改修について、社会資本整備総合交付金事業及び防災・安全交付金事業の住宅・建築物安全ストック形成事業などは耐震改修工事については補助対象経費の限度額が定められていることや、耐震改修に当たっては仮設庁舎の建設、執務室の移転等を要することもあり、財政負担が大きいものである。
また、津波被災地区の復旧・復興や原子力災害対策などの事業量が増大する中、これらに対応するため、一般財源を優先的に充当していることを背景に、一般財源の負担が大きい現行の補助制度においては、住民の安全・安心の確保の中心的役割を担う、災害対応の拠点となるべき庁舎について、抜本的な対策を講じることが難しい状況にある。
よって、庁舎の耐震改修を早期に進めるため、工事に係る限度額の拡充や補助率の嵩上げについて、特段の措置を講じるよう要望する。
|
◆教育庁関係
原子力発電所事故による放射線の不安から多くの児童が転校しているため、新たに複式学級が発生しており、教育環境の悪化が懸念される。
これからの学校はゆとりある環境のもと、児童生徒一人ひとりの状況に適合した学習指導、生徒指導を行い、個々の個性や能力の伸長を図る必要がある。
よって、次の事項について要望する。
1 少人数学級編制制度の継続及びより一層の拡大、充実に向け、学力向上及び生徒指導充実のための常勤講師の加配を行うとともに、そのために不足する教室、備品等の確保に必要な財政的補助を講じること。
2 複式学級編制基準を弾力的に運用すること。
3 特別支援教育充実のため、特別支援学級の基準を弾力的に運用できるようにするとともに、恒常的に支援員等を配置できるよう新たな補助制度を創設するなど支援策を講じること。
4 学校・家庭・地域環境の改善に向けた支援ネットワーク構築のために大きな役割を果たしているスクールソーシャルワーカーを継続的に配置するとともに、増員を図ること。
5 児童生徒が抱えている心の問題を解決するため、今後も引き続きスクールカウンセラー活用事業を実施するとともに十分な予算を確保すること。
6 校医を活用した放射線に関する教育や体力づくりなど、放射線の影響と体力低下が危惧される子どもの心身をケアする施策を実施するとともに財政支援すること。
7 学校司書の配置促進及び資質向上等を図るため、県独自の具体的制度や基準を創設し、適切な予算措置を講じること。
東日本大震災や原子力発電所事故に伴い、子どもたちの心のケアやきめ細かな指導など一人ひとりに寄り添う指導体制が喫緊の課題となっている。
よって、次の事項について要望する。
1 震災・原発事故に対応するため、標準法定数の弾力的運用及び中・長期的な計画の下で加配を実施すること。
2 不登校対応や教科教育の充実のための専科教員の配置を行うこと。
3 複式学級解消等に向けた講師等の人的加配を拡充すること。
4 中学校における免許教科外指導解消のための加配教員を増員する こと。
原子力発電所事故による児童生徒への健康被害・夏期の暑さ対策として、小中学校のエアコン導入については、学校施設環境改善交付金(空調設置)が設けられているが、補助基準㎡単価20,500円、補助率3分の1と実施単価を大きく下回る実情にある。
よって、小中学校へのエアコン設置費用を全額補助するよう要望する。
また、リース方式により導入する場合においても国庫補助が活用できるよう特段の措置を講じるよう要望する。
国においては、第2期教育振興基本計画における目標水準の達成に必要な所要額を計上した「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画」に基づき、小中学校のICT環境の整備を進めるための地方財政措置を講じているが、地方交付税による財政措置であり、目標達成に向けた整備を進めるに当たり、自治体の実質負担が大きいため、かかる予算確保が困難な実情にある。
よって、地方交付税による財政措置ではなく、全額補助または高い補助率による補助制度の創設について、特段の措置を講じるよう要望する。
学校等の公立文教施設については、東日本大震災においても市町村の応急避難場所として重要な役割を果たす施設となっており、地域住民の安全・安心を確保するためにも、その耐震性能の確保は最優先課題である。
市町村の財政状況が極めて厳しい状況にある中、早急に耐震化を進めるためには、市町村の財政負担の軽減、国・県による財政措置の拡充が重要である。
よって、公立文教施設等の速やかな耐震化及び災害時の避難施設としての整備等に係る財源の確保並びに校舎増改築、屋内運動場改築、プール建造等に係る財源の確保について、特段の措置を講じるよう要望する。
公立学校施設の耐震性能の向上に係る国庫負担率の
引上げについて |
東日本大震災により多くの公立学校施設が被災したため、早急に耐震性能の向上を進めていく必要があるが、国の耐震化事業の補助率はIs値が0.3以上の建物については2分の1となっており、さらに改築を伴う補助単価が実施単価を下回っていることから、自治体の財政負担が多くなり、耐震化率向上の阻害要因となっている。
よって、公立学校施設の耐震化事業補助率を一律3分の2とし、補助単価を実施単価とする国庫補助制度の見直し及び平成27年までを時限とする地震防災対策特別措置法の期限延長について、特段の措置を講じるよう要望する。
小中学校の県費負担教職員の旅費は、県が負担することとなっているが、近年旅費の削減が続いており、教職員の研修会等への参加が困難な状況となっている。
校長は、県配分予算の範囲内で出張命令を出すこととなっているが、教育活動に必要不可欠な児童生徒の引率業務や校外学習前の安全確認のための点検業務をはじめ、当面する教育課題解決のための必要な教職員研修や諸会議等への出張命令が出せない事例も出てきており、学校運営や教育行政に重大な支障が出ている。
よって、円滑な学校運営が図られるよう、県負担旅費の十分な確保・配分を要望する。
原子力災害により避難を強いられている相双地区の教育は、放射能の健康不安と隣り合わせの中、教育環境の不十分な仮設校舎で奮闘している教職員、震災関連業務の長期化による心身の疲労の蓄積が懸念される教職員、単年ごと勤務の精神的なストレスを抱える兼務教職員等、さまざまな教職員の献身的な勤務によって支えられている。
このような状況において、今後、人事異動で勤務を希望する教職員が減少し、このままでは当該地区の教育が先細りすることが懸念されている。
よって、当該地区に勤務する教職員及び兼務教職員を対象に、教職調整額、主任手当等とは別に「復興手当(仮称)」を創設し、支給するよう要望する。
| 放射線量の低い地域における児童生徒等の体験活動支援について |
風評被害により教育旅行の入込み状況は甚大な影響を受けている。
この状況の中、ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業については、多くの子どもたちが、夏休み等に心身ともに伸び伸び自然活動や交流活動等ができる機会の創出及び受入地域の活性化に大きな役割を果たした。
しかしながら、支援事業によっては、補助対象が学校の住所を置く市町村外で、さらに宿泊を伴わなければならないものや県内での活動に限定するなどの条件となっているため、一部の体験活動が補助対象外となっている。
よって、平成27年度についても本事業を継続するとともに、補助額の増額及び利活用しやすいように補助対象要件の拡充について要望する。
国・県・市がそれぞれ指定した文化財について、保存や修理を行う所有者に対し補助金を交付するなど財政的な援助を行っている。
また、県においても、国や県指定の文化財に対して、文化財保存活用事業補助金交付要綱や同補助金取扱要領等により、財政的援助を行っているところであるが、文化財を収蔵・展示・公開する施設整備・保管にかかる市町村の負担は大きなものとなっている。
よって、国民の貴重な財産である文化財を後世に伝えていくという文化財保護法等の趣旨に鑑み、文化財保護事業費補助金について、これまでの補助率を維持するよう要望する。
また、文化財の保存施設の整備等にかかる経費について財政支援するよう要望する。
東日本大震災により多くの文化財が壊滅的な打撃を受け、その完全なる復旧が望まれている。
国指定文化財については、手厚い災害復旧補助が制度化されているが、県指定文化財については、現行では補助率が総事業費の2分の1ではあるものの、予算規模が少ないため必要となる復旧事業を実施できず、また、国指定文化財に関する災害復旧について県の補助制度がないことから、市町村や所有者の財政負担の割合が大きく、復旧事業の障害となっている。
よって、早急な文化財の復旧を推進するため、次の事項について要望する。
1 国指定文化財にかかる災害復旧事業についても、補助制度を創設すること。
2 被災した県指定文化財の復旧に関する補助金について、災害復旧事業として国と同様の補助率に引き上げ、確実な文化財の復旧ができるよう支援すること。
3 指定文化財にかかる防災事業を充実させること。
4 復旧事業に必要な予算を確保すること。
国際化の進展に伴い、小中学校における英語教育の充実が求められている中、自治体においては、JETプログラムの活用による語学指導外国人の確保を図ってきたところである。
また、英語教育の一層の充実強化を図るため、小学校から中学校までの9か年を見通した系統性のある英語教育を目指し、従来からの
JETプログラムの活用による語学指導外国人に加え、自治体の独自雇用により語学指導外国人を増員しているが、財政的に厳しい自治体にあっては、外国人語学指導助手を思うように雇用することができず、小学校の英語活動の充実について格差が生じている状況にある。
よって、自治体が単独で雇用する語学指導外国人に対する財政措置を講じるよう要望する。
東日本大震災により被災し、経済的理由により就園・就学が困難となった児童生徒が持続的かつ円滑に義務教育を享受できるよう就園・就学の支援については、被災児童生徒就学支援事業補助金により平成26年度までの予算措置がなされているが、被災地域については今後の動向が予測できない状況にあるため、引き続き財政支援が必要である。
よって、被災児童生徒等就学支援事業補助金を継続するよう要望する。
中山間地域における人口減少は深刻であり、複式学級となる学校が増加している中、一定規模の児童生徒が集い、学ぶことができる環境を整備する観点から、広域的な複数の小中学校統合が行われているが、統合により新たな学校への通学距離が長くなるため、将来にわたって適正に通学支援を継続していくことが不可欠となっている。
市町村が通学支援を行う場合、現在の国の財政支援のうち、へき地児童生徒援助費等交付金については、国庫補助の開始から5年間という年限があり、また、普通交付税による措置については、スクールバスの定員が10名以上という算定基準があることから、通学支援の継続のための安定的な財源の確保や小規模な小中学校での実施が困難となっている。
よって、へき地児童生徒援助費等交付金に基づくスクールバス・ボートの委託料に係る年限の廃止及び普通交付税算定基礎となるスクールバス・ボートの定員基準の緩和について、特段の措置を講じるよう要望する。
県教育庁では、県内の適正な人事交流を目的とし、教職員は3管内3地区(A地区:市・主要町村の学校、B地区:平地の学校、C地区:へき地の学校)で一定期間勤務することが求められている。
しかしながら、震災及び原子力災害により仮設校舎へ入居している小学校については、同じ仮設校舎に入居しているにも関わらず従来の制度のまま区分がなされており、現場の教職員からも区分の整合性がとれていないとの指摘がある。
よって、へき地校に区分されている小学校と同一仮設校舎に入居している小学校については、少なくとも自校に帰還するまでの期間について、物的・精神的困難性の観点から「みなしへき地校」に加え、学校間の不均衡を調整するよう要望する。
| 避難指示区域内における県立高校早期再開に向けた整備について |
現在、県立小高工業高校及び小高商業高校については、仮設校舎で教育活動が行われている。
自治体においては、帰還困難区域及び津波被災地を除く避難指示区域内において、道路、上下水道などのインフラ整備及び同区域内の全ての小中学校について平成25年中に復旧が完了したところである。
また、地元の企業においては、新規採用にあたり実業系高校生のニーズが高くなっているため、教育環境の充実が必要である。
よって、両高校の除染をはじめ、施設の修繕等を実施し、本校舎の再開に向けた取組を進めるよう要望する。
学校給食に使用する食材については、児童生徒の保護者はもちろん市民などからも強い要望があり、自治体では、給食調理場に学校給食用食材の放射性物質測定検査機器を導入するなど、安全性の確保に努めている。
検査機器整備後も、検査要員経費や検査試料代等が毎年必要となるが、平成26年度においては、検査機器の校正費を除き国の震災復興特別交付税での措置となったが、当該交付税の終了期限については不明確となっている。
よって、継続的に安定して検査を実施する体制を確保するため、学校給食検査体制支援事業補助金を復活措置するよう要望する。
国の経済財政運営と構造改革に関する基本方針においては、国及び自治体の事務事業の民間への移管を推進することとしており、総務省においては、地方交付税の算定について、これまで自治体直営の場合の経費を基準としていたものを民間委託の費用に改めることとされたところである。
小中学校の給食業務もこの対象事業とされており、順次進めているところであるが、全ての学校を委託していくためには、給食業務において必要不可欠な栄養管理はもとより、「O-157事件」以来その基準が厳しくなった衛生管理、さらには学校給食における食物アレルギー対策や放射性物質に対して適正に対応していくため、学校栄養職員の配置を促進することが必要である。
よって、学校栄養職員の配置を促進するよう要望する。
|
◆警察本部関係
現在、即日交付ができる運転免許センターは福島と郡山にあり、両免許センターの免許更新の利用状況は、平成24年度の福島は約6.7万人であったのに対し、郡山は約9.2万人と郡山の利用者が約2.5万人多い結果になっている。
休日については、福島が土曜日閉庁、日曜日は運転免許更新のみを取り扱い、郡山は土曜日閉庁、日曜日は、第2・第4に限り午前予約制、午後は通常通り開庁し、免許更新を取り扱っており、現在、郡山運転免許センターでの日曜日更新者の数は、1か月1,200人となっている。
よって、近隣市町村等広範囲に及ぶ地域における利用者の利便性を高めるため、郡山運転免許センターの毎日曜日と土曜日開設を要望する。
|