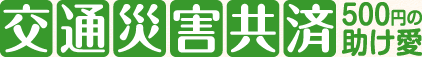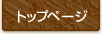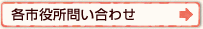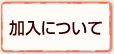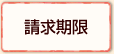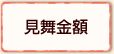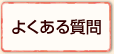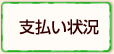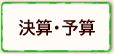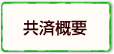19.外国において、交通事故にあった場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
共済条例第2条「日本国内において発生したものをいう。」と規定されている。
20.外国人登録をしている者で、市民交通災害共済に加入している者が印鑑を所有しない場合、申請書は拇印でもよいか。
差し支えない。
なお、外国人の場合は、外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律第1条により、印鑑は不要で署名のみでよいとされている。
(外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律第1条)
法令の規定により署名、捺印すべき場合に於いては外国人は署名するを以て足る。
21.未成年者は請求行為を行えるか。
請求人が未成年の場合は、親権者又は後見人が請求を行うものとする。
22.婚姻をしている未成年者は、見舞金の請求をできるか。
請求できる。
(民法第753条)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
23.会員が年度途中で県内の他市に転出した場合、転出先の市で見舞金の請求はできるか。
請求できる。
会員台帳により、共済への加入の確認が出来れば、転出先の市に請求をしても問題ない。
24.交通事故証明書が人身事故でなく、物件事故扱い(名前が記載されていないもの)の場合、見舞金を請求できるか。
請求できる。
この場合、物件事故証明書(名前が記載されていないもの)の他、医師の診断書、自認書が必要です。
25.自動車を運転中、自損事故をおこしたが物件事故として処理をしたため、事故証明書に名前が記載されなかった。この場合、見舞金を請求できるか。
請求できる。
この場合も(24)と同様の扱いとなる。
26.条例施行規則第4条第2号に規定する「交通事故に関し権限を有する機関の発行する交通事故の事実を証する書類」とは何か。
次に掲げる者の発行する書類をいう。
- 学校長
- 消防(署)長
- 警察署長
- 労働基準監督署長
- 鉄道公安室長
- 救急車を常設する病院での救急車による搬送証明書(病院長)
27.自転車による自損事故で、救急車で病院に運ばれた場合、見舞金の等級はどうなるのか。
交通事故証明書が必要であるが、交通事故証明書が得られなかった場合、救急車を常設する病院での救急車による搬送証明は、通常の事故証明書と同様に扱う。
28.郵便局職員が配達途中、バイクで転倒しけがをしたが、警察に届けなかったために事故証明書がでなかった。この場合、郵便局長の証明でも見舞金は支給できるか。
支給できない。
所属長(会社社長等)の証明は(26)の証明には該当しない。
29.交通事故の届け出をしなかったために、交通事故証明書は得られなかったが、自賠責保険金は支払われた。この場合の取り扱いは.
条例施行規則第4条第2号に規定する交通事故証明書が得られなかったものにあって保険会社へ事故証明入手不能理由書等の提出により自賠責保険金が支払われた場合は、自認書、人身事故証明書入手不能理由書により見舞金を支給するものとする。
なお、人身事故証明入手不能理由書については写で差し支えない。
30.上記の例で保険金は支払われなかったが、自認書のみで、見舞金は支給できるか。
支給できない。
条例施行規則第4条の2第3項に規定する書類は、いずれも必ず添付するものとする。
31.任意保険会社が代行して自賠責分も含んで保険を支払い、後日保険会社同士で精算するといった方法をとっている場合がある。その際送付される「人身障害支払通知書」を「自賠責保険損害賠償額支払通知書」の代わりとして提出した場合も見舞金を支給できるか。
支給できる。
この場合も(29)と同じく見舞金を支給するものとする。
32.医師の診断書の代わりに診療の領収書でも見舞金の請求をできるか。
請求できない。
診療の領収書からは交通事故によって通院したものであるかの確認が困難なため認めていない。
33.交通事故により骨折しギブスで固定し自宅療養した。この場合、治療実日数に含まれるか。
含まれない。
実際に入院・通院した日数を基準にしており、自宅治療若しくは、投薬等の期間は含まれない。
34.治療のための温泉(湯治)療養は見舞金算定期間に入るか。
通常一般の温泉地での療養は、期間に入らない。ただし、治療を目的としたりリハビリテーション等その他医師の監督下における治療は認める。
35.交通事故に遭うも、特に外傷がなかった。しかし、念のため病院で検査をした場合、通院として治療実日数に含まれるか。
含まれる。
36.往診は治療実日数に含まれるか。
含まれる。
37.同じ日の午前中にA病院で治療し、午後にB接骨院で施術を受けた場合、見舞金算定期間はどうなるか。
同一日に複数の病院等で治療を受けた場合でも期間は一日として計算する。
38.交通事故に遭い、通院中に再度事故にあった場合の申請はどうなるのか。
見舞金はそのつど支給する。ただし、重複して通院した日数は1日として計算する。
39.当初8等級の見舞金の支給を受けたが、治療が長引いた場合はどうなるか。
交通事故にあった日から1年以内に障害の程度が上級に移行すればその差額を支給する。
40.請求期間は。
請求期間は弔慰金、見舞金、重度障害見舞金ともに交通事故にあった日から2年間のうちに行わなければならない。
41.交通事故にあってから1年以上治療を続けている場合、見舞金算定期間は。
この制度は交通事故にあった日から1年間の障害の程度に応じ見舞金を支給するもので、1年を越える治療期間については、対象とならない。
42.交通事故により負傷し、入院していたが、入院中に他の病気が原因で死亡した場合弔慰金を支給できるか。
交通事故による負傷の治療のみを支給対象とし、死亡については交通事故との因果関係が認められる場合を除き支給対象とならない。
43.交通事故にあって長期間入院し治療したが、障害が残り、重度障害者として申請することになった。医師の診断・認定審査会の決定を待ち、認定されたの が事故のあった日から、1年を経過してしまった場合、重度障害見舞金は支給できるのか。また、1年以内に認定された場合、何を申請書に添付すればよいの か。
支給できる。請求期間は認定を受けてから2年間とする。
(共済条例第9条)
重度障害見舞金の申請書類は、交通事故証明書、後遺障害診断書を添付する。
44.重度障害見舞金とは。
自動車損害賠償保障法施行命(別表)の第1級又は第2級に該当する障害となったときに、見舞金の他に重度障害見舞金として30万円を支給する。なお、請求期間は認定を受けてから2年間とする。
45.重度障害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合。
重度障害見舞金を受け、その後(交通事故発生の日から1年以内)死亡したときは、その差額を支給する。
〈例〉
(見舞金請求+重度障害請求)+弔慰金請求=弔慰金
3等級 重度障害
(200,000円 + 300,000円)+ 550,000円 =1,000,000円
46.会員が交通事故で死亡した場合、共済弔慰金受け取り人ををあらかじめ指定していたが、指定されていた者が既に死亡していた場合、請求者は誰になるのか。
会員の遺族とする。
請求する者の順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順である。(共済条例施行規則第6条)
47.事業所等の雇主は弔慰金受取人になれるか。
なれない。
この場合の受取人は、会員の遺族である。
48.交通事故で死亡したが、身寄りがないため町内会長が葬儀を執り行った。共済弔慰金の受取人がいない場合の取り扱いは。
共済条例施行規則第5条および第6条に規定する「あらかじめ指定した受取人」、「遺族」がいない場合は、葬祭執行者に対して、25万円を葬祭費として支給する。
49.本共済の加入掛金は、所得控除の対象となるか。
所得税法に定められた控除対象とならない。
50.災害見舞金等の支払を受けた場合、所得税の対象となるか。
所得税法施行令第30条第3項に該当し、非課税対象となる。
(所得税法施行令第30条第3項)
「非課税とされる保険金、損害賠償金等」心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金