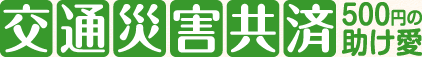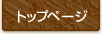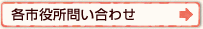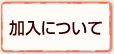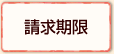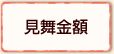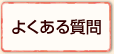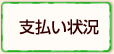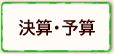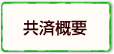51.「一般交通の用に供するその他の場所」とは。
- 不特定多数の人、車両が自由に通行できる状態になっている場所は道路の範ちゅうである。
- 校庭、遊園地、公園、社寺の境内、私有工場の敷地内の空地等であっても、一般交通の用に供されている場所は道路にあたる。
- 道路工事のため、道路標識をもって一般の通行が禁止された場所であってもこれは一時的に行う道路管理上の措置にすぎないので、道路と解すべきである。
52.農道は道路か。
道路である。
53.ガソリンスタンドの敷地内は道路と判断してよいか。
(51)の例により判断すべきである。
54.田畑の中での耕運機による事故は対象となるか。
対象とならない。
55.自動車教習所内での事故は対象となるか。
対象とならない。
ただし、仮運転免許中による路上での教習中の事故は対象となる。
56.ビル建設工事現場内での事故は対象となるか。
対象とならない。
57.宅地造成区域内での事故は対象となるか。
対象となる。
ただし、次の例にあたるもの及び宅地造成作業従事者は除く。
「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現に公衆、すな わち不特定多数の人、車両等の交通の用に供されている場所を指し、必ずしもいわゆる道路の形態を備えていることまで必要とするものではないが、当該場所の 管理者が一般交通の用に供することを認めていない場所、すなわちその場所の通行につき、管理者の許可ないし、了解を要する場所で、しかも客観的にも不特定 多数の人、車両等の交通の用に供されているとみられる状況にない場所はいわゆる道路としての要件を欠くものと認められる。
58.道路建設中で供用開始前の道路における事故は見舞金を支給できるか。
支給できない。
供用開始前の道路とは、一般交通の用に供するその他の場所(現に一般公衆及び車両等の交通の用に供されているとみられる客観的状況のある場所で、しかもその通行することについて、通行者が管理者の許可などを受ける必要のない場所)に該当しない。
59.道路工事のため、道路標識をもって一般の通行を禁止している場所での交通事故は見舞金を支給できるか。
支給できる。
一般の通行を禁止された場所であっても、交通の危険を防止するため一時的に行う道路管理上の措置にすぎず(道路法第46条第1項、第48条第1、2項)、道路本来の目的効用を達成するための措置であり、道路とされるため、見舞金の支給対象となる。
60.身体障害者の車いす、高齢者用電動車両、小児用の自転車等は対象となるか。
対象とならない。
道路交通法第2条第3項「身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者。次条の大型の自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者」は歩行者と規定されている。
61.小児用の自転車等(三輪車、補助車のついている小児用自転車、うば車)とはどのようなものか。
小児用自転車とは次の各号に該当するものをいう。
- 走行時速が4キロ~5キロぐらいであること。
- 慣性走行装置がないこと。
- 補助車があること。
- 原則として16インチ以下であること。
- 作成目的が小児用であること。
- 大きさが小児用であるもの。
- 以上の小児用の車に大人が乗った場合でもその車の属性によって判断して小児用とすること。
62.祭りを見物中、山車にぶつかり負傷した。この場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
山車は道路交通法に規定する車両(軽車両)と認められる。この場合も交通事故証明書が必要である。
63.遊園地の乗物(ゴーカート、豆電車、モノレール等)による事故は見舞金を支給できるか。
支給できない。
遊園地の乗物は、共済条例第2条に定める車両に該当しない。
64.馬に蹴られて負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
ただし、道路交通法第2条第11号の規定により牛馬は軽車両とされているので、道路上の事故によるものは支給できる。
65.自転車で走行中、転んで負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
自転車による事故について、交通事故証明書が得られない場合は「目撃者証明書」により10等級の額を支給する。
66.バイクでの自損事故の場合「目撃者証明書」でも見舞金を支給できるか。
支給できない。
「目撃者証明書」は自転車についてのみ適用するものである。
67.「目撃者証明書」の目撃者は、両親でもよいか。
差し支えない。
68.「目撃者証明書」の目撃者が子供の場合は。
保護者が連記し押印すること。
この場合、子供とは「中学生以下」をいう。
69.自転車と歩行者の接触事故の場合でも見舞金は支給できるか。
支給できる。
この場合も交通事故証明書が得られないときは、目撃者証明書により支給する。
70.自転車で走行中、誤って道路上の看板にぶつかりけがをした。この場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
(65)の例による。
71.自転車同士で衝突をした場合でも見舞金は支給できるか。
支給できる。
(65)の例による。
72.自転車に子供を同乗させて走行中、子供がダイヤのスポークに足をはさんで負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
ただし、16才以上の者が6才未満の者を正当な設備(手かけ、足かけ、腰かけ)をした自転車に同乗させた場合の事故についてのみ適用する。
73.道路上を電動式キックボードで走行中に自損事故によりけがをした場合、目撃者証明書により見舞金を支給できるか。
支給できない。
目撃者証明書は、自転車の事故についてのみ適用するものである。
74.バイク(又は自転車)をひいていて、側溝に落ち負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
道路交通法第2条第3項第2号により大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者は歩行者と規定されている。
75.駐めたおいた自転車を子供がいたずらをして指をはさんで負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
交通事故とは認められない。
76.自転車に大人が二人乗りをして転倒負傷した場合、二人とも「目撃者証明書」扱いとして見舞金を支給できるか。
支給できない。
運転者も自転車の荷台に乗っていた者も見舞金は支給できない。
77.学校の校庭で自転車の交通安全教室の際に、転倒しけがをした。この場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
特定の者を対象とした校庭での行事(交通教室、運動会等)は道路とは判断しがたい。
78.放課後、校庭で自転車で遊んでいた児童が転倒しけがをした場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
道路とみなされる状況にある校庭での事故は対象とする。
79.交通事故にあった会員が前途を悲観して自殺をした。この場合、弔慰金は支給できるか。
支給できない。
会員の故意によるものであるときは支給できない。
80.友人の自動車の助手席に同乗し負傷した。ところが、友人は無免許運転であった。この場合の取り扱いはどのようになるか。
同乗者(会員)が無免許運転、若しくは酒気帯び運転の事実を察知しうる状況にある場合は条例第10条の規定により支給できない。
81.夫が免許停止中であることを知りながら、妻(会員)が同乗し死傷した場合、支給できるか。
支給できない。
82.少量の酒を飲んで交通事故を起こした場合は、支給対象になるか。
対象とならない。
83.飛行機、船舶による事故は対象となるか。
対象とならない。
道路交通法第2条第8号に規定する「車両」にあたらない。
84.電車の乗降の際、ドアにはさまれ負傷した場合、対象となるか。
対象とならない。
電車の搭乗者は対象とならない。
85.しゃ断機、警報機がともにない踏切での自動車と電車の衝突事故は対象となるか。
対象となる。
しゃ断機、警報機のない踏切での事故並びに同踏切での歩行者の事故については支給対象になる。
ただし、しゃ断機が閉じているとき又は警報機が鳴っているときに車両等が通過した際の事故については支給できない。
86.踏切道のない線路を横断しようとして列車にはねられ負傷又は死亡した場合、見舞金又は弔慰金を支給できるか。
支給できない。
踏切道以外での列車による人身事故は交通事故とは認められない。
(共済条例第2条第1項第1号)
車両の道路における交通による人身事故(自損事故を含む)、又は、これら車両の道路における交通以外の運行による人身事故(自損事故を除く)。
87.幼児が踏切に入って死傷した場合は支給できるか。
支給できる。
88.電車の脱線事故による乗客は支給対象となるか。
対象とならない。
電車の搭乗者は対象とならない。
89.バスとはどこまでを言うのか。(路線バス、観光バス、送迎バス等)
道路交通法の車両(道路交通法第2条第8号)に該当するものであれば、バスの種類を問わず、見舞金支給の対象となる。この場合も、交通事故証明書は必要である。
90.バスが急ブレーキをかけたため乗客が負傷した場合、支給対象となるか。
対象となる。
ただし、当然「交通事故証明書」は必要である。
91.バスの乗降の際、ステップで足をすべらし負傷した場合、支給対象となるか。
対象とならない。
交通事故とは認められない。
92.停車している車両から落ちて負傷した場合、支給対象となるか。
対象とならない。
交通事故とは認められない。
93.タクシーが事故をおこし、乗客がけがをしたが物件事故として処理したため事故証明書に乗客の名前が載っていなかった。この場合、タクシーの運転手が乗客を乗せていたと証明すれば見舞金は支給できるか。
支給できる。
この場合、交通事故証明書の他、医師の診断書、自認書が必要である。
94.道路における交通以外の運行による人身事故(自損事故を除く)とは、どのような事故を指すのか。
道路上での車両の運行で発生した人身事故を指し、例としては、当該車両が交通以外の目的をもって作成されたもの(クレーン車、ショベルカー等)による事故を対象としている。
95.クレーン車が道路上において看板等を取付中、誤ってそれが落下し通行中の歩行者を負傷させた場合、支給対象となるか。
支給対象となる。
共済条例第2条「車両の道路における交通以外の運行による人身事故(自損事故を除く)。」の範ちゅうである。
96.バイク(自転車)で走行中、脳出血をおこし、死亡したものと医師が推定される事故で、診断書が高血圧による脳出血で病死とされた場合は支給対象となるか。
支給対象とならない。
死亡の原因が交通事故との因果関係が認められない場合は支給対象とならない。
97.自動車を運転中、誤ってガードレールに激突、警察署へは届けないため「目撃者証明書」扱いとしてよいか。
支給対象とならない。
98.幅員の狭い道路を走行中、対向車が急に寄ってきたため、危険を感じ避けようとしたところ誤って側溝に落ち負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
交通による事故とは認められない。
99.自動車のはねた石が頭に当たり負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
この場合も交通事故証明書が必要である。
100.故障のため、道路上において自動車の下にもぐって修理中、突然車が動き出し負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
101.自動車を運転中、荷台につけていた荷物が落ち歩行者にあたって負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
102.車の後を押している途中、急に発進したため負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
103.駐めておいた車に子供がいたずらし負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
104.エンジン故障のため、けん引されていた車による事故の場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
105.自動車を停止して運転者又は同乗者が降りようとドアを開けたとき、他車が接触したため負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
106.自動車の運転を誤って道路わきの家屋に突入し、家の中にいた人が負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
107.公園内で、通行人と自転車が接触事故をおこした場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
公園内であっても一般交通の用に供されている場所は道路にあたり、支給できる。
108.駐車していた車の中で子供が窓の開閉をしている際、誤って自分の手を挟んだ場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
109.歩行中に駐車中の自動車にぶつかり転倒して、負傷した。見舞金は支給できるか。
支給できない。
車両の交通による事故とは認められない。
110.農道を耕運機で走行中に、電柱にぶつかり負傷した場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
「農道」は「一般交通の用に供される場所」に該当し、「道路」である。ただし、車両登録した耕運機であること。
111.畑で作業をしていたら、駐めておいた耕運機が動き出し、耕運機を避けきれず下敷きになって負傷してしまった場合、見舞金は支給できるか。
支給できない。
畑は道路とみなすことができず、支給できない。
112.バスに乗車していたが、バスが対向車と衝突したため、乗客はけがを負った。ただし、この運転手は、免許停止中であった。この場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
乗客(会員)が無免許運転の事実を察知しうる状況にある場合は、条例第10条の規定により支給できないがバスの運転手が無免許運転であることは、通常、乗客は知りえないので、乗客は見舞金の支給対象である。
ただし、運転手については共済条例第10条の規定により支給対象外である。
113.自転車を自宅の敷地内で運転していたが、運転を誤り敷地内の畑に転落し負傷した。この場合、見舞金は支給できるか。
不特定多数のものが出入りできる敷地内であれば、道路とみなされ支給できる。
114.自動車の荷台に乗っていたが、振り落とされ荷台から転落し、けがを負った。この場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。
ただし、道路交通法第55条第1項又は第56条第2項に該当する場合に限る。
(道路交通法第55条第1項)
車両の運転者は、当該車両のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自転車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最低限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
(道路交通法第56条第2項)
貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可したときは、前条第1項の規定にかかわらず当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
115.自動車を運転中、信号待ちのため車を停止していたが、後方から来た自動車が前方不注意のため自車に衝突し、その勢いで、自車の前方に停止していた自動車に追突し、皆、けがを負った。この場合、見舞金は支給できるか。
支給できる。